TOP > レポート&コラム > ISASニュース > 連載の内容 > 研究紹介
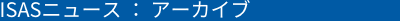
連載の内容 / 研究紹介
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年
1997年
1996年
1995年
1994年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 155(1994年2月) |
宇宙輸送の革新 |
稲谷 芳文 |
| 156(1994年3月) |
流れのシミュレーション |
桑原 邦郎 |
| 157(1994年4月) |
宇宙におけるひもの利用 |
小山 孝一郎 |
| 158(1994年5月) |
ガンマ線バースト天文学 |
村上 敏夫 |
| 159(1994年6月) |
空気を利用した推進エンジン |
棚次 亘弘 |
| 160(1994年7月) |
衛星異常診断システムの開発 |
橋本 正之 |
| 162(1994年9月) |
宇宙で電場を測る |
早川 基 |
| 163(1994年10月) |
無衝突衝撃波による高エネルギー・プラズマ粒子加速 |
星野 真弘 |
| 164(1994年11月) |
宇宙に翔びだす生き物たち |
黒谷 明美 |
| 165(1994年12月) |
超流動ヘリウムとIRTS |
村上 正秀 |
1993年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 143(1993年2月) |
微小重力下における動物の姿勢調節 |
渡邉 悟 |
| 144(1993年3月) |
ペネトレータの開発 |
藤村 彰夫 |
| 145(1993年4月) |
深宇宙探査機によるオカルテーション観測 |
山本 善一 |
| 146(1993年5月) |
ハレー彗星、月、そして惑星へ |
石井 信明 |
| 147(1993年6月) |
簡易型機構の研究 |
樋口 健 |
| 148(1993年7月) |
太陽系前駆物質、微粒子の集積、そして小惑星 |
杉浦 直治 |
| 149(1993年8月) |
太陽系の化石を求めて |
山本 哲生 |
| 150(1993年9月) |
VSOP三昧の記 |
平林 久 |
| 151(1993年10月) |
深宇宙ミッションにおける追跡管制 |
西村 敏充 |
| 152(1993年11月) |
究極のすだれコリメータ |
小川原 嘉明 |
| 153(1993年12月) |
太陽発電衛星 ー宇宙から地上へクリーンで安価なエネルギーを供給するための最適な方法 |
ヴラジミール・バンケ |
1992年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 131(1992年2月) |
さきがけ最接近ー磁気圏の観測 |
大家 寛 |
| 132(1992年3月) |
宇宙空間プラズマの直接計測 |
町田 忍 |
| 133(1992年4月) |
グライディングパラシュートを利用した回収システム |
中島 俊 |
| 134(1992年5月) |
CO2レーザと高エネルギ物質 |
斎藤 猛男 |
| 135(1992年6月) |
深宇宙軌道決定システム |
加藤 隆二 |
| 136(1992年7月) |
原始地球及び地球圏外環境下での有機物の生成 |
小林 憲正 |
| 137(1992年8月) |
気球は宇宙観測への第一歩 ー宇宙ガンマ線の観測ー |
山上 隆正 |
| 138(1992年9月) |
宇宙活動のための最重要課題 |
パトリック Q.コリンズ |
| 139(1992年10月) |
宇宙空間で測る ー衛星からの電波干渉との戦いー |
山本 達人 |
| 140(1992年11月) |
放射線に感じるプラスチック |
藤井 正美 |
| 141(1992年12月) |
高速度ダストを捕まえる話 |
藤原 顕 |
1991年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 119(1991年2月) |
「ミニ対流圏」仮説と大気圏上下結合 |
山中 大学 |
| 120(1991年3月) |
大気球南極大陸を周回 ーポーラー・パトロール・バルーンー |
平澤 威男 |
| 121(1991年4月) |
宇宙ロボットの研究について |
土屋 和雄 |
| 122(1991年5月) |
宇宙環境と飛翔体環境 |
佐々木 進 |
| 123(1991年6月) |
宇宙機器用耐熱複合材料 |
八田 博志 |
| 124(1991年7月) |
Beamwaveguide Research at JPL |
William A. Imbriale |
| 125(1991年8月) |
人工衛星によるサティライト線の観測 |
加藤 隆子 |
| 126(1991年9月) |
新設大学における宇宙・理工学研究ことはじめ |
松方 純 |
| 127(1991年10月) |
自律分散システム |
松方 純 |
| 129(1991年12月) |
宇宙流体力学と化学物理 |
藤原 俊隆 |
1990年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 106(1990年1月) |
ミリ波からサブミリ波へ |
稲谷 順司 |
| 108(1990年3月) |
金属系複合材料 |
大蔵 明光 |
| 109(1990年4月) |
情報処理システムの開発技法 |
山田 隆弘 |
| 110(1990年5月) |
宇宙ロボット |
中谷 一郎 |
| 111(1990年6月) |
高速気流総合実験設備について |
辛島 桂一 |
| 112(1990年7月) |
多層膜反射鏡 |
山下 広順 |
| 113(1990年8月) |
大気中の二酸化炭素 |
中澤 高清 |
| 114(1990年9月) |
展開アンテナ |
八坂 哲雄 |
| 115(1990年10月) |
惑星火山学と固体天体 |
藤井 直之 |
| 116(1990年11月) |
「超」燃焼の研究 |
新岡 嵩 |
| 117(1990年12月) |
ASTRO-D搭載のX線用CCDカメラ |
常深 博 |
1989年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 095(1989年2月) |
衝撃波 |
高山 和喜 |
| 096(1989年3月) |
日本初の軌道赤外線望遠鏡 |
村上 浩 |
| 097(1989年4月) |
多価イオン科学 |
市川 行和 |
| 098(1989年5月) |
半導体中の不純物と欠陥の評価 |
田島 道夫 |
| 099(1989年6月) |
増え続ける大気中微量気体と地球環境 |
巻出 義紘 |
| 101(1989年8月) |
X線天文学、超高密度星 |
蓬茨 霊運 |
| 102(1989年9月) |
マイクロ波無線送電 |
賀谷 信幸 |
| 103(1989年10月) |
実用化時代を迎えた電気推進 |
都木 恭一郎 |
| 104(1989年11月) |
ボイジャー・海王星日米共同観測をおえて |
河島 信樹 |
| 105(1989年12月) |
深宇宙探査 |
川口 淳一郎 |
1988年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 083(1988年2月) |
構造屋の知恵の輪ゲーム |
小野田 淳次郎 |
| 084(1988年3月) |
中性子星の瞬き |
長瀬 文昭 |
| 085(1988年4月) |
核酸の起源を宇宙に探る |
長谷川 典巳 |
| 086(1988年5月) |
数値流体力学と航空機設計 |
藤井 孝蔵 |
| 087(1988年6月) |
EXOS-D衛星と磁場観測 |
福西 浩 |
| 088(1988年7月) |
スロットアンテナ |
伊藤 精彦 |
| 089(1988年8月) |
無衝突衝撃波と非熱的粒子 |
寺沢 敏夫 |
| 090(1988年9月) |
宇宙航空用複合材の将来 |
田谷 稔 |
| 091(1988年10月) |
宇宙ロボット特論 |
梅谷 陽二 |
| 092(1988年11月) |
火星CO2大気の光化学的安定性の再検討 |
島崎 達夫 |
| 093(1988年12月) |
「ぎんが」との日々 |
井上 一 |
1987年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 071(1987年2月) |
原始惑星系と塵の雲 |
中野 武宣 |
| 072(1987年3月) |
電場計測へ一歩前進 |
鶴田 浩一郎 |
| 074(1987年5月) |
電波望遠鏡はピンボケ? |
森本 雅樹 |
| 075(1987年6月) |
生命発生の謎を探り、新しい蛋白質をつくる |
三浦 謹一郎 |
| 076(1987年7月) |
結晶成長の理解 |
西永 頌 |
| 077(1987年8月) |
太陽風・磁気圏・オーロラ −風が吹けば桶屋がもうかる話− |
向井 利典 |
| 078(1987年9月) |
力持ちの姿勢制御手段CMG ー気球ゴンドラの方向制御を中心としてー |
矢島 信之 |
| 079(1987年10月) |
銀河の多様さを測る |
小平 桂一 |
| 080(1987年11月) |
究極のレーザー“自由電子レーザー”の話 |
斎藤 宏文 |
| 081(1987年12月) |
鉄と鋼とマルエージ鋼 |
栗林 一彦 |
1986年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 059(1986年2月) |
軌道工学 |
松尾 弘毅 |
| 060(1986年3月) |
ミリ波・赤外線国際共同観測 |
海部 宣男 |
| 061(1986年4月) |
レーダリモートセンシング |
広沢 春任 |
| 063(1986年6月) |
オーロラの謎を追う |
江尻 全機 |
| 064(1986年7月) |
宇宙飛行機の研究 |
長友 信人 |
| 065(1986年8月) |
宇宙空間観測30年 −草創の頃− |
野村 民也 |
| 066(1986年9月) |
さきがけ磁場観測とハレー彗星 |
斎藤 尚生 |
| 067(1986年10月) |
重力と生命のかかわり |
山下 雅道 |
| 069(1986年12月) |
塵探査の近況 |
向井 正 |
1985年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 047(1985年2月) |
臼田宇宙空間観測所 |
林 友直 |
| 049(1985年4月) |
宇宙空間で電場を測る |
鶴田 浩一郎 |
| 050(1985年5月) |
宇宙構造物の構造概念 |
名取 通弘 |
| 051(1985年6月) |
ASTRO-C衛星 |
槙野 文命 |
| 052(1985年7月) |
空気力を利用した軌道制御 |
安部 隆士 |
| 053(1985年8月) |
衝突現象と惑星形成論 |
水谷 仁 |
| 054(1985年9月) |
難しいロケットの燃焼安定性予測 |
判沢 正久 |
| 056(1985年11月) |
静止衛星とミッション解析 |
竹内 端夫 |
| 057(1985年12月) |
来し方行く末 |
高野 忠 |
1984年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 036(1984年3月) |
宇宙科学と生命 |
清水 幹夫 |
| 037(1984年4月) |
宇宙と航空の接点 |
前田 弘 |
| 038(1984年5月) |
宇宙を再現する |
河島 信樹 |
| 039(1984年6月) |
木星型惑星探査体の熱防御 |
久保田 弘敏 |
| 040(1984年7月) |
ロケットによるサブミリ波帯での宇宙の観測 |
松本 敏雄 |
| 041(1984年8月) |
宇宙にインテリジェンスを、もっとインテリジェンスを |
田辺 徹 |
| 042(1984年9月) |
宇宙プラズマ現象の室内実験 |
中村 良治 |
| 043(1984年10月) |
惑星間塵の研究 |
山越 和雄 |
| 044(1984年11月) |
我が国初の惑星間空間探査機ーMS-T5ー |
平尾 邦雄 |
| 045(1984年12月) |
画像処理ひとすじ |
高木 幹雄 |
1983年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 023(1983年2月) |
縁の下の力持ち |
堀内 良 |
| 024(1983年3月) |
オーロラと「磁力線のつなぎかえ」 |
西田 篤弘 |
| 025(1983年4月) |
原子分子と宇宙科学 |
高柳 和夫 |
| 026(1983年5月) |
じゃじゃ馬ならしのロケット燃料研究 |
岩間 彬 |
| 028(1983年7月) |
X線星アラカルト |
田中 靖郎 |
| 029(1983年8月) |
“じきけん”(EXOS-B)衛星による日米共同実験 |
木村 磐根 |
| 030(1983年9月) |
インドネシア日食の気球観測 |
田鍋 浩義 |
| 031(1983年10月) |
ヒートパイプエンジン |
小林 康徳 |
| 032(1983年11月) |
気流とそのシミュレーション |
小口 伯郎 |
1982年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 011(1982年2月) |
SEPAC:オーロラをつくる物語 |
大林 辰蔵 |
| 012(1982年3月) |
満1歳を迎えた「ひのとり」−ひのとりシンポジウムをめぐって− |
田中 捷雄 |
| 013(1982年4月) |
大気力学、MUレーダー、リモートセンシングetc. |
加藤 進 |
| 014(1982年5月) |
チタン球形チャンバの開発 |
森 大吉郎 |
| 015(1982年6月) |
私の「詩と真実」DICHTUNG UND WAHRHEIT |
三浦 公亮 |
| 016(1982年7月) |
銀河系の星と塵 |
奥田 治之 |
| 017(1982年8月) |
温故知新 |
早川 幸男 |
| 018(1982年9月) |
新整備塔 |
橋元 保雄 |
| 019(1982年10月) |
衛星の姿勢制御 |
二宮 敬虔 |
| 020(1982年11月) |
MINIX計画 −宇宙太陽発電に向けて− |
松本 紘 |
| 021(1982年12月) |
成層圏エアロゾルの変動 |
広野 求和 |
1981年
| 発行NO(発行年月) |
タイトル |
著者 |
| 002(1981年5月) |
大気球について |
西村 純 |
| 003(1981年6月) |
惑星からの爆発性電波 |
大家 寛 |
| 004(1981年7月) |
MPDアークジェット研究 |
栗木 恭一 |
| 005(1981年8月) |
中層大気の観測 |
伊藤 富造 |
| 006(1981年9月) |
ランチャ・ドーム |
小野田淳二郎
平田 安弘 |
| 007(1981年10月) |
液水ロケットエンジンの開発 |
倉谷 健治 |
| 008(1981年11月) |
回収技術の開発経過 |
雛田 元紀 |
| 009(1981年12月) |
カルマン・フィルターとの20年 |
西村 敏充 |
![]()