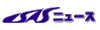| - Home page |
| - No.259 目次 |
| + 研究紹介 |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - 18mφアンテナの撤去に寄せて |
| - でっかい宇宙のマイクロプロセス |
| - 東奔西走 |
| - パソコン活用術 |
| - いも焼酎 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
一方,極低温の研究分野で冷媒に使われる,またそのものの物理現象の興味からヘリウム・水素(これもノンウォーターアイスですが)の研究は進んでいます。
ここで取り上げている外惑星 特に冥王星(〜30AU)以遠の惑星・衛星の表面に見出したノンウォーターアイスは,結晶学的な構造がわかっている程度のもので,物質科学の基礎から研究する必要のあるものです。メタンと窒素の沸点(ガスが液体になる温度)は1気圧下でそれぞれ109K(絶対温度),77.4K,融点(液体が固体になる温度)は90.7Kおよび63.3Kです。メタン氷は液体窒素を冷媒として使うことで作成することができますが,窒素とメタンは反応して融点を下げるため窒素ガスを遮断しないとメタンの氷は作成できません。またトリトンの表面温度まで物性測定するために液体ヘリウムを冷媒として用いて窒素氷も作成して実験を行いました。
ロシアの研究者によってメタン氷,窒素氷の音波速度の測定結果が報告されていますが,どのような状態の氷を使って測定したか記述がなく,添付されている装置の図を見てもよくわからないので,私たち(私と名古屋大学大学院生山下靖幸)はデュワー(冷媒を入れるガラス製魔法瓶)の外から観察しながら氷を作成し,音波速度を測定することにしました。ガラスデュワーの中へ光が入って温度が上がらないように極低温実験の場合ガラスに銀メッキを施しますが,外から観察できることを優先させ,メッキを施さない部分(スリット)を設けました。
デユーワー中のメタン氷
 液体ヘリウムの水位を上げることによって試料部分の温度を徐々に下げていくと,ガスがまず液体になり,さらに固体へと変化します。ゆっくり(1時間程度以上かけ)下から固化させれば,透明な氷が得られますが,急激に温度を下げるとクラックのたくさん入った質の悪い不透明の氷しかできません。添付写真では金属のピストン(ネジや穴が見えます)と下の金属プレートとの間にメタンの氷ができています。
液体ヘリウムの水位を上げることによって試料部分の温度を徐々に下げていくと,ガスがまず液体になり,さらに固体へと変化します。ゆっくり(1時間程度以上かけ)下から固化させれば,透明な氷が得られますが,急激に温度を下げるとクラックのたくさん入った質の悪い不透明の氷しかできません。添付写真では金属のピストン(ネジや穴が見えます)と下の金属プレートとの間にメタンの氷ができています。
ピストンと底面のプレートの中に音波を発生する超音波振動子が入っており,その場で音波速度を測定することができます。測定結果は従来のロシアの研究者によって報告されているものに比べ,1割程度高い音波速度を示しました。これは従来のものが空隙率の高いもの,霜を固めたようなものを測っていたのであろうと解釈できます。わたくしたちの作成したメタン氷,窒素氷は透明ですが,単結晶ではありません。1〜2mmの単結晶の集合体です。温度を上昇させ融解していくと結晶粒界から解けていくので結晶サイズがわかる。トリトン表面を構成しているメタン氷,窒素氷が固いのか柔らかいのか(流動特性)を調べました。ピストンを通して外から荷重をかけると(50kg/cm2
,女性の靴のヒールにかかる荷重程度)ピストンとガラスチューブの隙間に流れ出て行ってしまい,少し固い液体のような振る舞いをしました。ピストンの進行速度を変えて歪み速度を変えたり,ガラスを引き抜いて円筒形氷試料の側面を自由表面(応力がかからない状態)にして変形実験を,また荷重緩和の実験も行いました。粘性率は,メタン氷,窒素氷ともに1010Pa sec 程度で,水(みず)氷の粘性率に比べ5桁程度小さい。この値は暑い夏の日のアスファルトのものに相当します。