所長より
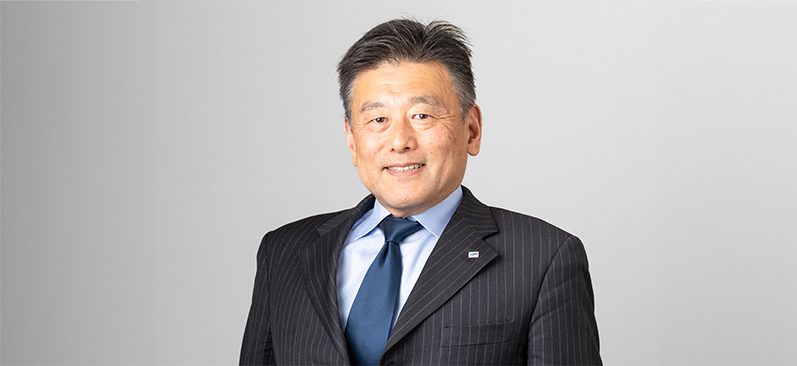
2020年12月、はやぶさ2は小惑星リュウグウのサンプルを無事地球に届けることに成功した。このこととそれ以後のいくつかの成功から、世界の宇宙科学界におけるJAXA宇宙科学研究所の立ち位置、世界において期待される宇宙研が果たすべき役割が明快になったと感じる。一方で、宇宙科学を取り巻く環境は速いペースで変化しており、それがもたらす制約の範囲内であってもしたたかに期待に応えていくことが求められる。
宇宙研の最大の強みは、その中型計画で世界をあっと言わせることをやってみせることにある。この強みを失うことがあってはならない。また、この強みとは、新しく面白い宇宙科学の領域を切り拓くような計画を実施する際に最大限に発揮されるのであり、ある分野のあるテーマに関して突き詰める計画を実施することは、必ずしも宇宙研の強みを生かすわけではないと考える。このような、ある意味で常に新しいアプローチで中型計画に注力していくことと並行して、小型計画に対しても同じレヴェルでの成果創出を求めることは、もはや、現実的ではないという事実に正面から向き合う必要がある。小型計画では衛星メーカーが協力しやすい形も意識しつつ、計画の特徴を明快にし、その特徴を出すうえで必須となる新しい要素は絞り込み、全体サイズを欲張ることなく、それでよいものについては既存品を活用し、絞り込まれた新規要素の開発は宇宙科学コミュニティ側が主導する形こそがあるべき姿ではないか。
これらの計画を実施していく中で日本のコミュニティが世界での存在感を高め、海外が主導する計画に参加する機会を獲得することの重要性は言うまでもない。今後は、日本の枠組みでは到達できない太陽系の領域へと向かう探査システムに小型ロボットを提供する、といった形態の海外計画参加を実現したい。
世界をあっと言わせる中型計画を実行するには、そのための筋力トレーニングが必須である。これを支える活動を宇宙科学プログラムに追加したいと考える。具体的には、世界最先端の要素を含み内製比率の高い小型プロジェクトを、速いサイクルで回していくことを狙いたい。これは当然、人材育成効果を伴うものであるが、そのことは宇宙産業の在り方が大きく変わる中でJAXAに求められるのは「技術を持っていること」だと考えれば、JAXA全体にとっても効果的なプログラム要素となるはずである。また、この文脈で、宇宙研が保有する実験設備・実験場を整えていくことも必須であることに考えが及ぶ。
さらには、小惑星探査での世界のリーダーとなった宇宙研は、JAXAにおけるプラネタリー・ディフェンス(日本語では地球防衛と呼びたい)活動を先導することへの期待にも応えていきたい。2029年4月13日金曜日。このチャンスを見逃すべきではない。
2025年4月
JAXA 宇宙科学研究所長
藤本 正樹
