宇宙からの赤外線観測を高感度で行おうとするときに、大切なことがあります。それは、望遠鏡を含む観測機器を冷却する必要があるということです。どのような望遠鏡といえども温度を持っている限りは、その温度に応じた赤外線を放射します。20℃の望遠鏡の発する赤外線放射(熱放射)は、天体からの赤外線放射よりも、典型的には100万倍以上も強くなります。このような強大な望遠鏡からの赤外線放射のもとでは、暗い天体など見ることができません。高感度達成のためには、望遠鏡からの熱放射を下げる必要があります。そのための最も効果的な方法は、望遠鏡を冷却することです。「あかり」の場合では、望遠鏡をマイナス265℃以下(絶対温度で数K以下)という極低温にまで冷却する必要がありました。
このような極低温を実現するため、「あかり」では、人類が手にできる最も冷たい液体である液体ヘリウム(1気圧での沸点がマイナス269℃)を用いました。ただし、液体ヘリウムには大きな欠点があります。それは、非常に蒸発しやすい液体であるということです。例えば、1gの液体ヘリウムが蒸発するときに奪う熱は、1gの水が沸騰して蒸発するときのそれに比べて1/100しかありません。したがって、「あかり」冷却系にとっての最重要課題は、液体ヘリウムをいかに節約するかということになります。
図29に「あかり」冷却系の断面図を示します。下の方に、液体ヘリウムを収めるタンクが見えます。このタンクを液体ヘリウムで満杯にして、衛星を打ち上げます。地上において外からの熱を遮断して液体ヘリウムの余計な蒸発を防ぐため、魔法瓶のような大きな真空容器に収められています。望遠鏡の開口部にも蓋(開口蓋)がかぶせてあります。衛星が宇宙に行って衛星外部が真空になった後に、この蓋を開けて観測を始めます。
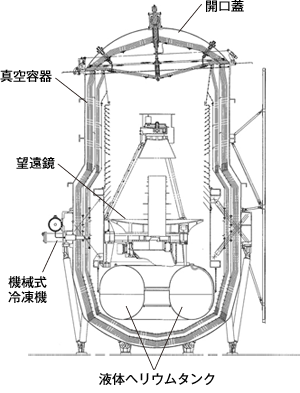
図29 「あかり」冷却系の断面図
液体ヘリウムと機械式冷凍機を併用したシステムである。
さらに「あかり」では、赤外線天文衛星としては世界で初めて、機械式冷凍機(2段式スターリング冷凍機)で真空容器の内部を冷却しました。その結果、観測中の液体ヘリウムへ伝わる熱を大幅に低減することができました。1995年にESAが打ち上げた赤外線宇宙天文台ISOと比べると、10分の1以下と極めて小さな値です。日本製品は、車だけでなく宇宙望遠鏡でも、「燃費が非常に良い!」ことが証明されました。
「あかり」冷却系により、観測機器は軌道上で所定通りの温度に冷却されました。それでも、二つの予想外の事態が起きました
一つは、姿勢センサのトラブルにより、打上げから望遠鏡の開口蓋を開けるまでの期間が予定の3倍にも延びたことです。蓋が付いた状態では、液体ヘリウムの蒸発量は4倍にも増加します。日々どんどん減少していくヘリウムのことを思うと、気が気ではありませんでした。
もう一つは、蒸発したヘリウムガスが衛星の外に排出されたのですが、それが効率の良い推進系として働いてしまったことです。排出されたガスの圧力が、衛星を加速したのです。そのために、通常は下降していくべき軌道が、「あかり」の場合は毎日、数十m上昇していきました。
このように予想外の事態も起きましたが、冷却系全体としては設計通りの性能を発揮しました。そして、ミッションから要請されていた最低1年の観測期間を超え、約1.5年にわたり液体ヘリウムは保持されていました。設計上、液体ヘリウムの軌道上保持期間は、打上げ後550日と予想されていました。液体ヘリウムが蒸発し切ったのは、打上げ後550.5日でした。予測との差は、わずか半日。軌道上でいろいろと予想外のことは発生しましたが、設計予想値と実績が0.1%(!)という高精度で一致したことになります。
(なかがわ・たかお)
