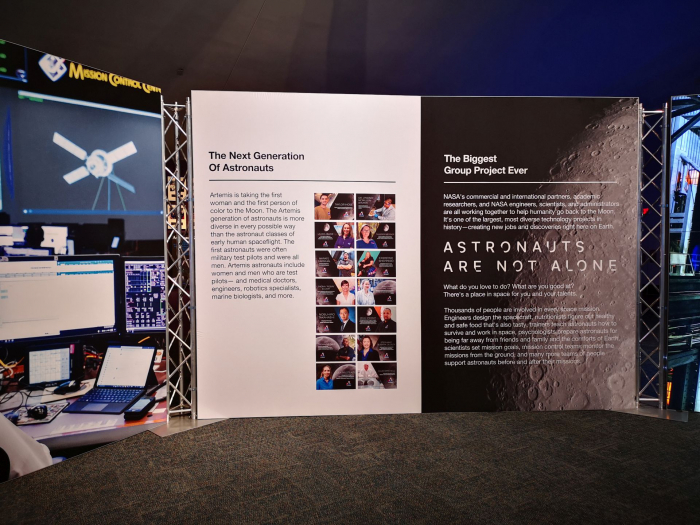ゲートウェイのピンバッチを着けて
2年ほど前、NASAのウェブサイトの 「I am Artemis」 と題したインタビューコーナーに登場されています。
「I am Artemis」: NASAが主導している月面探査プログラム「アルテミス計画」に携わっている人たちを紹介するコーナーです。私は当時NASAジョンソン宇宙センターがあるアメリカ合衆国テキサス州のヒューストンに駐在し、有人月周回軌道拠点「ゲートウェイ」に関する技術調整のJAXA現地代表を務めていたことから取り上げていただきました。ゲートウェイは、アルテミス計画のプログラムの一つで月探査や火星探査の中継基地としての役割があり、ISS計画の参加国を中心に国際協力で開発が進められています。インタビュー記事では、「髙橋」を英訳すると「High Bridge」であり、地球と月の架け橋となるゲートウェイにおいて良好な国際協力関係を育むのに適任だと紹介していただきました。
NASAジョンソン宇宙センター内の展示室のパネル。「インタビュー『I am Artemis』の写真が使われていて、私の写真もあります。パネルのタイトルが『The Next Generation Of Astronauts(次世代の宇宙飛行士たち)』で、しかもJAXA宇宙飛行士候補者の選抜が行われていたときだったので、私が月に行く宇宙飛行士候補だと誤解された、なんてこともありました」(髙橋)
3年間のヒューストン駐在を終え、2023年7月から科学推進部に所属されています。
科学推進部では国際関係の仕事を担当しています。2023年12月、NASAのジム・フリー副長官が来日し関係機関を訪問いただいた際、私が宇宙科学研究所をご案内しました。日本滞在中、ジム・フリー副長官はSNSのXに複数回ポストしています。筑波宇宙センターと文部科学省についてそれぞれ1回、そして宇宙科学研究所については3回ポストされました。その中に、翌年1月に月着陸に挑む小型月着陸実証機SLIMの模型の前でのジム・フリー副長官と私のツーショット写真がありました。
ジム・フリー副長官とはゲートウェイで接点があり、私はゲートウェイのピンバッチを着けて迎えました。ヒューストンを離れる際、NASAの人たちから「あなたはこれからもゲートウェイ・ファミリーの一員だ」と言っていただけたからです。「ファミリー」は、日本では「家族」を指しますが、欧米では仕事などを一緒にした「仲間」という意味でも使います。私の好きな言葉の一つです。
ジム・フリー副長官は、ピンバッチに気付いて微笑み、続けて「いいネクタイをしているね」とも言ってくれました。私は、ヒューストン・アストロズのネクタイをしていたからです。私は人と接するときは、相手が好きなこと、興味を持っていることを準備するようにしています。宇宙ミッションのピンバッジやミッションパッチなど身に着けるものは仲間意識を高めるのに効果的であることを知り、またワールドシリーズやスーパーボウルの際には職場でもそれぞれが応援するチームのユニフォームを着るというアメリカ文化が身に付いたからかもしれません。
私たちのツーショット写真をゲートウェイの仲間たちが見て、リポストしたり、コメントをしてくれたりもしました。うれしかったですね。海外機関ではSNSでの情報発信に力を入れており、JAXAとNASAが一緒に取り組んでいる様子を見せること、つながりを広げていくことは、国際協力をうまく進めるために重要だと考えています。
強烈な記憶、バイコヌールでの3カ月
ずっと国際関係の仕事をされてきたのですか?
実は違います。私は、大学で情報工学を学んで修士号を取り、1998年にNASDAに入社しました。最初に配属されたプロジェクトは、技術試験衛星VII型でした。配属直後の1998年七夕に、「おりひめ」「ひこぼし」と名付けられた衛星は、ランデブ・ドッキング実験に成功しました。またロボットアームを使った実験にも成功し、これらの技術が、宇宙ステーション補給機「こうのとり」や国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟のロボットアームにつながることになります。当時は筑波宇宙センターの閉鎖された環境で休みなく人工衛星の追跡管制を行う日々でした。私が有人宇宙活動の国際協力を担当するのは、それから15年後のことです。
ほかにどのようなプロジェクトに携わってきたのですか?
1999年から光衛星間通信衛星OICETS(きらり)のプロジェクトに参加しました。OICETSは、ESAのARTEMIS衛星との間でレーザー光による通信実験を行うための技術試験衛星です。思い返せば、このときからアルテミスという名前に縁があったのですね。
OICETSは、打上げまでにとても苦労しました。新たに開発するJ-Iロケットで2002年に打ち上げる予定だったのですが、2001年にJ-Iロケットの開発計画が凍結されてしまいました。さらに2003年にH-IIAロケット6号機の打上げ失敗があり、光通信の相手となるARTEMISの寿命も限られていることから、外国のロケットで打ち上げることになりました。
マイクロスペースシステム研究室という部署で50kg級の小型衛星μ-LabSatの開発と運用をしながらロケット探しに奔走し、ようやくドニエプルロケットに決めました。射場はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地です。ユーリ・ガガーリンさんが人類で初めて宇宙へ飛び立った場所でもあります。私たちは打上げ準備のためにバイコヌールで3カ月間射場作業を行ったのですが、そこは自由に出入りできない閉鎖都市で、射場の施設や設備についても制限されることが多く、特殊な環境にとても苦労しました。
苦境を乗り切った秘策。それも人と人のつながり
具体的には、どのような苦労があったのでしょうか?
ドニエプルロケットは、地下のサイロから打ち上げられます。ところが、準備作業のために地下サイロに入る予約を数日前にしておいても、「今日は駄目だ」と言われてしまうのです。別の日に予約し直しても、また「今日は駄目だ」と。ようやく地下サイロに入ることができても、「そこは行くな」「こっちは見るな」と言われてしまいました。ドニエプルロケットは旧ソ連の大陸間弾道ミサイル(ICBM)を人工衛星打上げ用に転用したものであり、極秘事項が多いのです。
よく観察していると、地下サイロのセキュリティを現場で仕切っている人が分かりました。そこで、その人に積極的に話し掛け、街中で一緒に食事をしたりして仲良くなったのです。すると、地下サイロでの作業もスムーズにできるようになりました。われわれのミッションの目的や私という人物を理解してもらえたからです。人と人がお互いをよく知り、良好な関係を結ぶことは、どの国でも仕事をうまく進めるために大切なのです。たとえ、お互いの言葉が分からなくても、気持ちは伝わるものです。
宇宙に行く前の宇宙飛行士が宿泊するコスモノートホテルに滞在できて、現地で雇用したカザフ人夫婦に日本食のつくり方を覚えてもらったので、生活はそれほど困りませんでした。ですが、毎日何かしら問題が起きるものです。ホテルから射場まで片道1時間ほどですが、用意されていたバスのエアコンが故障しました。バイコヌールは砂漠地帯で、夏は気温が40℃を超えます。交渉の末、新しいバスを調達してもらうことができました。その真新しいバスの窓ガラスにOICETSのミッションシールを貼ってきました。
OICETSとARTEMISの光通信実験の結果は?
つくばエクスプレスが開業した2005年8月24日にOICETSを打ち上げ、12月9日にOICETSとARTEMISの間で世界初の双方向光衛星間通信に成功しました。私もARTEMISの地上局があるベルギーのルデュという小さな町に行きましたが、このときも大変でした。妻の出産予定日が11月末だったのですが、12月になっても生まれない。明日生まれなかったらベルギーに発たなければいけない、というギリギリのタイミングで長男が誕生。その半日後に飛行機に乗り込みました。
そして光衛星間通信に成功してほっとしていたら、突然、国際電話で連絡が来たのです。年明けから経営企画部に行ってください、と。それまでエンジニアとして技術系の仕事をしてきましたから、激務で深夜帰りの多いと噂の東京事務所勤務となることに驚きました。まるでミッションインポッシブルのような出来事でした。
話が戻りますが、なぜ就職先にNASDAを選んだのですか?
大学時代、プログラミングのアルバイトをしていて、ITを使ったシステム構築が得意で世の中の役に立つものも開発しました。一つは、東洋医療と西洋医療を融合させたもので、機器で測定したツボのデータをメールで病院に送り、データベースから健康状態を推測した結果をもとに医師が診断書を送り返すというシステムです。もう一つは、進化する占いです。インターネットを使って集めた占いの結果を統計処理し、さらにスクリーニングやオペレーションズリサーチの手法を用いることによって精度を高めることを行いました。
その流れでシステム構築の世界に進む道もありましたが、宇宙開発の世界に入ったのは、毛利衛宇宙飛行士の影響が大きいです。私が大学に入った1992年、毛利さんが日本人として初めてスペースシャトルで宇宙飛行をしました。それまで宇宙は遠い存在だと思っていたので、日本人が宇宙に行ける時代になったことに感動しました。そして、21世紀には月に行ったり宇宙旅行をしたり、宇宙が人類の活動の場になるに違いないと思い、それを実現する仕事がしたいと考えたのです。大学OBの上垣内茂樹さんを紹介されてお話を伺い、その思いが強くなりNASDAに就職しました。
あなたは宇宙へ行きたいですか?
「有人宇宙ミッション検討のミエル化」という活動をされていました。どういう活動ですか?
人が宇宙船に乗って宇宙に行くことについての検討を活性化させようというJAXA職員有志による活動で、2011年4月12日にスタートしました。有志といっても、最初は私を含めて2人でした。まずJAXA職員に「あなたは宇宙へ行きたいですか?」という問いから始まるアンケートを実施しました。さらに、日本の有人宇宙ミッションはどうあるべきか、さまざまな立場の人たちと意見交換を行いました。仲間は次第に増えてJAXA職員内外を含め200名を超え、活動結果を『日本の宇宙探検』として2012年3月に出版しました。たくさんの人に読んで欲しいので、利益なしのワンコイン500円としてコンビニにも置いてもらいました。宇宙への関心を高めてもらう有力なツールになったと思っています。現在はPDFを無料で公開しています。
「ミエル化」の活動を通して、どのようなことを感じましたか?
「あなたは宇宙へ行きたいですか?」という問いに対して「行きたい」と答えたJAXA職員は、約7割でした。私が注目したのはその割合ではなく、「行きたくない」と答えた人の理由です。安全に対する不安やコストが高いというのは予想の範囲でしたが、「自分が宇宙に行くより、人が宇宙に行く乗り物をつくりたい」という回答があり、JAXAの職員らしいなと思いました。
人類初の人工衛星が打ち上げられたのが1957年、ユーリ・ガガーリンさんが人類で初めて宇宙に行ったのが1961年4月12日です。「ミエル化」の活動開始日は、ちょうど50年後にあたります。46億年の地球史で人類が宇宙に行く手段を持ってから、まだ100年未満です。しかし今は、できなかったことが次々と可能になり、知らなかったことを知り、行きたいところに行けるようになる、まさに「宇宙大航海時代」です。
だからこそ日本から有人宇宙船を打ち上げたいと思い、「ミエル化」の活動を始めました。勉強会や講演会に参加してくれた当時学生だった人たちが今ではJAXAや宇宙ベンチャーで働いていたり、航海を共にする仲間が増えていくのを実感しています。
この記事のタイトルは、髙橋さんに付けていただきました。
私が小さい頃には、地球のような惑星がほかにも存在するのかどうかが分かりませんでした。今では6,000個を超える太陽系以外の惑星が発見され、地球型惑星もたくさんあることが分かってきました。私は、そこに生命が存在すると信じています。
外国の人に対しては「私は日本人です」と自己紹介するように、ほかの天体の人に対しては「私は地球人です」と言うでしょう。彼らには「宇宙人」と呼ばれるかもしれません。人類はまだ地球外の生命を発見できていませんが、「私は地球人です」「私は宇宙人です」と言える日が来るために、今、科学衛星や探査機と共に宇宙船地球号で航海中なのです。そういったことを考えて、このタイトルをインタビュー前に提案しました。
髙橋さんは宇宙に行きたいですか?
気楽に旅ができるようになれば行きたいです。時期の問題だけで、いずれ人類は飛行機に乗るように宇宙に行く日がくるでしょう。その時、私は自分の目で宇宙から地球を眺めてみたいです。ISSから見える地球は、一部分です。私は、アポロの宇宙飛行士が見た丸い地球、これからアルテミス計画で宇宙飛行士たちが見る地球が見てみたいです。
システムズエンジニアリングで移転先検討。宇宙飛行士搭乗支援や安全審査も
その後は、どのような仕事をされてきたのですか?
システムズエンジニアリングをご存じでしょうか。宇宙機のような複雑なシステムのミッションを成功させるためのもので、JAXAではシステムズエンジニアリングの強化に力を入れています。システムズエンジニアリングは万能ではありませんが、「東京事務所の移転先をシステムズエンジニアリングで検討せよ」という指示が私のところに来ました。職員数、出張の行き先や回数、ステークホルダを考慮したさまざまな業務の内容などを数値化し、どこが最適かを検討しました。その結果、新御茶ノ水が候補になり、2013年に御茶ノ水ソラシティに移転したのです。
有人宇宙活動に関わるようになったのは、その後ですか?
「ミエル化」の活動で現場の苦労を知らずに夢だけを語っていたことが影響したのかもしれませんが、現場を経験してみなさいということで2013年から有人宇宙ミッション本部事業推進部(現在の有人宇宙ミッション部門)で仕事をすることになりました。
そこでは事業計画や評価、危機管理を担当していました。また搭乗支援隊として、『日本の宇宙探検』の制作に協力してくれた3人の新人宇宙飛行士たちの初フライトを支える仕事に従事できたことが喜びでした。大西卓哉宇宙飛行士がISSに搭乗する際は、再びバイコヌールに行く機会が与えられました。11年ぶりです。OICETSの打上げのときに毎日利用したバスが、今でも宇宙飛行士の移動に使われていました。窓ガラスには、ミッションマークがたくさん貼られていました。その中に私たちが最初に貼ったOICETSのミッションマークを見つけたときは、うれしかったですね。新たに大西宇宙飛行士のミッションマークを貼ってきました。
 |
 |
バイコヌールで移動に使われるバスの窓ガラスには、たくさんのミッションマークが貼られている。最初に貼られたのが、左の写真に写っているOICETSである(2005年)。右は、髙橋さんが2016年に大西宇宙飛行士のミッションマークを貼っている様子。
その後は、安全・信頼性推進部でISSの安全を担当しました。最初の仕事は「こうのとり6号機」の安全確認でした。種子島宇宙センターに行き、ロケット先端のフェアリングにある小さな扉を開けて頭を突っ込み、ロケットに搭載された「こうのとり6号機」が安全審査の結果をもとに対処されていることを検証確認しました。「こうのとり6号機」の雄姿を目に焼き付け、扉が閉められました。翌日に打上げを目視し、さらにISSに到着した「こうのとり6号機」の様子をNASA TVで見たときの感激は今も忘れられません。安全に宇宙飛行士たちのもとに実験機器や食糧などが運ばれたからです。
ロケットの打ち上げを待つ間、NASA関係者に種子島宇宙センターを案内するという役割もありました。その時に会ったNASAのISS副マネージャは後にゲートウェイのプロジェクトマネージャとなり、ヒューストンで再会しました。
ISSの安全担当になり、NASAへ行くことも増えたのではないですか?
2017年に初めてNASAに出張しました。その後は安全審査のために何度もジョンソン宇宙センターに行くことになりました。安全審査の際に親しくなったNASAのマネージャから「ヒューストンで仕事ができる場所が必要だろう」と言って、彼らの居室の一角に私専用の机を用意していただき「Nobu」というプレートも付けていただきました。NASAの皆さんとの関係が深まったこともあってか、2020年からヒューストンに駐在してゲートウェイを担当することになったようです。新型コロナウイルスによる苦労については、話が長くなりますのでまたの機会に(笑)。
NASAの一室に専用の机を用意していただいた。ネームプレートは「Nobu」。「皆さんからは『Nobu』と呼んでもらっています」(髙橋さん)
人のつながりはJAXAの資産
お話しを聞いていると、人と親しくなるのが上手だと感じます。コツはあるのでしょうか?
自分では、むしろ人付き合いは苦手だと思っています。私は、ちょっと変わり者で、考えていることが先を行き過ぎてしまっているようなのです。しかも、考えていることをうまく説明できないので、周りに理解してもらえず、浮いてしまいがちです。だからこそ、より良い関係を結んで仕事を楽しくするために大切なことは何か、失敗を重ねながら学んできました。
私が人と接するときに大切にしているのは、距離感です。どこまで近付けるのか、どこから先に入ってはいけないのかを見極めます。ギリギリまで近付くことで、好印象や仲間意識を持ってもらえると思うのです。近付くときには、まず自分の好きなことを伝えがちですが、そうではなく、相手が好きなことを聞き、それに興味を持ち自分も好きになってみることが大切だと思っています。
また、相手が自分に期待することを読み取るようにしています。相手が本音を言っている場合もあれば、裏を読んでくれという場合もあるでしょう。言葉だけでは読み取れないところまでを読み取る、ということを心掛けています。それに加えて、自分の思っていることを正直に伝えることが大切です。耳障りのいいことを言ってその場限りの関係をつくるのは簡単ですが、それでは信用されません。
これまで出会った中で特に印象に残っている人は?
たくさんいますが、イーロン・マスクさんもその一人です。2008年から2011年までシステムズエンジニアリング推進室に所属していたとき、赤外線宇宙望遠鏡SPICAを担当させていただきました。SPICAの打上げロケットを検討しているとき、彼が創業したスペースX社のファルコンヘビーが能力と価格の面で候補になると考えました。当時のイーロン・マスクさんは、今ほど知名度は高くありませんでした。JAXA内に伝手もなく、米国出張の機会にスペースX社を単独訪問する約束を苦労して取り付けました。スペースX社での打合せを終えてタクシーで帰ろうとしたときに駐車場に入ってくる赤いテスラ・ロードスターを発見し、タクシーの運転手に駐車場に戻るようお願いしました。そこでイーロン・マスクさんに出会い、ロードスターやロケットについての話をすることができました。
あの頃はスペースX社がファルコン9を開発中の段階であり、その発展型であるファルコンヘビーはSPICAの打上げロケット候補から外れ、その後SPICAも計画が中止されました。当時SPICAが打上げ予定としていた2018年に、あの駐車場で見たテスラ・ロードスターが搭載されたファルコンヘビーが打ち上がった際には、いろいろな感情があふれ出ました。市販車のカーステレオからデヴィッド・ボウイの曲が流れる様子に、人類が火星へ宇宙旅行をする想像をかき立てられました。
私は、スペースシャトルの形状が好きです。飛行機のような翼を持ち、乗り物感が強いですよね。有人宇宙船は、安全であることを大前提として、デザインも重要だと思っています。イーロン・マスクさんがデザインを重視する点に共感します。
「私は車が趣味で、ヒューストンに赴任するまで赤のテスラ・ロードスターに乗っていました」(髙橋さん)
髙橋さんの周りには人と人とのつながりが、たくさんあるのですね。
かつて一緒に仕事をした人たちと再会し、また仕事を共にすることもあります。宇宙規模の奇跡や巡り合わせで出会った人たちとのつながりは、とても大切なもので、私個人のものではなくJAXAの資産だと考えています。それは人と人との橋渡しにより国際協力がスムーズになることを実感してきたからです。
日本の長所は「技術力」と「和の心」
宇宙開発は国際協力が不可欠になっています。なぜですか?
宇宙開発のような大きなプロジェクトの場合、一国でできることは限られています。なぜ国際協力をするのかというと、それぞれの国が持つ長所を生かして取り組むことで、より早く、より良くプロジェクトを成功に導けるからです。
日本の長所は?
ユニークで高い技術を有していることです。「はやぶさ2」による小惑星からのサンプルリターンも、SLIMの月面ピンポイント着陸も、海外の宇宙機関から称賛されています。日本はそうしたユニークで高い技術を持っているから、国際協力の話が進むのです。ISS計画に日本が参加するとき、日本は有人宇宙活動の実績がありませんでしたが、技術を持っていました。その後、日本の技術の高さを証明することで、NASAから信頼を得て、ゲートウェイでは対等に意見できる関係になりました。ISS計画で苦労された人たちの様子は書籍などで知ることができます。先輩方が築いてきた実績に感謝しつつ、私は次の世代に橋渡しをするよう心掛けています。
もう一つの長所が、和の心です。日本人は、争わないで物事をうまくまとめる力を持っています。2カ国間の協力がうまくいかないとき、日本がその間に入ることでうまく進み出すことがあります。尊敬する若田光一宇宙飛行士は長期滞在ミッションの際に「和の心」をミッションテーマとして掲げられており、日本人初のISSコマンダーとしての重責を果たされました。余談ですが、若田宇宙飛行士が2014年3月9日にISSコマンダーに就任された直後の3月15日に、ナショナルジオグラフィックで「ライブ・フロム・スペース:宇宙より生中継」という番組が世界170カ国で生放送されました。私は日本の番組で解説者を務めさせていただきました。
「プラネタリーディフェンス」にも注目
明日から海外出張だそうですね。今回の目的は?
X線分光撮像衛星XRISMのファーストライトや小型月着陸実証機SLIMの成功を携え、國中均所長に同行して火星衛星探査計画MMX、二重小惑星探査計画HERAなどの将来ミッションにおける国際協力を着実に進めることです。
HERAによる小惑星観測は、関心が高まっているプラネタリーディフェンス、つまり天体の地球衝突から人類を守る活動にもつながります。6600万年前、小惑星が地球に衝突して恐竜が絶滅しました。将来、同じことが起きる確率は非常に高いと考えられています。実際、2029年にはアポフィスという小惑星が、地球表面から3万2000kmまで接近します。これは地球と月の距離のおよそ10分の1です。地球に衝突する可能性のある小惑星を探査する絶好の機会であり、複数の国が協力して複数の方法で同時に観測した方が、多様なデータが得られて総合的な理解につながります。
今回の海外出張では、まだ計画化されていない将来ミッションについても議論してきます。ここから新たな航海が始まるかもしれません。楽しみにしていてください。
【 ISASニュース 2024年7月号(No.520) 掲載 】(一部加筆)