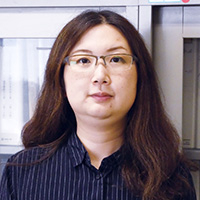組み立て・試験検証は準備が重要
SOLAR-C(高感度太陽紫外線分光観測衛星)プロジェクトチームに所属されています。どのようなことを担当されているのでしょうか?
SOLAR-Cは、日本が主導し、米国と欧州諸国が参加する国際プロジェクトです。2024年3月にプロジェクトチームが発足しました。私は、プロジェクトの準備段階だった2021年からSOLAR-Cに携わっており、現在は望遠鏡の組み立て・試験検証についてJAXA側の取りまとめを担当しています。
望遠鏡は複数の要素から構成されていて、担当の機関がそれぞれ開発します。それらの要素を集めて望遠鏡を組み立てるのですが、完成した望遠鏡はロケット打上げ時の振動に耐え、地上とは異なる宇宙空間の環境で正しく動作し、想定どおりの機能や性能を発揮するものでなければなりません。
そのため、要素ごとの試験検証に加えて、試験用のエンジニアリングモデル、そして実際に打ち上げるフライトモデルを組み立てて試験検証を行います。その取りまとめが私の役割です。
SOLAR-Cは現在、どのような状況ですか?
2025年度中に基本設計審査が行われる予定で、その後、詳細設計、製作へと進み、2028年度の打上げを目指しています。
組み立て・試験検証の取りまとめの仕事が忙しくなるのは、衛星の製作が始まってからでしょうか?
いいえ、すでに忙しくなってきています。フライトモデルの試験で初めて問題が見つかると、打上げスケジュールに影響が出る恐れがあります。フライトモデルを組み立てた後では試験が難しい項目もあります。そのため、打上げまでのロードマップを見据えて、どの段階で何の試験を行うべきかを綿密に計画しておく必要があります。その計画をプロジェクトメンバー全員で共有することも欠かせません。
組み立て・試験検証は、本番の作業だけでなく、そのための準備が非常に重要なのです。
特に難しさを感じている点はありますか?
SOLAR-Cには多くの海外宇宙機関が参加しており、組み立て・試験検証に関しても、各機関からさまざまな要望が寄せられます。それらの要望に対して、相手側とJAXAの双方が納得できる落としどころを見つけていかなければならず、そこが難しい点です。ただ、難しいからこそ、やりがいも感じています。
調整をうまく進めるコツはあるのでしょうか?
要望を表面的な言葉だけで受け取ってしまうと、意見が衝突してしまうことがあります。しかし、なぜその要望が出てきたのかという背景を丁寧にひもといていくことで、解決の糸口が見えてくることもあります。
もちろん、どうしても相手の要望を受け入れられない場合もあります。そうしたときに納得してもらうためにも、丁寧な説明が欠かせません。対話こそがプロジェクトを円滑に進めるための鍵だと思います。
新しいものを見つけたい。そのために観測装置をつくる。
宇宙科学分野に進もうと思ったきっかけを教えてください。
小学生のころ、すばる望遠鏡のファーストライトの画像をニュースで見て「いいな」と感じたのが、最初のきっかけです。それ以来、宇宙に興味を持ち続けてきました。
高校生のときに系外惑星が発見されたというニュースに触れたことも、大きなきっかけです。「天文学は、今も未知のものが見つかる学問領域なんだ」と、ますます魅力を感じるようになりました。
では、大学では迷わず天文学を選んだのでしょうか?
大学に入った当初は、まだ決めきれていませんでした。幅広くいろいろなことに興味があり、「やってみないと分からないから、あれもこれもやってみたい!」と思ってしまうのです。宇宙物理学や素粒子物理学に興味があり、進む学科を決める2年生の夏の直前まで迷っていました。
天文学を選んだ決め手は何だったのですか?
知らなかったことが分かっていくという感覚に強く惹かれていて、「新しいものを見つけたい」という思いが常にありました。それを実現できる場を探す中で、自分たちで装置をつくり、観測研究を行っている研究室が天文学科にあることを知ったのです。
未知のものを見つけるために、新しい観測装置を自分たちでつくる。新しい観測装置をつくって、新しいサイエンスに挑戦する。そんな研究スタイルが、自分に合っていると感じました。そして大学、大学院と、装置開発と観測研究の両方を続けてきました。
チリ・アタカマ砂漠へ。装置開発と観測研究を経験
どのような装置開発と観測研究を行ったのでしょうか?
私が大学院に進んだころ、チリのアタカマ砂漠に口径6.5mの世界最大級の赤外線望遠鏡を建設する東京大学アタカマ天文台(TAO)計画が始まり、私が所属していた研究室も参加していました。その場所で想定どおりの観測ができるかを検証するため、まず口径1mのminiTAO望遠鏡を建設することになり、この望遠鏡に搭載する観測装置の現地観測立ち上げに携わり、実際にアタカマ砂漠に行って観測も行いました。
一生の最後に超新星爆発を起こすような重い星が誕生する様子を、赤外線で観測しました。生まれたばかりの重い星は、濃いガスに覆われているため、可視光では見ることができず、電波がよく使われます。私は、赤外線で星をより細かい部分まで見たり、明るさの変化を調べるという、当時あまり行われていなかった観測に挑戦しました。
自分の関わった観測装置で、新しいサイエンスに挑む。まさに、やりたかったことが実現できました。もちろん装置開発でも観測でもトラブルがありましたが、それも含めて楽しく、よい経験でした。そしてこの経験は、現在取り組んでいるSOLAR-Cにもつながっていると感じています。
アタカマの星空は、とてもきれいですか?
望遠鏡が安定して動いているときは、少し外に出て空を見上げることもできます。きっとものすごくきれいな星空が見えるだろうと、私も期待していたのですが、実はあまり感動しませんでした。
望遠鏡は乾燥した砂漠にあるので空気が澄んでいて、実際にはとても美しい星空が広がっていたはずです。でも、標高5,640mという高地にあるため酸素が薄く、頭がぼんやりしていて、その美しさを十分に感じ取れなかったのかもしれません。高所に順応した後に、標高2,300mほどの町で見た星空は、ものすごくきれいでした。

大型国際プロジェクトを経験したい
JAXAに入る前は、国立天文台でプロジェクト研究員をされていました。どのようなことに取り組まれていたのでしょうか?
口径30mの超大型望遠鏡 TMT(Thirty Meter Telescope )プロジェクトで、観測装置の開発に取り組みました。最先端のサイエンスに挑戦しようとすると、プロジェクトは大規模に、そして国際的になります。「新しいものを見つけたい」という思いは変わらず持ち続けていたので、大型の国際プロジェクトに関わってみたかったのです。
大学のプロジェクトとTMTのような大型国際プロジェクトでは、進め方も大きく異なります。また、私は装置開発と観測研究の両方をやってきましたが、TMTでは装置開発が中心になります。そうした変化に付いていけるのか不安もありましたが、「やってみなければ分からない。もし向いていなければ、観測研究寄りのポジションなど次の道を考えればいい」と思い切って飛び込みました。
TMTプロジェクトに入って、いかがでしたか?
大変なことも多くありましたが、それ以上にやりがいを感じました。だからこそ、任期付きのポジションではプロジェクトの途中から入って途中で離れなければならないことを、残念に感じるようになっていきました。その後、任期付きのJAXA宇宙科学プロジェクト研究員として衛星搭載機器の開発に携わっているときに、SOLAR-Cの研究開発員を募集していることを知って応募したのです。
SOLAR-Cで始まる太陽の新しいサイエンス
SOLAR-Cプロジェクトにおいて、内山さんの強みは何だと思いますか?
装置開発と観測研究、両方のバックグラウンドがあるので、サイエンス側の人が話していることや考えていることをくみ取り、それをほかの関係者に分かりやすく伝えることができることでしょうか。
また、プロジェクトを進めていると、初めてのことや分からないことに、たくさん出会います。そのときには、周囲の人に積極的に話を聞いて学び、どんどん吸収していきたいと考えています。私は、大先輩に対しても気後れせずに話を聞きに行ってしまうタイプなので、それも一つの長所かもしれません。
高校生のころ、「天文学は今も未知のものが見つかる学問領域」だと思ったとありました。SOLAR-Cによって太陽についての新しいことが見つかりそうですか?
これまでにも多くの太陽観測衛星が打ち上げられ、さまざまな観測が行われてきました。しかし、高温のコロナや太陽風がどのようにしてつくられるのか、また爆発現象であるフレアがいつ、どのようにして発生するのか、さらにフレアが地球にどのように影響を及ぼすのかという宇宙天気の仕組みなど、解明されていないことがまだ多くあります。
SOLAR-Cは、紫外線で太陽を観測します。紫外線はオゾン層に吸収されてしまうため、地上では観測できません。これまでも衛星による紫外線観測は行われてきましたが、SOLAR-Cでは、これまでよりも大口径の望遠鏡を用いて、より高い解像度で太陽を細かく観測することが可能です。
SOLAR-Cによってコロナやフレアなど太陽に関する現象が解明されることを、私たちも期待してプロジェクトを進めています。
今後、どのようなことに取り組みたいとお考えですか?
新しいものを見つけたい。そのために新しい観測装置をつくる。これは、私の中では最も重要なことで、一番のモチベーションになっています。これからも宇宙科学プロジェクトに関わり、新しいサイエンスを可能にする新しい観測装置をつくっていきたいですね。
【 ISASニュース 2025年6月号(No.531) 掲載 】(一部加筆)