物の動く仕組みに興味
専門を教えていただけますか?
電源系と呼ばれる宇宙用の太陽電池やバッテリーの研究開発をしてきました。現在は、深宇宙探査技術実証機DESTINY⁺プロジェクトで、プロジェクトエンジニアとして工学側の責任者をしています。電源系だけでなくシステム全体を見渡す必要があり、視野が広がったように思います。
子どものころから宇宙や工学に興味を持っていたのですか?
小さいころから物が動く仕組みに興味がありました。まさに「三つ子の魂百まで」ですね。小学生のころ、家電を買い換えるときには、捨てる前に分解して中がどうなっているのかを観察し、組み立て直し、どういう仕組みで動いているのかを調べていました。ラジカセやビデオデッキ、ミシン、テレビも分解しました。どれも完全には元に戻せませんでしたが......。
また、学研まんがの『ひみつシリーズ』が好きで、何冊も買ってもらいました。中でも『宇宙生活・スペースシャトルのひみつ』を繰り返し読んでいました。その本は、今も実家にあります。スペースシャトルの最初の打上げに合わせて1981年に発行されたもので、情報が古くなったところもありますが、今読んでも面白いです。
同年代で宇宙や工学に興味を持つ人の多くが通る道かもしれませんが、私もガンダムがとても好きでした。強度があって軽いガンダリウム合金やレーダーを無効化するミノフスキー粒子など、架空の要素もありつつ、宇宙に関してしっかりと考証されていて、クレーターを利用した月面都市やラグランジュ点のスペースコロニーなどリアリティがあり、ガンダムの世界に夢中になりました。
子どものころ、将来はどういう職業に就きたいと思っていましたか?
家電を分解するだけでなく、説明書を読むのも好きでした。理解しづらいところがどうしても気になってしまい、分かりやすい説明書をつくる仕事をしたいと考えていたころもありました。
高電圧工学から宇宙研へ
大学や大学院ではどのようなテーマに取り組んだのですか?
大学では工学部電気工学科に進み、大学院では高電圧工学の研究室に所属しました。博士課程のときは、電力分野の課題である放電現象の抑制を目指し、放電過程の観察や定式化に取り組みました。
高電圧実験は、3階分ほどの吹き抜けのある広いホールで行われます。通常、抵抗やコンデンサといった電子部品は米粒ほどのサイズですが、高電圧実験で使うものは数メーター以上あります。それらをクレーンでつり上げ、回路を組み立てます。そうしたスケールの大きな実験は、とても刺激的でした。
その時点では、宇宙との関わりはなかったのですか?
大学院修了まで宇宙とは関わりがなく、就職も電力系の研究所を考えていました。そんな折、宇宙研で高電圧や放電を専門とする研究者を募集していることを耳にしたのです。その少し前、NASDAが打ち上げた地球観測技術衛星「みどりII」で、太陽電池パネルからの供給電力が急激に低下し、運用を停止するという問題が発生していました。募集の背景には、そういう事情もあったようです。もともと宇宙に興味があったので応募したところ、採用していただきました。タイミングも良く、運にも恵まれていたと思います。
宇宙研に来てまず驚いたのが、高電圧という概念の違いです。大学院では最大210万ボルトで実験をしていました。ところが、宇宙分野では200ボルトで高電圧だというのです。1,000分の1です。分野によってこれほど変わるものかと、衝撃を受けました。
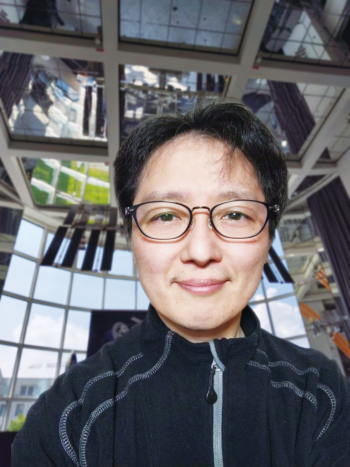
宇宙用太陽電池の品質評価方法を革新
これまで、どのような研究開発に携わってきたのでしょうか?
私が宇宙研に入ったのは2005年で、金星探査機「あかつき」と水星探査機「みお」の開発が本格化するタイミングでした。まず、それらのプロジェクトで太陽電池の開発を担当しました。「あかつき」と「みお」は、日本初の内惑星探査機です。太陽に近付くため太陽光の強度は、金星では地球の2倍、水星では11倍にもなります。そのため、強い太陽光にも耐えられる太陽電池の開発が、大きな課題になっていました。「みお」のために開発された内惑星の熱真空環境を模擬できる試験装置を利用し、実験を重ねましたが、特に「みお」の太陽電池の開発は困難を極めました。新しい実験をするたびに新たな課題が出てきて、経験の浅い私は、もう実験をしない方がいいのではないかと思ったほどです。
「あかつき」「みお」の太陽電池開発では、特にどのようなことに取り組んだのでしょうか?
当時、私は田島道夫先生の研究室に所属していました。田島先生は、シリコン結晶にレーザー光を当てることで励起された電子が、基底状態に戻る際にエネルギーを光として放出するフォトルミネッセンスという現象を利用した半導体評価研究の第一人者です。放出される光の相対強度がシリコン結晶中の不純物濃度に比例することを発見し、国内外の半導体評価基準として採用されました。また、非破壊でシリコン結晶中の欠陥の二次元分布を可視化できます。この手法はシリコン以外の半導体結晶にも適用でき、半導体や太陽電池の品質評価に広く使われるようになりました。電流を流した場合も同様の現象が生じ、エレクトロルミネセンスと呼ばれ、これも品質評価に使われています。
一方、宇宙分野では、太陽電池1枚1枚を人がルーペで見て、クラック(割れ)などの異常がないか検査していました。この作業には高度な技術を要し、熟練者にしかできません。そこで私たちは、フォトルミネッセンスとエレクトロルミネセンスを「あかつき」と「みお」の太陽電池の検査に導入しました。この方法を用いれば、クラックなどの異常が素人でも一目で判別できます。これらを宇宙用太陽電池の検査に使ったのは世界初で、国際会議で発表した際には大きな反響がありました。この経験を通じて、私は研究と開発の橋渡しの重要性を強く意識するようになりました。
SLIMの想定外の月面着陸を支えたバッテリーと太陽電池
宇宙用のバッテリーについては、どのような研究開発をされてきたのでしょうか?
宇宙飛翔工学研究系の大山聖さんから、火星探査用の飛行機のバッテリーについて相談を受けました。従来の宇宙用バッテリーは、真空中で膨張しないように、また打上げ時の衝撃や振動にも耐えられるように、外装に金属缶を使った頑丈なつくりになっています。とても重いため、火星飛行機に搭載できません。
軽量化のよいアイデアがないか考えた末、発想を転換しました。バッテリーだけで頑張って強度を出すのではなく、バッテリーの外装の強度はそこそこでよいとして、翼の中に入れるなど構体と合わせて必要な強度を持たせることを考えたのです。そして、古河電池と協力し、外装にSUS(ステンレス)の0.1mmの薄板を用いたラミネート型電池を開発しました。このSUSラミネート電池は、火星飛行機より先に小型月着陸実証機SLIMに搭載されました。
集中しすぎると視野が狭くなり、新しいアイデアが生まれにくくなります。むしろ、皿洗いやシャワー、通勤中に、思いがけないアイデアが浮かぶものです。このときも、そうでした。
SLIMに搭載されたSUSラミネート電池は期待通り機能しましたか?
SLIMは月面ピンポイント着陸に成功しましたが、想定外の姿勢だったため着陸直後は太陽電池に光が当たらず、発電ができませんでした。その状況でもSUSラミネート電池の電力を使うことで、データを地上に送信し、マルチバンド分光カメラによる初期観測もできました。よし!と思いましたし、今でも月を見ると、SLIMがあそこにいるんだなと感慨深いです。
SLIMは、太陽電池も画期的でした。シャープが開発した3接合型太陽電池で、非常に薄くて軽く、曲げることもできます。宇宙で使われている3接合型太陽電池の厚さは150µmほどです。SLIMの太陽電池の厚さはわずか13µm。薄くなると熱暴走のリスクがありますが、それを抑制し製品化に成功しているのは世界でシャープだけです。
月の夜は地球の時間で約14日間続き、マイナス180℃にもなります。SLIMは夜を越えられないと考えられていたのですが、夜が明けて太陽電池に光が当たると発電が始まり、SLIMは再起動しました。そして、夜をなんと3回も越えられました。これは、この太陽電池の性能がいかに高いかを示しています。
日本の太陽電池の技術は世界トップです。しかし国内だけでは需要が少ない。そうした中、DESTINY⁺に搭載する薄膜太陽電池パドルが、ESAの探査機RAMSESに採用されることになりました。RAMSESは、2029年に地球に接近する小惑星アポフォスを探査します。実績が増えれば、日本の太陽電池をもっと使ってもらえるのではないかと期待しています。使ってもらうことで、技術もさらに育ちます。
低温で充放電可能な電池、ワイヤレス充電、温度差発電......
ほかにも開発中のものがあれば、教えてください。
超小型火星着陸機に搭載する、低温で充放電が可能なリチウムイオン電池の開発を進めています。リチウムイオン電池の最適な使用温度は20℃~30℃程度で、0℃以下では充電しないように説明書に書かれています。無理矢理充電すると、表面にリチウムが析出し、ショートすることもあります。
火星表面の温度は、最も高い赤道域でもマイナス60℃ほどです。ヒーターで温めることはできますが、使用電力はできるだけ抑えたい。そこで、低温で機能する電池が求められています。さすがにマイナス60℃では電解液がシャーベット状になってしまうため、マイナス30℃で充電も放電もできる電池を目指して、半導体エネルギー研究所と協力しながら試作中です。
電源系に関して、さらに将来的な構想はありますか?
ワイヤレス充電を実現したいですね。ワイヤレス充電は、地上では広く使われていますが、宇宙では実証段階にとどまり実用化には至っていません。天体の表面を探査する場合、ダストやレゴリスがケーブル接続の障害になります。無人探査では接続の位置合わせが難しく、有人探査では電極が露出していると危険です。ワイヤレス充電の実現を目指し、青山学院大学と共同研究を始めたところです。
惑星間飛行では、電力を得る手段として、多くの場合で太陽電池が使われています。宇宙空間で環境から得られるエネルギーのうち、最も密度が高いのが太陽光だからです。しかし、木星より遠くの天体、月の縦穴や永久影の探査では、一番は必ずしも太陽光ではなくなります。NASAの探査機の中には原子力電池を搭載したものもありますが、安全面で課題があります。例えば、生命探査の対象となっている木星の衛星エウロパや土星の衛星エンケラドスは表面を覆う氷の下に海があり、海底からは熱水が噴出しています。海水の温度差や海流を使って発電できないか。木星の衛星イオは火山活動が活発なので、地熱が使えないか。木星や土星は磁場が強いので、放射線帯の高エネルギー粒子を電力に変えられないか。こうした新しい発電手法を模索しています。
宇宙研在職中に、あと一つか二つ、自ら開発したものを探査機に搭載できたらいいなと思っています。また、自分はいろいろな人との出会いに恵まれ、チャンスを与えてもらいました。これからは、次の人に引き継いでいくことも自分の役割だと思っています。
運も実力のうち
電源系に携わってきた20年を振り返って、どのようなことを思いますか?
自分は運が良かったと感じています。そして、運が巡ってきたときに、そのチャンスを活かせたことも実力の一つではないかと思うのです。自分のことを実力があると言うのは気恥ずかしいのですが、運がいいと思えることも実力の一つだし、実力があれば運を引き寄せることもできるのかもしれません。
研究開発を行う中で、心掛けていることはありますか?
絶対にこれをやりたい、と決めて進むタイプではありません。そのときの環境で、自分が何をやれば自分も周りの人も楽しく、そしてプロジェクトが成功するかを考え、それに全力で取り組むことを心掛けています。
電源系の研究開発の面白さは、どういう点だとお考えですか?
地上では、電力はコンセントにプラグを差せば簡単に手に入ります。あって当然のもので、なければ困る存在です。宇宙探査においても電力は不可欠で、常に新しい技術開発が求められます。でも実現して探査機に搭載されたとき、電源系は前面には出てきません。そういう立ち位置も、自分に合っていて心地よく感じます。
【 ISASニュース 2025年2月号(No.527) 掲載 】(一部加筆)

