TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > X線で白色矮星の重さを測る
![]()
| │1│2│3│ |
X線天文衛星「すざく」による白色矮星の観測
私たちのモデルの問題点は、白色矮星の重さだけでなく、単位面積当たりのプラズマ流量も同時に測定する必要があることです。そのため、精度が不十分な観測にこのモデルを適用すると、白色矮星の重さがうまく求まりません。その問題を解決してくれたのが、X線天文衛星「すざく」です。
「すざく」は2005年7月に打ち上げられ、現在も活躍中の日本で5番目のX線天文衛星です。アメリカとの国際協力で製作されました。「すざく」には、X線望遠鏡(XRT)とX線CCD(XIS)の観測システムが4組と硬X線検出器(HXD)が1台搭載されています。XRTとXISの観測システムは0.2〜12keV(電子ボルト。1電子ボルトは電子1個が1Vの電位差で獲得するエネルギー)のエネルギーのX線を観測でき、HXDは10〜600keVをカバーしています。
これまでに20個ほどの強磁場白色矮星の良質なデータが「すざく」によって得られています。図2は、「すざく」によって得られた、うみへび座EX星と呼ばれる強磁場白色矮星のX線スペクトルです。
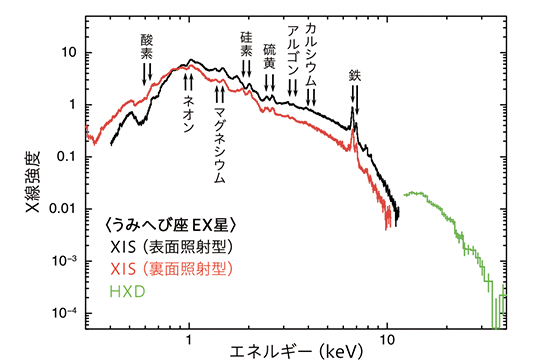
|
強磁場白色矮星に流れ込む数億度のプラズマが放射する10keV以上のX線は、HXDによる高感度な観測が可能です。図2の緑の線で示した通り、40keVまでしっかりとしたシグナルが得られており、プラズマの最高温度を高い精度で決定できます。
また、白色矮星のX線にはさまざまな「輝線」が含まれています。輝線とは、原子内の電子がより原子核に近い内側に落ちたときに放射される特定のエネルギーの光(X線)です。輝線の構造は元素の種類や温度で決まるため、輝線はそれを放射するプラズマの情報を与えてくれます。宇宙には鉄が豊富にあり、6〜7keVに現れる鉄の輝線はX線天文学で特に重要です。「すざく」のXRTとXISのシステムは、この領域で高い集光力と優れたエネルギー分解能を持っています。図2の矢印で示したように、「すざく」による観測では、鉄をはじめとするさまざまな輝線がはっきりと得られています。これにより、プラズマの温度や密度分布を精度よく測れます。
うみへび座EX星の白色矮星の重さは、従来のX線モデルと星の運動から求めた値が2倍も違いました。星の運動による測定は、白色矮星と伴星の両方の運動速度が測られ、さらに互いの陰に隠れる「蝕」も観測される系で、非常に高い精度が得られます。このような系は非常にまれですが、うみへび座EX星はこれを満たします。また、従来のモデルでは、プラズマ流の長さは白色矮星の半径に対して十分短いと算出されましたが、白色矮星の半径に匹敵することを示す観測もありました。
「すざく」によって得られたうみへび座EX星のデータに、私たちのモデルを適用すると(図3)、白色矮星の重さと単位面積当たりのプラズマ流量が見事に求まりました。得られた白色矮星の重さは太陽の重さの約![]() 倍となり、従来のX線モデルで求められた0.42±0.02倍より有意に重い結果になりました。一方で、星の運動から得られた0.79±0.023倍と、ぎりぎりですが誤差の範囲で一致しました。また、プラズマ流の長さは白色矮星半径の3分の1もあると見積もられ、上記の観測結果と一致しました。これらから、従来のX線モデルはプラズマ流の物理の取り込み方が不十分であり、私たちのモデルがより現実を表していることが分かってきました。こうして、私たちはX線による白色矮星重量の測定手法を、今までにない高い精度で確立しました。現在、磁場によるプラズマの冷却も取り入れたX線モデルの構築に取り組んでおり、さらなる精度向上を目指しています。
倍となり、従来のX線モデルで求められた0.42±0.02倍より有意に重い結果になりました。一方で、星の運動から得られた0.79±0.023倍と、ぎりぎりですが誤差の範囲で一致しました。また、プラズマ流の長さは白色矮星半径の3分の1もあると見積もられ、上記の観測結果と一致しました。これらから、従来のX線モデルはプラズマ流の物理の取り込み方が不十分であり、私たちのモデルがより現実を表していることが分かってきました。こうして、私たちはX線による白色矮星重量の測定手法を、今までにない高い精度で確立しました。現在、磁場によるプラズマの冷却も取り入れたX線モデルの構築に取り組んでおり、さらなる精度向上を目指しています。
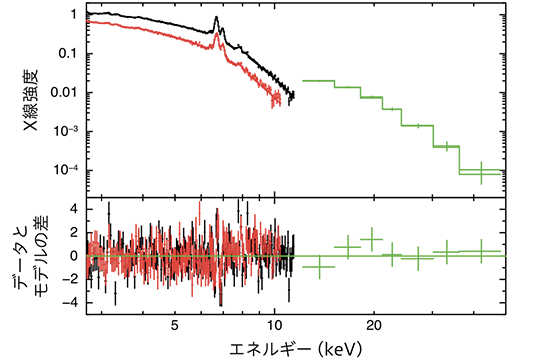
|
X線による白色矮星の重量測定法の強みは、星の運動によるものと違い、蝕などが観測されなくても高精度な測定が可能なことです。この手法を用いれば、系によらず、多くの近接連星内の白色矮星の重さを測定できます。
さらに高精度な測定に向けて
2015年に、「すざく」をしのぐ強力な観測機器を搭載した次期X線天文衛星ASTRO-Hが打ち上げられます。ASTRO-Hをもってすれば、白色矮星の重さを格段に精度よく測ることができます。
また、私たちのモデルが不十分であったり、もしかすると間違えであることを思い知らされるかもしれません。しかし、私たちはそれをとても楽しみにしています。
(はやし・たかゆき)
| │1│2│3│ |
