TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「あかり」衛星で探る星間塵の一生
![]()
| │1│2│3│ |
星間塵
宇宙空間の星々の間には、無数の小さな固体微小粒子が漂っています。それらは、「星間塵」あるいは「星間ダスト」と呼ばれ、小さいものでは数ナノメートル以下のものまであります。これらの塵は、例えば、太陽系内の微惑星などの固体物質の原材料として、あるいは、宇宙空間におけるさまざまな天体現象や星間環境の中で複雑な化学過程を経ることにより、生命体の素ともいえる有機物の形成において重要な役割を演じていると考えられています。したがって、こうした塵がどのように生まれ、宇宙空間の中でどういった進化を遂げるのかを理解することは、化学的・物質的に豊かな現在の宇宙がいかにしてつくり上げられてきたのかを知る上で不可欠であり、今日の天文学における重要なトピックの一つだといえます。
塵の放つ赤外線
それでは、こうした塵の性質を探るには、どうすればよいのでしょうか? そのためには、塵の放つ光について理解する必要があります。星間塵は、主に星が放つ可視光や紫外線を受けて、絶対温度で数十K(ケルビン)から数百Kに暖められ、その結果、自ら赤外線を放つようになります。ただし、塵から放たれる赤外線の色調(スペクトル)は、仮に同じ温度の塵であっても、物質の種類によって異なります。したがって、赤外線を用いた観測によって塵からやって来る光を詳しく分析してやれば、どのような種類の物質がどういった物理環境のもとで存在しているのかを探ることができるのです。こうした赤外線観測には、大気の熱放射や吸収などの邪魔を受けない宇宙からの衛星観測が適しています。そこで私たちは、赤外線天文衛星「あかり」を用いて、宇宙空間における星間塵の一生を探る試みを進めています。本記事では、そうした試みの一環として、「あかり」の観測に基づく最新の研究成果のいくつかを報告します。
「あかり」がとらえた超新星周囲での塵誕生の現場
星間塵には、黒鉛やダイヤモンドの粉末のような炭素質のものや、ガラスや石英、サファイアの粉末のようなケイ素質のものをはじめ、さまざまな元素が含まれています。こうした水素やヘリウムより重い元素は、恒星の進化の中で、恒星内部の核反応により合成されます。そして、恒星が一生の終焉を迎え、化学的に豊かな元素を含むガスを宇宙空間に放出し、その結果、冷えた放出ガス中で塵が形成されるのだと考えられています。しかしながら、どのような種類の塵が、どのような星の進化の末に形成されるかについての観測的な証拠は少なく、依然として塵の誕生過程は多くの謎に包まれています。
さて、超新星爆発というのは、太陽のおよそ8倍以上の重い星が終焉を迎える際に、星内部で合成した元素を含むガスを宇宙空間にまき散らす瞬間の姿です。初め主として水素とヘリウムだけしかなかった宇宙が、現在の惑星や生命体に至るまでさまざまな固体物質や化学的に豊かな環境を有する宇宙となる過程で、特に早期宇宙の化学進化においては、この超新星爆発が重要な役割を演じていると考えられています。というのは、超新星爆発を起こすような重い星は、進化の寿命が数百万年と短く、宇宙空間に効率的に化学的に豊かな物質を供給し得るからです。もし超新星周囲での塵の形成の様子が観測的に明らかになれば、超新星爆発を起こさずに終焉を迎える小・中質量星に加えて、大質量星が、宇宙空間に漂う塵の誕生に深く寄与することが分かり、早期宇宙における星間塵の起源について重要な情報を得ることができます。
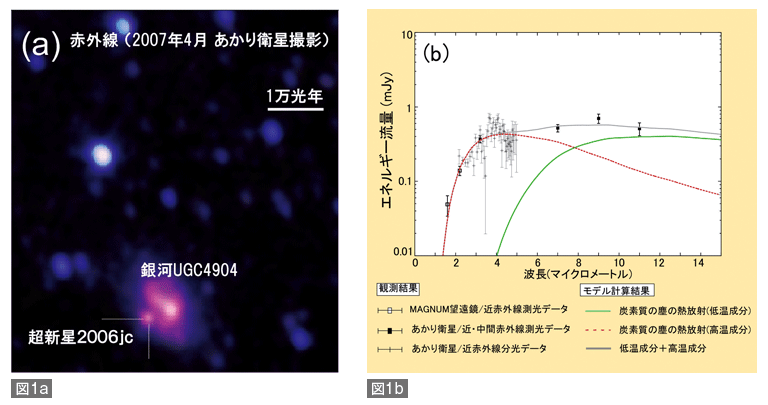
【画像クリックで拡大】
|
| │1│2│3│ |
