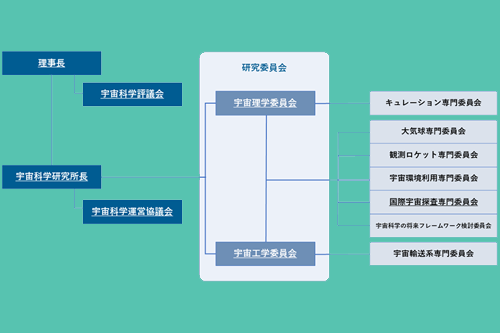SLIMが月面に着陸した日、管制室では何が起こっていたのか?SLIMプロジェクトの成功を振り返る~International SpaceOps Award for Outstanding Achievement (AOA) for 2025、受賞インタビュー:宮澤優氏、石田貴行氏(SLIM Operations Team)~
2025年8月18日 | あいさすpeople
2025年5月26日~30日にカナダのモントリオールで開催された18th International Conference on Space Operations(SpaceOps)にて、SLIM Operations Team(SLIM運用チーム)がInternational SpaceOps Award for Outstanding Achievement (AOA) for 2025を受賞しました。
小型月着陸実証機SLIM(Smart Lander for Investigating Moon)は、2024年1月20日(日本標準時)に日本で初めて月に着陸した小型探査機です。SLIMは、世界初の高精度なピンポイント着陸*1をはじめとする多くの科学的成果を上げただけでなく、着陸直前のトラブル*2や想定外の姿勢での着陸を乗り越えての月面運用*3を行い、歴史に残るミッションとなりました。
本インタビューでは、SLIM運用チームを代表して授賞式に登壇された宮澤優氏と石田貴行氏にお話を伺いました。授賞式の感想と併せて、着陸運用の中心人物だったお2人に、着陸当日の管制室の様子や、それぞれが運用やトラブル対応をする中で何を感じ、考えたのかを振り返っていただきました。

宮澤 優(宇宙探査イノベーションハブ/主任研究開発員)
SLIM運用スーパーバイザ(運用リーダ)として、月着陸当日の管制室で全体の状況を把握し、コマンドの指示を送る等、運用の指揮を執った。SLIMの電源系も担当。(宮澤さんが執筆されたSLIMの電源系について記事はこちら)

石田 貴行(宇宙科学研究所科学衛星運用・データ利用ユニット/研究開発員)
SLIMのピンポイント着陸のキー技術のひとつ、画像照合航法を担当。画像照合航法によりSLIMは月軌道上で自身の位置を測定し、自律的に軌道修正することで目標地点に着陸することができる。目標としていた100m以内の着陸精度を見事に実現した。(石田さんが執筆されたSLIMが自身の位置を誤認してしまった場合に備えて開発された地上システム「画像航法支援系」についての記事はこちら)
この度はSLIM運用チームでの受賞、おめでとうございます!受賞の感想を教えてください。

宮澤: ありがとうございます。SpaceOpsは、宇宙に関する学会の中でも、地上での運用や地上システムに特化した学会です。今回の受賞理由として、SLIMがピンポイント月面着陸を成功させたことだけでなく、着陸時に起きたトラブルにも運用チーム全員が落ち着いて対応し、理学観測や越夜運用を含めて最後までミッションを完遂させたことを評価していただけたのはチームの一員として非常に嬉しかったです。また、この賞は2012年に宇宙科学研究所(宇宙研)を象徴するプロジェクト、小惑星探査機「はやぶさ」の運用チームも受賞しているので、その後に続くことができたのも良かったです。
石田: 今回の賞はSLIMのミッションそのものというよりも、地上で運用をしていた人間が、どう頑張ってミッションを成功させたかを見ていただけたと思っています。例えばSLIMは越夜を3回達成しましたが、それはSLIMの探査機自体が素晴らしかっただけでなく、地上から地道にコマンドを送り続けたオペレータの頑張りがかなり大きいです。そういった我々の努力に対して「頑張ったね」と言ってもらえたものだと理解しています。
宮澤さんは運用リーダとして、石田さんは画像航法担当として、着陸運用の中心人物だったと伺っています。着陸当日のことを教えてください。
宮澤: 着陸の運用が開始してからは、様々な異常を模擬した訓練とは違ってトラブルもなく順調に進んで行きました。各フェーズのチェックポイントで担当者から報告の声が上がるので、全員がSLIMの状況を把握しながら、それぞれが着実に決められた役割をこなしていました。
石田: そうですね。着陸運用の時間は非常に短いので、報告のタイミングも文言も、台本で一言一句決まっています。私も画像航法担当として報告をしたのですが、SLIMが動力降下を開始する直前の、1番最初の画像照合航法を実施した時の「画像航法、よし!」の声は、緊張で上ずったのを覚えています(笑)。ここの画像照合航法の成否が着陸のGO/NO GOの判断基準の1つで、ここを失敗したらほぼミッション失敗だったので、私の人生で1番緊張した瞬間でした。
宮澤: 石田さんが緊張していたことには全く気がつきませんでした。でも、みんな訓練の時より声が大きかった気がします。
全てが順調に進んでいたのが、着陸前後にトラブルに見舞われましたね。その時の管制室の様子を教えてください。
宮澤: 私が異変に気が付いたのは、モニタに映るSLIMの推定着陸姿勢が想定外であることと太陽電池が発電していないことが判明した時でした。その時点で通信は取れていて、SLIMが生きていることは確実だったので、大きなパニックにはなりませんでしたが、その直後はみんなで「なんだ?なんだ?」とはなりましたね。
石田: そうでしたね。ただ、太陽電池が発電していないということは、SLIMに搭載しているバッテリで運用しているということで、残り時間が迫っていました。太陽電池が発電していれば数日間の運用が可能ですが、とりあえずその時はあと数時間しかないと瞬時に分かったので、すぐにデータを取り出そうという冷静な判断がありましたね。
宮澤: そうですね。トラブルはあったものの、事前に準備していた手順で決められていたとおりに運用を続けました。バッテリの過放電や故障で探査機が永久停電しないよう、バッテリが空になる前に切り離す必要があったので、電源系の担当者にバッテリの持ち時間をすぐに教えてほしいと伝えて、バッテリの切り離しまでの時間を確認しました。もともとバッテリを切り離す用意はしていたのですが、SLIMが逆立ちしてしまったことで予定よりも早く切り離すことになりました。その後は、残り時間も見ながらデータを地上に下ろし、マルチバンド分光カメラ(MBC)の観測運用も実施できました。非常に慌ただしくはありましたが、落ち着いて想定通りの運用ができたと思います。
トラブルが起きた時、どのようなことを考え、行動しましたか?
宮澤: 何が起こったのか気になりはしましたが、着陸後運用をする上では、トラブルの原因を考えるよりも今できることに注力することが重要です。SLIMのデータを地上に下ろすことが最優先でしたが、そのためにはたくさんの手順があったので、他のことを考えている余裕はなかったです。何か運用に支障が出るようなことが起きれば、担当者から報告が来るので、私は自分の作業に集中して取り組みました。
石田: 私は画像航法や航法カメラ担当する立場として、限られた時間の中で急いで画像データを地上に送信することになったので、とにかくデータの取りこぼしがないか、全てダウンリンクがされているかに集中していました。ダウンリンクが終わった後は、すぐにその画像データを可視化して、チームのみんなに見てもらいました。その時の画像でトラブルの原因となったメインエンジンから離脱したスラスタ(ノズル部)も確認しました。
宮澤: あの画像を見た時は、管制室がどよめきましたね。
石田: 着陸後にやることは全員決まっていたので、管制室全体が、とりあえず探査機で何かが起きていることは間違いないけど、一旦自分の役割に集中しようという空気だったと思います。
バッテリを切り離し、探査機の電源がOFFになった時は、どのような様子でしたか?

宮澤: 「終わったかー!」って感じでした。
石田: 疲れましたよね。「切れたか~」という感じで。
宮澤: 管制室の雰囲気としては、電源を切るまでにやるべきことはできたものの、その時点でSLIMが必ず復活する保証はなかったので、お祭りムードではありませんでした。想定通りの着陸姿勢であれば着陸後からそのままミッションの観測運用を数日間実施する想定でしたが、それができずにバッテリによる動作を強制停止させてしまいましたので。何とも言えない達成感と悲しさが入り混じった感情でした。
石田: そうでしたね。ミッション機器の方々に少し申し訳ない気持ちがありました。どちらかと言えば反省会のムードでしたね。
SLIMと通信を再開するまでと、再開した時のことについて、教えてください。

宮澤: 着陸した翌日の昼から、毎日運用はしていました。着陸した日のうちに、SLIMが太陽電池パネルを西に向けた姿勢で着陸しているだろうと分かっていたので、太陽が当たれば発電すると期待していました。ただ、予想と違うことが起こっている可能性もあるので、連日SLIMに「起きて、起きて」と、色々と条件を変えながら通信機をオンにするコマンドを送りました。ミッション機器の担当は、いつSLIMが起きても良いように毎日運用室に来ていたので、我々が諦めるわけにはいかないと強く感じながら運用にあたっていました。復活した時は一気にみんな元気になりました。着陸した後は全力で喜べなかったので、この時に初めて心から喜べて、やっとみんな笑顔で運用ができると思って嬉しかったです。
SLIMが越夜を達成した時や、運用終了を迎えるまではいかがでしたか?
宮澤: SLIMは3回の越夜を達成しましたが、1回目はすごく驚きました。
石田: 驚きましたよね。そもそもSLIMは月の朝の3日間しか運用しない前提だったので、4日目以降は耐えられるような設計になっていません。最初に通信が復活した時も当初予定していなかった真昼間を通った上で起きたのですが、越夜までできるんだなと思いました。
宮澤: 最初に再開した時に日没まで運用をやり切れていたおかげで、チームは割と楽観的な雰囲気で、「越夜ができたら頑張ろう」と言っていた中で生き返ったので、テンションが上がりました。
石田: 「行けるところまで行こう!」という感じでしたね。その後、2回目3回目と越夜が成功したので、もうこのままずっと生き続けるのではないかと思って、当然4回目も期待していました。
宮澤: 4回目も起きると信じていたので、残念でした。4月が最後だったのですが、5月以降も諦めずに運用を続けていました。8月に停波運用をして、SLIMの月面での運用を終えた時は、やり切ったとはいえ寂しかったです。
SLIMプロジェクトチームはどのようなチームでしたか?
宮澤: 個人的には若手とマネージャ級の経験者とのバランスがすごく良いチームだと感じていました。SLIMに参加したメンバは若手が多く、SLIMが初めてのミッションという方が多かったのですが、やる気に満ち溢れていました。その上で、ベテランの先生方が、若手メンバが面白いことや難しいことに挑戦できる機会を持ちやすいようにしてくれたので、そこが良かったと思います。
石田: 私は、信頼関係がしっかりと構築されていたチームという印象です。例えば、運用が始まる直前には、かなりの人数で集まって運用の訓練を通しで行い、その中で問題がないか等の話し合いを毎週のように実施していたのですが、そういった集まりを通して、「このハードウェアシステムにはこの人がいるから大丈夫」といった信頼関係ができていったので、ある意味でみんながアイデンティティを明確に持って、自分の担当により集中しやすい環境だったと思います。
最後に、SLIMプロジェクトを振り返っての感想やメッセージをお願いします。
宮澤: 私は最初にSLIMのミッションを聞いた時、面白そうと思ったと同時に、本当にできるのかなと思っていました。ピンポイント着陸もそうですが、探査機の1つ1つの機器も複雑なものや新しいものが多かったですし、開発途中で色々なトラブルもあったので、すごく難しいミッションだと感じていました。でも、そんな中でも誰も諦めずに、絶対にできると信じて取り組んでいました。色々な苦労もあった中で、みんなで難しいことにチャレンジして、団結して乗り越えることができたのは、すごく楽しかったですね。
石田: 私は2015年に宇宙研に来てから、ほぼSLIMプロジェクトだけに取り組んできましたが、同じ仕事を飽きずに続けてこられたのは、SLIMのミッションが非常に魅力的だったからだと思います。日本はそれまでに月に着陸したことすらなかったのに、1発目でピンポイント着陸を目指しました。ピンポイント着陸も画像照合航法も今まで誰もやってこなかったことで、達成出来たら世界初です。世界初のことに挑戦できる環境はあまり多くないと思うので、それが私のモチベーションでした。宇宙研は、こういった尖ったミッションが多いのが魅力だと思います。

宮澤: そうですね。私はSpaceOpsで月面着陸のパネルディスカッション*4にも登壇したのですが、他の登壇者が所属している団体は開発チームと運用チームで分かれていたので、両チームの連携が非常に重要といった話がありました。民間企業では、得意分野で担当分けをして効率を良くすることが目的だと思うのですが、JAXA、特に宇宙研のミッションは、開発も運用も同じ人達がやることが多いです。おそらくこれもすごく強みで、SLIMの成功に繋がっているように思います。
石田: 宇宙研の文化ですよね。世界初に挑戦ができる環境で、自分で開発して運用もできるというのは、かなり貴重だと思います。
本日は貴重なお話をありがとうございました。SLIMを歴史に残るミッションにしてくださったチームの皆さんの、今後益々のご活躍も楽しみにしています!
用語解説
- *1 SLIMミッションの目的のひとつ「ピンポイント着陸」は、従来の月着陸精度である数km~10数kmに対して100mオーダーの実証を目指した。結果として、着陸目標地点から60m程度の位置に着陸を成功させた。
- *2 着陸の約34秒前、高度50m付近で推進系に異常が発生した。具体的には、メインエンジン2機のうち1機のノズルが離脱し、推力が低下した。
- *3 月表面は、14日間の昼間と14日間の夜間を繰り返す。月の昼は約110℃、夜は約-170℃とその差は200℃以上。夜間を越えて活動する「越夜」は大きな温度変化を伴うため、SLIMの設計上想定していなかったが、3回の越夜に成功した。
- *4 宮澤さんが参加されたパネルディスカッションはこちら|SpaceOps 2025 Plenary & Keynote Speakers Plenary 1 | Lunar Exploration: Landing on the Moon