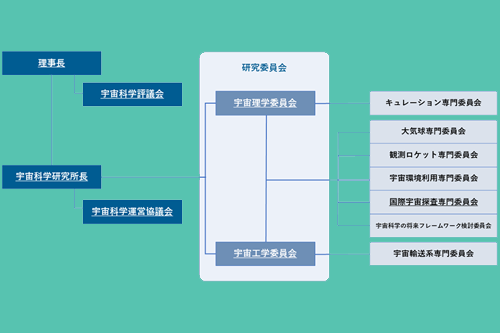人生初の観測ロケット実験、担当した機器の評価で見事に受賞!
~SPIE ASTRO 2024 Best Paper Prizes、受賞インタビュー:清水里香氏~
2024年10月17日 | あいさすpeople, 表彰・受賞

清水里香氏(総合研究大学院大学 宇宙科学専攻/5年一貫制博士課程3年)が2024年6月15日から21日にパシフィコ横浜で開催された「天体望遠鏡と観測装置」に関する国際光工学会(SPIE)主催のシンポジウムSPIE ASTRO 2024の「X-Ray, Optical, and Infrared Detectors for Astronomy XI (AS112)」にて、「Evaluation of a CMOS sensor for solar flare soft X-ray imaging spectroscopy onboard the sounding rocket experiment FOXSI-4」と題する口頭発表を行い、Best Paper Prizeを受賞しました。本インタビューでは、受賞内容と併せて、参加された観測ロケット実験や清水さんの研究に対する思いについて、お伺いしました。
この度は「Best Paper Prize」の受賞、おめでとうございます!学会での様子や受賞の感想を教えてください。
ありがとうございます!SPIEのような国際的な大きな学会への参加は初めてで、とにかく人が多くて驚きました。私の講演にも100人以上の方が聞きに来てくれていたと思います。初めての英語での発表ということもありとても緊張しましたが、参加者から質問もあり、「興味を持ってくださっている!」と実感できて、嬉しかったです。研究室や日米のFOXSI-4チームメンバー等、たくさんの方から受賞をお祝いしていただきました。
今回の講演は日米共同の観測ロケット実験FOXSI-4に搭載された機器についてですね。FOXSI-4とはどのようなプロジェクトですか?
FOXSI(Focusing Optics X-ray Solar Imager)シリーズは、太陽コロナにおける高エネルギー現象の理解を目指した日米共同の観測ロケット実験です。NASAの観測ロケットを使用し、日米の複数の大学や研究機関のX線観測技術を組み合わせることで、太陽のX線を観測しています。今回のFOXSI-4は、このシリーズの4度目の飛翔です。
FOXSI-4では、世界初の観測ロケットによる中規模以上の太陽フレアの観測を行いました。太陽フレアは、太陽大気で起こる爆発現象です。太陽には、磁石のようなN極とS極がたくさんあり、この2つの極をつなぐ磁力線が接近して、ある限界点を超えて磁力線につなぎ変わりが起きる(磁気再結合)と、そのエネルギーが爆発となって現れると考えられています。この発生のメカニズムは、明らかになっていないことが多く、FOXSI-4はその解明に向けて計画されました。
FOXSI-4は、2024年4月17日に米国アラスカ州から無事に打ち上げられ、太陽フレアから放たれるX線を詳細に観測(集光撮像分光観測)することに成功しました!
清水さんも、アラスカでのFOXSI-4の打上げに参加されたのでしょうか?

参加しました!観測ロケットは衛星と違って、ロケット自身が宇宙空間を飛行しながら落下するまでの間に観測を行います。打上げから30分程度で落下しますが、実際に宇宙空間で観測できるのは中盤の5~6分間ほどです。
FOXSI-4は、太陽フレアが発生するタイミングに合わせてロケットを打ち上げ、観測を行うミッションでした。フレア予測を担当しているチームがいて、太陽の状態をリアルタイムでモニターして、打上げの機会を見定めていました。1日4時間の打上げウィンドウ*1の中で、「太陽のこの場所で起こりそう」とか「まだちょっと早いね」といった話し合いをしているのを見ながら、打上げの判断があるのをドキドキしながら待ちました。実際にFOXSI-4が打ち上がると、無事に飛翔したのを10秒ほどは直接見られましたが、すぐに持ち場へバタバタと戻り、データ確認の作業に入りました(笑)。
FOXSI-4は、私にとって初めての宇宙プロジェクトであり、初めての国際ミッションでもありました。大規模なプロジェクトではありませんが、観測ロケット実験を経験し、ミッションの在り方や流れを知ることができました。ここで学んだ多くのことは、私の研究に対するモチベーションをさらに大きくしてくれました。
FOXSI-4のプロジェクトでは、主にどのようなことを担当されたのでしょうか?

私たちは、搭載観測装置の一つである「軟X線観測用CMOSカメラ」という、1秒間に250枚の撮像が可能な高速度カメラを主に担当しました。このカメラを使うと、「光子計測」という、X線の光子(光の粒子)を1つずつ取得する手法で観測ができます。撮影した画像には、センサーを通して電子に変換された光子の1つ1つが白い点となって写ります。白い点の1つ1つが画像のどこ写っているかによって、X線が太陽のどの位置から出たのかという「場所の情報」が分かったり、撮影時はシャッターを連続で切り続けるため、どの画像に写っているかによって、いつ太陽から出たX線かという「時間の情報」が分かったり、白い点がつくるセンサーの出力値はX線のエネルギーに比例しているため、「エネルギーの情報」も得られたりと、様々なことを同時に知ることができます。光子計測は太陽に対してまだ新しい手法なので、今後もっと活躍するのではないかと思います!
今回の受賞は、このカメラに関係するものですね。発表内容を教えてください。
今回の講演では、軟X線観測用CMOSカメラのセンサーについて、放射光施設での実験を通してX線に対してどのような反応をするか評価し、この機器が太陽フレアを観測するのに有用であることを発表しました。
放射光施設の実験では、センサーにX線ビームを当てて、センサーから出力される値を解析しました。一般的に評価を行う場合は、いくつかのエネルギー値を取ってモデル化し、シミュレーションをすることで性能を見ることが多いですが、今回は使用するカメラがかなり高速に撮影できデータも早く取得できることから、実験で細かくたくさんのデータを取得して性能を見る方法を取りました。具体的には、X線ビームのエネルギーを0.8 keVから10 keVまで25 eV単位で段階的に変えてセンサーに当てて、その反応を解析しました。今回の実験で、センサーは当てられたエネルギーの値に対して、高い精度で反応を示すことが確認できました。
今回の講演では、センサーの有用性を示したことに加えて、少し珍しい内容も発表しました。光子のエネルギーを観測するには、光子1つ1つを区別できるよう、画像の白い点が重ならずに独立している必要があります。しかし、エネルギーの値が高いと、光子が電子に変換される過程で広がり、画像で解析する際に複数のピクセル(画素)にまたがって検出されることがあります。そこで、今回の実験で得たデータから、エネルギーの値に応じて電子がどの程度の割合で広がるかを表にまとめて発表しました。どれくらいのエネルギーでどの程度広がるかが分かれば、観測する際に白い点同士がくっつかないように減光することで、光子1つ1つのエネルギーが分かるようになります。この資料は、センサーを専門としている方でも見慣れないものだったようで、表の見方についての質問も受けました。
今回の受賞は、細かい実験を行い、そこで得たデータを分析し評価した点が、好評いただけたのだと思います。100テラ(1012)バイト弱ほどあった膨大なデータを全て解析したのは本当に大変でしたが、頑張って良かったです!
たくさんの実験やデータ解析の努力も認められての受賞ですね!FOXSI-4打上げの翌月にも、大きな太陽フレアの発生やオーロラのニュースもあったので、太陽フレアに関心を持つ人も増えそうですね。

「推しフレア」のコーナーより。右が清水さん。
そうですね。最近は太陽フレアが話題になることが多かったので、嬉しかったです。太陽フレアは、その様子も美しいので、眺めるのも楽しいです。2023年11月に開催されたJAXA相模原キャンパス特別公開*2では、宇宙科学研究所(宇宙研)の太陽研究者から動画配信をしましたが、私は太陽フレアの魅力をお伝えするべく、「推しフレア」のコーナーを担当しました。このコーナーでは、同じ宇宙研の太陽研究者の方々から、お気に入りのフレアを投票していただいて、その中のいくつかを動画にして発表しました。学術的な意味だけではなく、美しさ、かわいさ、ダイナミックさ等、芸術的な意味での投票も多かったです。去年初めて作ったコーナーでしたが、評判もよかったです!
美しくもあり、かわいくもある太陽フレア、大変魅力的ですね!ところで、清水さんが現在の進路を選んだのは、何かきっかけがあったのでしょうか?
宇宙に興味を持ったのは小惑星探査機「はやぶさ」*3からで、そこからずっと宇宙が好きです。昔から自分の手で何かを作ることも好きだったので、進路を決めるうえでは「宇宙」と「ものづくり」を掛け合わせた道を考えました。今の研究に進むきっかけとなったのは、太陽研究に興味のある大学学部生向けツアーに参加したことです。様々な先生方が研究内容を紹介してくださる中で、観測ロケット実験やFOXSIシリーズについて知りました。衛星プロジェクトの場合、10年以上の長い期間をかけて進められるものが多いですが、観測ロケット実験は5年ほどの短い周期で実施されます。これは、学生の間に「装置開発→打上げ→データ解析」の工程をやりきることができるサイクルの短さです。宇宙プロジェクトを一通り経験したいと考えていた私にとっては、大変魅力的でした。また、そのツアーに参加したときにはFOXSI-4の計画もすでに決定していたので、タイミング的にもバッチリで、運命的な出会いだったと思います!
FOXSI-4の打上げが無事に達成されましたが、次はどのような予定が控えていますか?
FOXSI-4で自分が担当した機器が宇宙からデータを持ち帰ってきたことは、私にとって、かけがえのない経験となりました。これから世界初の太陽フレアのデータを解析する作業に入りますが、この作業も初めてなので、とてもワクワクしています。また、FOXSI-4が捉えた太陽フレアは、太陽観測衛星「ひので」でも同時に撮っているので、他のデータと合わせての解析も進めたいです。FOXSIシリーズについては、FOXSI-5の話が出ているので、そちらも実現したら参加したいですね。ゆくゆくは、衛星等のもっと大規模な宇宙プロジェクトにも参加していきたいです!
最後に、将来の展望について教えてください。

将来的には、理学・工学の枠を超えた研究者になることが目標です。理学的な面での太陽フレアの機構解明も、工学的な面での観測機器等の開発も、両方を担える人材になりたいです。私は昔から色々なことに人一倍の興味を示す性格で、今担当している研究を全力で進める中でも、「時間さえあれば、あれもやりたいな。これもやりたいな。」と考えています(笑)。進路を考えていた頃から現在に至るまで、「宇宙」と「ものづくり」の2本柱で走り続けたい気持ちは変わりません。この2本柱を軸に、好奇心旺盛な性格を活かして、宇宙のメカニズムを解明する科学者でありながら、機器の開発をする技術者でもある、ハイブリットな研究者としてのポジションを確立していきたいです!
本日は、素敵なお話をありがとうございました。幅広い分野で活躍される清水さんを、今後も楽しみにしています!
用語解説
- *1 打上げウィンドウ:科学目標や運用上の制約などを考慮したうえでロケットの打ち上げが許される時間帯のこと。
- *2 JAXA相模原キャンパス 特別公開:年に1度開催されるJAXA相模原キャンパスのイベント。2023年は、2日間にわたって開催され、1日目は現地で、2日目はオンラインで開催された。研究者や職員による工夫を凝らした活動紹介が行われる。
- *3 小惑星探査機「はやぶさ」:2003年5月9日に打上げられた小惑星探査機。2010年6月13日に、小惑星「イトカワ」から表面物資を地球に持ち帰ることに成功した。
関連リンク
- SPIE ASTRO 2024 SPIE ASTRO 2024 Paper Prizes
- SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation
- Evaluation of a CMOS sensor for solar flare soft X-ray imaging spectroscopy onboard the sounding rocket experiment FOXSI-4
- 宇宙科学研究所 太陽系化学研究系 ひのでプロジェクト
- 太陽X線研究グループ
- JAXA相模原チャンネル(YouTube)JAXAの太陽研究者が語る!太陽重大ニュース【JAXA相模原キャンパス特別公開2023】
- 太陽観測衛星「ひので」