火星の衛星フォボスの「色」は何が決めているのか?
2025年3月17日 | 宇宙航空プロジェクト研究員, あいさすpeople
研究概要
私は火星の衛星フォボスと火星の研究をしています。もともと「惑星の表層環境はどのように進化してきたのか?」ということに興味があり、大学院では火星着陸機が観測した鉱物データと室内実験とを組み合わせることで、火星の表層環境進化に関する研究を行っていました。火星の月であるフォボスは、JAXA/NASA/DLR/CNESの4宇宙機関の共同プロジェクトである火星衛星探査計画MMX (Martian Moons eXploration)の主要な探査ターゲットです。宇宙航空プロジェクト研究員として火星衛星探査計画MMXに携わる中で、衛星のフォボスから何か火星本体の進化史の情報も引き出せないだろうか?という観点から着想したのが「フォボスの『色』は何が決めているのか?」という研究テーマです。
惑星科学者が惑星の「色」と言った場合、天王星の青緑色や火星の赤色といった「実際の色」を指す時もありますが、「反射スペクトル*1の傾き」のことを指している場合もあり、ここでは後者の意味になります。フォボスは可視光ではほぼ灰色一色にしか見えないのですが(図1)、近赤外領域も含めた反射スペクトルの反射率の傾き(可視/近赤外の比)に注目して見ると、短波長(=可視光、青色側)の反射率が相対的に高い場所と長波長(=近赤外、赤色側)の反射率が相対的に高い場所とがまばらに分布していることが知られています(図2)。一般に、物質の反射スペクトルはその物質の化学情報(惑星の固体表面の場合は鉱物組成や結晶度)を反映しています。しかし、フォボス上に見られるこの「色」の分布が何を表しているのかは諸説あり、まだよくわかっていません。


ところで、昔の火星は今の地球のように水をたたえていたと聞いたことはあるでしょうか?これは、人類がこれまで行ってきた10機以上(!)の火星着陸探査機による鉱物や地層の分析から明らかになったことです。しかし、観察されているような地層の堆積には百万年以上の時間がかかり、そのような長期にわたって温暖な気候を維持するには厚い大気が必要です。このことから、火星はその歴史の中で大気の大部分を失ったと考えられています。火星は地球と違って強い磁場を持たず、重力も小さいため、大気が宇宙に散逸してしまうのです。では、この時フォボスはどうなっているのでしょうか?火星から流出する大気は電離したプラズマとしてフォボス表面に照射されます。その時、フォボス表面の物質はどういった影響を受けるのでしょうか?

このことを明らかにすべく、私はフォボスに火星大気が降り注ぐ環境を模擬した実験を行っています。専門的な言葉で言えば、宇宙空間に散逸した火星大気を模擬したプラズマをマイクロ波放電によって再現し、フォボス表面に存在すると考えられている種々の鉱物に浴びせています(図3)。実験の結果、模擬火星大気プラズマを照射する前後で鉱物の色が変わることがわかりました。この結果は現在、論文として投稿中です。人間の目ではほとんど「色」の変化は見えませんが、分析装置で反射スペクトルを測定すると確かに変化しているのです。特に、「スペクトルの傾き」に注目すると、鉱物によって「赤く」なったり「青く」なったりしていることがわかりました。つまり、フォボスの色の分布はフォボス上の鉱物組成の分布を表している可能性があります。また、この実験の結果はフォボス表面の物質が流出した昔の火星大気の一部を取り込んでいることを意味しています。火星衛星探査計画MMXが持ち帰るフォボス試料を分析すれば、過去の火星大気を復元できるかもしれません。フォボスの「色」が火星大気の影響を受けている仮説を検証し、火星大気の変遷といったさらなる謎を解き明かすべく、私は火星衛星探査計画MMXプロジェクトで探査機に搭載されるローバーの開発、運用、データの解析システムなど全体を通じた研究開発に携わり、充実したJAXAライフを満喫しています。
用語解説
- *1 反射スペクトル : ある物質が照射された光を反射する際の反射率を波長ごとにプロットしたもの(スペクトル)。


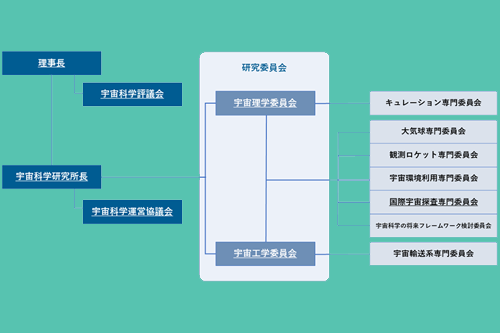

 田畑 陽久・太陽系科学研究系
田畑 陽久・太陽系科学研究系