「はやぶさ2#」の小惑星トリフネの近接フライバイ実現に向けた検討
2025年2月12日 | 宇宙航空プロジェクト研究員, あいさすpeople
研究概要
小惑星探査機「はやぶさ2」は、リュウグウのサンプルを地球に投下後、「はやぶさ2#」(はやぶさ2拡張ミッション)として、航行を続けています。このミッションにおける大きなイベントとして、小惑星トリフネ(2001 CC21)のフライバイ*1ミッションを2026年7月に控えています(図1)。このフライバイを行うことの意義として、小惑星の科学観測データを得ることに加えて、プラネタリーディフェンス*2に資する技術を獲得することが挙げられます。
「はやぶさ2#」のトリフネフライバイの特徴は、誘導精度を可能な限り高めて、小惑星のぎりぎりを通過することを目指していることです。これは次のような理由によります。「はやぶさ2」の持つカメラは探査機に固定されています。このため、図2の左図のように、カメラで小惑星を追い続けるというシーケンスによって、接近した点で観測を行おうとすると、探査機の姿勢ごとカメラを回転させる必要がありますが、このように素早く姿勢を変更することは「はやぶさ2」の姿勢制御能力では、現実的ではありません。そのため、図2の右図のように、小惑星への接近距離を小さくすることで、高解像度の画像を取得しようとしています。

このような接近を行うために、「はやぶさ2#」では、探査機が自律的に誘導航法を行うことを準備しています。この誘導航法とは、自身の位置を推定し、目標点に到達するための燃料噴射量を計算することを意味しています。過去に、小惑星リュウグウに接近した際には、地上に画像を送り、制御量を探査機に送り返すという運用を行っていました。しかし、今回のフライバイミッションでは小惑星への接近速度が大きいために、地上と通信し制御量を計算している時間の間に長い距離を移動し、誤差も大きくなってしまいます。そのため、探査機が自律的に制御量を計算し、燃料噴射を行うことで、誘導精度の向上を試みる予定です。この技術は,誘導精度が十分に高ければ、NASAのDARTが実証したように、小天体への衝突も可能となることから、プラネタリーディフェンスに資する技術とも言えます。このような精密なフライバイを実現できるように、現在チームで検討や準備を行っています。

私自身の研究としては、学生時代から「はやぶさ2」が小惑星に向けて投下したターゲットマーカーに着目した研究を行ってきました。このターゲットマーカーは、未知な環境である小惑星表面に対して、探査機が自律的に誘導を行うための目印です。これまでに画像を用いた誘導航法の研究を行ってきた経験や知見をもとに、2026年のフライバイにおいて、どのようにすると探査機が高い誘導精度を達成することができるのかということを他のチームメンバーとともに検討しています。加えて、自律的に精度の高い誘導航法を行えることは、ランデブーミッションにおいても、大きな利点があります。そのため、自律化の研究をより推し進めて、「はやぶさ2#」が2031年に到着予定の小惑星1999KY26への接近においても、役に立つような研究をしたいと考えています。
私は今年度から宇宙航空プロジェクト研究員に着任し、「はやぶさ2#」チームの一員として、フライバイミッションに向けた準備を行うようになりました。これまでで一番感じたことは、ミッション達成のためには、徹底した準備を行う必要があるということです。フライバイという探査自体は、本当に一瞬で終わるものですが、その一瞬のために、膨大な数の検討や作業があると感じます。フライバイ本番に向けて、本格的で大変な準備が今後待ち受けていると思いますが、一つ一つの研究・検討を丁寧に行っていきたいと思います。リュウグウにおいて成果をあげた先輩方の姿に学びつつ、私自身もフライバイの成功やその後の小惑星探査ミッションに貢献出来たらと考えています。
用語解説
- *1 フライバイ : 探査機が天体の近傍に接近し通過すること。
- *2 プラネタリーディフェンス : 天体の地球衝突から人類を守る活動。


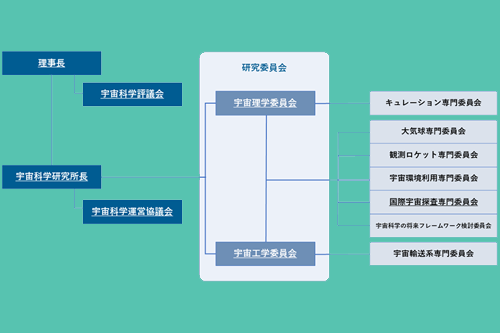

 楠本 哲也・宇宙飛翔工学研究系
楠本 哲也・宇宙飛翔工学研究系