南極周回大気球を用いたダークマター探索
2025年1月28日 | 宇宙航空プロジェクト研究員, あいさすpeople
研究概要

私は、宇宙の最も根源的な謎の一つである「ダークマター」の正体を解明することを目指し、南極上空を周回する大気球を利用するGAPS(General Antiparticle Spectrometer)実験に参加し、研究を行っています。宇宙を構成する物質のうち、光学観測ができる普通の物質はわずか約5%にすぎません。それに対して、約27%はダークマターが占めているとされています。この見えない物質の存在は、天文現象を通じて間接的に示されていますが、その正体についてはまだ明らかになっていません。GAPS実験は、反陽子や反重陽子などの稀少な反粒子の検出を通じて、ダークマターの崩壊や対消滅の痕跡を捉えることを目的としています。

GAPS実験は、反粒子を検出するための新しい手法を採用しています。従来の検出器は主に磁場を用いた粒子の曲率による粒子識別に頼っていましたが、GAPSは「エキゾチック原子法」という独自のアプローチを取ります。この方法では、粒子がシリコン(Si)半導体検出器内で止まり、Si原子との反応を通じて生成される特徴的なX線やハドロン*1を観測することで、粒子種の種類を特定します。
また、検出器を上空約36 kmを飛行する大気球に搭載することで、大気の影響を小さくした観測ができます。さらに、南極の白夜期間には南極を周回する気流が存在し、国境のない南極大陸上空を飛び続けられるため、長期間の観測が可能となります。また、極域では地磁気の影響が小さく、荷電粒子を効率的に観測できます。私は、JAXA/ISASに所属してからの半年程度で、米国内での検出器の構築や地上でのオペレーション、準備段階で取得したデータの解析を行ってきました。執筆現在、2024年度末の観測実施に向けて、南極氷上にて最終準備を進めています。私は、Si検出器の冷却系を主に担当し構築や運用を行っています。また、地上での試験データを解析し、検出器の健全性確認なども進めています。今後、南極周回フライトを実現して観測データを取得し、解析を進めてダークマターの正体解明を目指します。
用語解説
- *1 ハドロン : 陽子やパイ中間子といったクォークから構成される複合粒子の総称である。


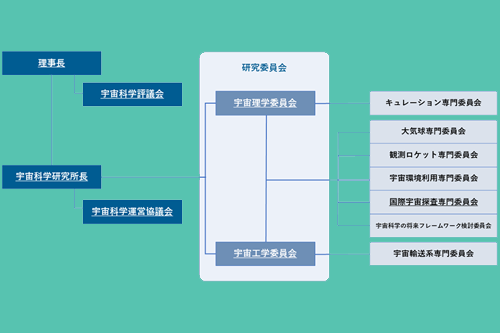

 青山 一天・学際科学研究系
青山 一天・学際科学研究系