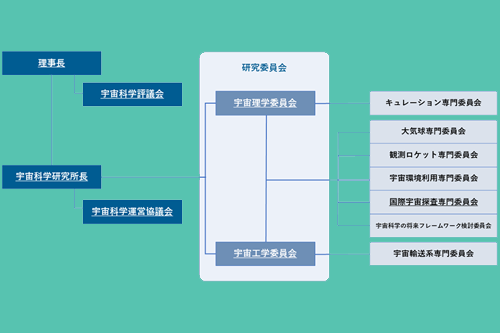第25回 宇宙科学シンポジウムを取材しました!~8月1日(金)実施の「ポスター展・ブース展」を一部ご紹介~
2025年9月29日 | あいさすpeople
2025年7月31日(木)と8月1日(金)の2日間、JAXA相模原キャンパスにて第25回宇宙科学シンポジウムが開催されました。今年度の宇宙科学シンポジウムは、「全ての世代が楽しみつつ次世代の宇宙科学を模索できるシンポジウムへ」というコンセプトのもと、従来のプログラム編成方針から大幅に刷新されました。(当日のプログラム等についてはこちら)





写真右:企画チームを率いる吉田哲也先生。

今回、「あいさすGATE」では、シンポジウム開催前の企画チームによる座談会*1において、特に目玉とされていた2日目の「ポスター展・ブース展」を取材しました。ブース展の展示物や出展者の声を中心に、当日の様子を一部お届けします!
今年度は、3テーマ「うごかす・とめる」「はかる・かんがえる・つたえる」「はやい・やすい・よい」について、ブース展が設けられました。(ブース出展情報はこちら)
ブース展「うごかす・とめる」
このテーマでは、その名のとおり様々な動きをする展示やデモが行われており、にぎわっていました。
■テーマ:折り紙・展開構造・機械的メタマテリアル
(代表者:安田 博実/JAXA 宇宙科学研究所宇宙飛翔工学研究系)
様々な素材や形状の構造物が展示されていました。会場では、説明を聞きながら実際に展示物に触れ、折って畳んだり、力を加えたりして、様々な材料や構造について体感しながら学ぶことができました。宇宙分野はもちろんのこと、私たちの身の回りへの応用についても想像が膨らみます。


■テーマ:トランスフォーマー(ロボット)
(代表者:久保 勇貴/神戸大学)
2つの足で立つ人型のドローンが展示されていました。4つのプロペラの推力と足の関節の角度を制御して、空中で安定化することが可能な設計になっているそうです。他にも、宇宙空間で宇宙機が形を変えながら、同時に軌道や姿勢を制御するための研究等についても説明していただきました。

■テーマ:ドラムロボ・人工筋肉
(代表者:奥井 学/中央大学理工学部)
軽快にドラムをたたく人工筋肉のロボットが展示されていました。シミュレーション環境で何度も強化学習を行った後、実際に学習した動きを人工筋肉の手が演奏するそうです。ブースでは、ダブルストロークという1回の振り下ろしで2回ドラムを叩くテクニックを披露していました。この技は柔らかく握りの強さを変える必要があるため、機械には難しい動きだそうです。

宇宙科学シンポジウムには、学生さんも大勢参加していました。そこで、「ドラムロボ・人工筋肉」のブースで展示をしていた山口 和真さん(中央大学 奥井研究室/学部4年生)に、今回の宇宙科学シンポジウムの感想を伺いました。

宇宙科学シンポジウムは初参加ですが、今まで他の研究者の成果を実物で見ることができる機会はなかなかなかったので、面白かったです。
私は、望遠鏡の筒の部分を螺旋状に分解させて布のようにコンパクトに収納した状態で打上げた後、自走式ジッパーで閉じる「螺旋分割型展開式バッフル」の開発をしているのですが、すぐ隣の「折り紙・展開構造・機械的メタマテリアル」のブースは、自分の研究と近い部分もあるので、将来的に何かに使えそうだなと思いながら興味深く見学しました。
ブース展「はかる・かんがえる・つたえる」
このテーマでは、未来の宇宙探査におけるデータ通信や新しい測定技術などが展示されていました。
■テーマ:AI On Board Computer
(代表者:松田 昇也/金沢大学理工研究域)
このブースには、2027年に打上予定の衛星に搭載予定のAI-OBCに関する展示(写真左)等がありました。また、AI-OBCが未来の惑星探査でより適切な着陸地点をリアルタイムで決定するような研究等についてにも触れることができました。


■テーマ:微惑星・小天体・太陽系物質科学
(代表者:深井 稜汰/JAXA 宇宙科学研究所太陽系科学研究系)
グローブボックス(写真左)の中で天体から採取した試料を取り分ける作業を模擬体験できる設備が展示されていました。取材班も、専用の大きくて長いグローブを装着し、特殊なピンセットを用いて、針の先ほどの大きさの粒子を専用の容器に移す作業に挑戦しました(写真右)。粒子を1つ拾い上げるのもなかなか難しく、繊細な作業でした。実際にキュレーションセンターで扱うのは天体から採取した本物の試料なので、慎重に扱わなければならないという緊張感もプラスされます。キュレーションがいかに集中力と根気が必要な仕事であるかを実感できました。


■テーマ:量子光学測定
(代表者:和泉 究/JAXA 宇宙科学研究所宇宙物理学研究系)
重力波を観測するための重力波レーザー干渉計の観測感度を上げるための研究等について、説明をしていただきました。レーザーで測距する際に問題となる量子揺らぎや測定する際の技術等について、研究者ではない取材班にも分かりやすく、かみ砕いて解説してくださいました。

このブースには、2025年7月に宇宙科学研究所(宇宙研)に着任された榎本 雄太郎先生(宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系/助教)も出展されていたので、宇宙科学シンポジウムの感想を伺いました。

宇宙科学シンポジウムは今回が初めての参加ですが、とても楽しいです。他の分野の方から色々な話が聞くことができて、特別公開に行った時のような子どもの頃の気持ちを思い出します。
「微惑星・小天体・太陽系物質科学」のブースのキュレーションの方々と話をしたのですが、それぞれが興味を持っている領域に接点も見つかったりして、面白いなと思いました。
私は宇宙研に来て間もないので、色々な方とお互いの専門の話をしながら知り合いになれるよい機会にもなりました。
ブース展「はやい・やすい・よい」
このテーマでは、宇宙探査の領域をより効率よく開拓していくために活かされる、新しい技術やアイディアが展示されていました。
■テーマ:超薄型太陽電池・薄膜デバイス
(代表者:甚野 裕明/JAXA 宇宙科学研究所宇宙機応用工学研究系)
超薄型のペロブスカイト太陽電池で駆動するプロペラ(写真左)や、ペロブスカイトナノ粒子を使ったシンチレータについての研究(写真右)等が展示されていました。1~3マイクロメートル(サランラップの10分の1)ほどの薄さのデバイス等を直接見ることができ、未来の技術を感じることができるブースでした。


■テーマ:宇宙ロボット・分散探索ロボット
(代表者:國井 康晴/中央大学理工学部)
「はやい・やすい・よい」の中でひときわ賑わっていたのが、このブース。複数台のロボットで探査を行う小型探査ロボットRED(写真左)や、勢いよくジャンプして移動する球体の月探査ロボット「まいど2号」(写真右)が展示されていました。「まいど2号」は実際にジャンプする様子を見ることができました。


■テーマ:宇宙探査における惑星保護と汚染管理
(代表者:木村 駿太/JAXA 宇宙科学研究所学際科学研究系)
こちらのブースでは、展示資料や将来の火星探査の着陸機のモデル(写真左:展開型柔軟エアロシェル)を活用しながら、他天体を探査する際に地球由来の微生物を持ち込まないための国際的な基準や検査方法(写真右:火星に着陸する機器を拭き取り、付着した微生物等を検査する際の道具)等について、説明していただきました。


「宇宙探査における惑星保護と汚染管理」ブースの出展者、木村駿太先生に、今回のシンポジウムに出展された感想を伺いました。

過去の宇宙科学シンポジウムの参加経験もありますが、今回は雰囲気が全く違いますね。開催時期も1月から7・8月に変わって参加しやすくなったように思いますし、JAXA内外の色々な人と交流ができるので、とてもよい場だと感じています。ポスター展に出展した学生さんからも、他大学の先生が話を聞いてくれてよいアドバイスを貰えたと報告があったので、よかったです。
リニューアルしたことで運営側は相当大変だったと思いますが、シンポジウムは大成功だと思います。今後は、ただ盛り上がってよかっただけで終わらないよう、開催目的に掲げている理工のマッチングが結果としてどれくらい達成できたか等を何かしらの形でまとめて可視化していけると、本当の意味での趣旨も満たせるように思いました。
ポスター展の様子
ポスター展は、3つのテーマ(テーマ1.理学が考える「こんな技術があれば実現できるサイエンス」、テーマ2.工学が考える「サイエンスに応用できるかもしれない技術」、テーマ3.プロジェクトの進捗・成果の共有)で構成されています。ポスター展は混雑を避けるためにテーマ別で午前・午後それぞれに1時間のコアタイムが設定され、確実にポスター発表者に質問・議論ができるよう配慮されていました。
今回の取材では、テーマ3.に出展していた火星衛星探査計画 MMXのプロジェクトチームにお話を伺いました。


火星衛星探査計画 MMXは、2026年度の打上げを目指して開発が進められている、世界初の火星衛星サンプルリターンミッションです。2026年度に打ち上げられた後、2027年度に火星衛星の擬周回軌道*2に突入して火星衛星観測とサンプル採取を行い、2031年度の地球帰還を計画しています。
MMXプロジェクトチームは、今回の宇宙科学シンポジウムが「プロ向けの特別公開」と打ち出されている点に着目して、宇宙のプロも楽しめるようにマニアックな構成でポスターを作成されたそうです。通常の特別公開等ではミッション概要の発表までに留まる場合が多いところ、ミッションの進め方の工夫や高度な表面探査の技術等、細かい内容までポスターに盛り込まれていました。
また今回の取材中、ポスター展や会場の談話スペースではいくつものグループができ、活発に会話が繰り広げられていました。

最後に、第25回宇宙科学シンポジウム企画チームからのコメントを紹介します!

吉田 哲也先生(宇宙科学研究所 研究総主幹 学際科学研究系/教授)
宇宙科学シンポジウムの開催が研究者の発表の練習の場になればと思います。また、企画チームの若手メンバがこの規模感のマネジメントの経験を積むことは、将来宇宙研を動かす次のリーダを見つけていくためのステップとして今後役立つと考えます。

河原 創先生(宇宙科学研究所 宇宙物理学研究系/准教授)
初回ということでギリギリ(セーフ)なことが多かった気がしますが、次回以降はもっと余裕が出るように運営していけるといいとおもいます。想像してたより多種多様な参加者がいたようでびっくりです。

中島 晋太郎先生(宇宙科学研究所 学際科学研究系/准教授)
企画チームの一員として、楽しみながら準備から当日まで走りぬくことができました。特に2日目は色々なところで議論をしている参加者の姿を見ることができました。「次回以降もこの形を続けてほしい」と思っていただけたなら第一回目としては良かったかなと考えます。

小田切 公秀先生(宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系/准教授)
ブース、ポスターの前で味わい深そうに、時間を気にせずじっくり議論する姿や、初見であろう装置や研究内容を前に楽しそうに会話する姿が印象的でした。とても賑やなシンポジウムにしてくださった参加者の皆さん、一緒に企画チームとして走ってくださった皆さん本当にありがとうございました!

甚野 裕明先生(宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系/助教)
私は、ブース出展者・企画チームの両方から関わらせていただきました。異なる角度から、「新しくなった宇宙科学シンポジウム」の醍醐味を堪能することができたと感じています。熱気あふれる企画チームの一員として働くことができ、光栄でした!

第25回宇宙科学シンポジウムの取材レポートは、いかがでしたか? ISASニュース(2025年8月号)では、企画チームメンバの記事が掲載されておりますので、あわせてご一読ください!