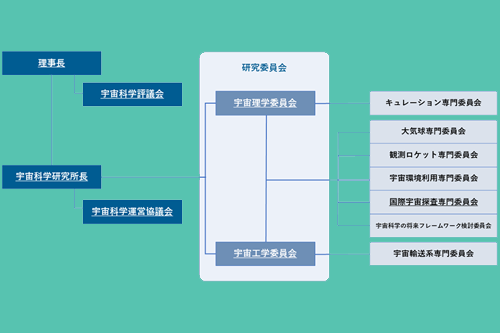挑戦したからこそ得られた貴重な経験の数々!
10週間にわたるヒューストンでのインターン
~Lunar and Planetary Institute(LPI)主催、Exploration Science Summer Intern Program参加インタビュー:杉本佳祈氏~
2024年10月31日 | あいさすpeople

杉本佳祈さん(東京大学 大学院理学系研究科地球惑星科学専攻/修士課程2年)が2024年5月28日から8月2日までの10週間、Lunar and Planetary Institute(LPI)がNASAと共同で主催する「Exploration Science Summer Intern Program」に参加しました。このプログラムは、それまでの月面着陸候補地点の評価等を目的としたインターンプログラム(Lunar Exploration Summer Intern Program)を踏襲し、将来の探査活動につながる研究活動を行うために計画され、地質学や惑星科学などを専門とする大学院生向けに実施されています。2024年のプログラムでは、世界中の応募者の中から杉本さんを含む10名が選抜され、米国テキサス州ヒューストンにあるLPIにて、NASA主導の月面探査プログラム「アルテミス計画」についての研究活動が行われました。選ばれた学生たちには、プログラム期間中の滞在費用や旅費が支給されます。
本インタビューでは、杉本さんのインターンでの研究活動や生活の様子をお伺いました!
現在の杉本さんの研究テーマと、インターンに参加した経緯を教えてください。
私の人生の目標は「人類の火星移住」です。その目標に向けて、人類が生きていくために欠かせない「水」に着目し、火星の地形等から火星の水の進化史を解明する研究をしています。大学の学部生の頃、JAXAの研究者の講義で「火星移住に向けて検討している」という話を聞いたことをきっかけに、火星や有人探査に興味を持つようになり、今の道に進みました。
今回のインターンについては、所属する研究室の臼井寛裕先生(宇宙科学研究所 太陽系科学研究系/教授)が紹介してくれました。研究内容には、アルテミス計画における月の着陸地点の選定についての記載がありました。私の最終目標である火星への移住においても、着陸地点の選定は不可欠です。人類の地球以外の惑星への着陸には、第1ステップとして月があり、その次のステップとして火星があると思うので、自分の研究のモチベーションと合致していると考え、応募を決めました。
実際にインターンへの参加が決まったときは、一瞬時間が止まったくらい、とても驚きました!参加したい思いはすごく強かったので、徐々に嬉しさを実感しました。臼井先生にも参加の報告をしたところ、競争率が非常に高いとのことで、大変驚かれていました。

インターンの全体像を教えてください。
インターン生は国際色豊かで、フランス人、イタリア人、韓国人、ドイツ人、インド人が2人、アメリカ人3人、そして日本人である私の10人で、LPIから車で数分のところにあるアパートで共同生活をしながら、平日9時から17時までLPIで研究課題に取り組みました。参加者の中では私が最小学年でした。
今回の研究課題は、NASAがアルテミスⅢで宇宙飛行士が月面着陸をする候補地点として選定している13箇所の中から、与えられた検討条件に対して最も適切な着陸地点を1つ見つけるというものでした。私たちは理学グループと工学グループに5名ずつ割り振られ、2つのグループに異なる検討条件が与えられました。今回のプログラムではLPIの教授が1名、指導教官として付いてくれました。インターン生は全員が一緒に作業ができるワーキングスペースで研究に取り組むのですが、毎日午後に教授がそこに来て、研究のサポートやアドバイスをしてくれました。毎週金曜日には、グループ単位でその週の研究成果を発表して、教授からフィードバックを受けました。
インターンの期間は10週間でしたが、教授から提示されたスケジュールは、最初の5週間で研究を行い、残りの5週間はレポート作成に費やすというものでした。研究を5週間という短い期間で仕上げなければならなかったのは、正直とても大変でした。インターン最終日の前日には、研究結果の発表もありました。
研究活動が中心でしたが、プログラムにはNASAのジョンソン宇宙センターへのツアーやセミナーなど、惑星科学等の知見を深める機会も多数用意されていました。ジョンソン宇宙センターのツアーでは、無重力環境の訓練施設で実際に宇宙飛行士が訓練をしている場面も特別に見学させていただきました。ジョンソン宇宙センターはLPIから車で10分ほどの場所にあり、私たちのアパートからも近かったので、土日にもインターンのメンバーと観光に行きました。全体を通して、非常に充実したプログラムだったと思います。
盛りだくさんのスケジュールですね!杉本さんのグループの研究について教えてください。
私は理学グループとして、「宇宙飛行士が最もアクセスしやすい、1番年代が古くて温度の低い永久影を見つける」という検討条件で研究しました。永久影とは、月の北極や南極にあるクレーターの内部等の周囲よりも標高の低い場所にある長い時間日の当たらない領域のことで、温度110 Kを下回っています。これは月で水が安定して存在し続けられる温度で、永久影には水が存在している可能性があります。13箇所の着陸候補地点はすべて月の南極付近に位置しています。

私たちは永久影の「温度」と「年代」の2つを個別に検討しました。温度については比較的順調に進みました。月にも季節があるのですが、夏の1番気温の高い時期に1番温度の低い領域は、冬でも同様に温度の低い領域となるため、月を周回している探査機からのデータを活用し、月の南極の1番気温が高い時期のデータの中で1番温度の低い領域にある永久影を選ぶ方向で進めました。
一方で、年代については議論をする内容が多く、なかなか難しかったです。例えば、クレーターの内部にある永久影は必ずクレーターができた後に生じるため、永久影はクレーターができた年代より若いはずです。なのでクレーターの形成された年代を永久影の年代の上限値(これより古くなるこことはないという値)として絞り込む方向で進めようと決まりました。地形は形成されてから時間の経過とともに劣化してその形を変えていくため、劣化により“クレーターの形が変わる”ということに着目して年代を求めました。しかし、答えを出すために何に注意して考えなければいけないかという点で、議論がありました。例えばクレーターが平面にできたか斜面にできたかでその崩れ方違うことが挙げられます。また、クレーターの近くで隕石などの衝突が起きると、衝突により飛散した物質が既存のクレーターに入り込み、劣化とは無関係にクレーターの形が変わるため、年代推定を複雑にしてしまうことなど、注意すべき点がいくつも挙がりました。過去の研究や論文等を参考にしながら熱心に取り組みましたが、私たち学生だけでは知識が及ばない部分もあり、悩むことが多かったです。困ったときは教授にも相談して、考える内容を絞りつつ、みんなで協力して進めました。
私たちのグループは分担して調査を進めたので、最後の研究結果も担当した部分について発表しました。先ほど、永久影の年代の上限値を決めるためにクレーターが形成された年代を求めることについて話しましたが、私は月のクレーター周りにある「ボルダー」という小さな岩塊の分布から、永久影の年代の下限値(これより若くなることはないという値)を推定するところを担当しました。発表をする上では、ボルダーとは何か、なぜボルダーについて考える必要があるかなど、工学専門の方々にも伝わるように意識してスライドを作成して、発表練習も重ねて臨みました。発表後は、教授からも褒めていただけて、嬉しかったです。
グループ全員でたくさんの話し合いが行われたのですね。工学グループの発表はいかがでしたか?
率直に「宇宙工学ってこういう研究をしているんだ!」という感想を持ちました。私はずっと理学の人間で、そもそも工学の研究がどのようなものかを知る機会があまりなかったので、とても興味深かったです。工学グループのテーマは、「宇宙飛行士が月面着陸するにあたって、最も危険性が低い候補地点を見つける」というものでした。発表の中では、危険が及ぶ時間スケールについて慎重に考えていたのが印象的でした。例えば、割と短い時間軸で起きる地すべりと滅多に発生しない地震では時間スケールが大きく異なるし、設定する時間スケールによっても危険な場所は変わるといった内容でした。工学の研究にも触れることができたことで、もっと理学と工学を交えた場を作りたいと思うきっかけになりました!
研究活動以外に、何か印象に残った出来事はありましたか?
本当に色々なことがありましたが、特に嬉しいハプニングが1つありました。ヒューストンには、有人宇宙活動に力を入れているJAXAヒューストン駐在員事務所があるのですが、そこでインターンでの研究結果を発表しました!インターンに行く前に、臼井先生よりLPIのインターンシップに参加されていた筑波の職員をご紹介いただきました。その方がさらにヒューストン駐在員をご紹介してくださり、その縁で今回発表する機会をいただきました。発表後には、参加者からの意見も交えて議論が展開され、有人宇宙活動の観点から現場の意見もお伺いすることができたので、とても充実した時間となりました。人と人との繋がりで得た機会に感謝しています。
インターンが終了した時は、どのような気持ちでしたか?

正直なところ、行っている期間の99%は辛いと感じていました。実は、海外に1人で行くのも、英語だけの環境で研究をするのも、同世代の研究者と議論をしながらグループワークで研究に取り組むのも、全て今回が初めてでした。特に最初は英語に苦戦して、議論の内容を理解して自分の意見を話すまでに、次の話題に進んでしまっていたこともありました。
でも、日本に戻る頃には、寂しい気持ちでいっぱいでした。英語で苦しんだとはいえ、同時にすごく良い経験をしているという実感もありました。もっと英語に浸かっていたかったという気持ちが強くて、「日本に帰ったら、私の中から英語が抜けてしまう!」と思って、すごく名残惜しかったです。日本に戻ってからは、英語が抜けないように独り言を英語で話すようにしていたほどで、研究室の方からは「アメリカンになってるね!」と言われました(笑)
インターンに参加したことで、何か変化はありましたか?
私の人生のゴールである「火星移住」の部分をもっと意識してどんどん実績を積み上げたいという思いや、有人探査に関わる仕事をしたいという思いが、より一層強くなりました。今回のインターンで得た知識の中には、今の私の研究に適用できるものもあり、自分の中の引き出しを増やすこともできたので、この経験をうまく次につなげていきたいです。
また、宇宙業界にとって国際交流が重要であることも改めて実感しました。同じ研究室に海外で活躍中の先輩もいるので、私もまた海外へ行けたらなと思っています。
もし同じような機会を前に、参加を悩んでいる後輩がいたらどうしますか?
「迷っているなら、やってみて!」と背中を押します。私自身、参加をしたくて申し込んだものの、本当に通るとは思っていませんでした。でも、実際には参加できて、たくさんのことを経験し学ぶことできました。今回のインターンに挑戦しなければ得ることができなかったことばかりだったと思います。たとえ応募して選考に通らなくても、申請をする際の書類を作成するスキル等は自分の経験値になるので決して無駄にはなりません。挑戦しなければ失敗すらできないし、何も始まりません。とにかくやってみることが大事だと思います!
本日は、貴重なお話をありがとうございました。インターンを経て大きく成長された杉本さんの益々のご活躍を楽しみにしています!
なお、杉本さんたちの研究成果は、2025年3月に開催されるLunar and Planetary Science Conference(LPSC)にて公表を予定しています。