気象衛星ひまわり8号・9号は宇宙望遠鏡になりうる!?
~金星大気温度の長期変動の観測に成功~
2025年7月2日 | 論文へのGATEWAY
日本で暮らしている誰もが一度は、気象衛星ひまわり8号・9号の画像を見たことがあるのではないでしょうか?日本の気象衛星ひまわり8号・9号はそれぞれ2014年と2016年に打ち上げられ、2015年夏の運用開始以来、我々の日々の暮らしの天気予報に欠かせない地球の画像を、様々な波長で宇宙空間から10分に一度という高頻度で撮影しています。実はこの気象衛星観測では地球の外側の宇宙空間も同時に撮像されており、気象画像の中には月をはじめとした太陽系天体が稀に写り込むことがあります。本研究ではそんな気象衛星画像を惑星科学、特に金星の研究にも活用したところ、金星大気の温度の長期変動の異なる高度での同時観測に初めて成功しました。
金星は非常に厚い大気を持ち、金星の自転速度の約60倍もの速さで大気が回転する「スーパーローテーション」という現象が特徴的です。その風速には数年スケールでの長期変動が観測されてきた一方、スーパーローテーションの駆動メカニズムに密接に関わるとされる大気波動の温度構造の長期変動は未解明なままでした。本研究では、複数の赤外バンドを用いた観測から異なる高度帯での温度変動を観測し、大気波動の鉛直構造も含めた時間変化を明らかにしました。将来的にはこの成果を金星大気循環モデルと比較することで、未解明な金星大気の長期変動の要因を特定できると考えられます。本研究で得られた観測結果は他の惑星探査機に搭載された機器の較正にも用いられるなど、金星大気の研究を発展させるだけでなく、今後の惑星探査にも幅広く貢献できると期待されます。
研究概要

金星の特徴の一つは、自転の約60倍もの速さで大気が回転するスーパーローテーションと呼ばれる現象であり、その風速は数年単位での長期変動を示すことが観測されてきました。太陽加熱に起因する熱潮汐波*1や、ロスビー波*2などの惑星スケール*3の波動構造がスーパーローテーションの維持機構として密接に関わっていると考えられていますが、熱潮汐波やロスビー波の波動構造も長期変動を示すのでしょうか?これらは金星大気の変動とその物理を理解する上で重要な情報ですが、この物理を解明するには長期間にわたる金星大気温度のモニタリングが必要です。しかし、これまで10年を超える金星のモニタリング観測が行われた探査はなく、他の手立てでの宇宙空間からの金星温度観測が必要でした。
そこで本研究では新たな観測手法として、気象衛星ひまわり8号・9号*4の地球観測時に写り込む金星像に着目しました。気象衛星ひまわり8号・9号は10分に1回の頻度で地球の観測を行いますが、地球の周囲の宇宙空間も同時に撮像されており、この宇宙空間に月などの太陽系天体が写り込むことがあります(図1)。金星も例外ではなく、現在までの全画像を調査したところ、2015年7月から2025年2月までの間に437回も撮像されていました。

本研究ではこの稀に得られる金星の赤外画像を用いることで、金星大気の輝度温度*5の長期変動を検出することに成功しました(図2)。特に複数の赤外バンドを用いることで、波長ごとの光学的厚さ*6の違いから異なる高度での温度の時間変動が初めて明らかになりました。更に解析を進めると、この時間変動が熱潮汐波のパターンの時間変化を示すことが明らかになりました。加えてロスビー波の温度振幅の高度依存性とその時間変化も初めて解明することに成功しました(図3)。今後、金星大気循環モデルと比較を進めることで、未だに解明されていない金星大気の長期変動の要因が明らかになり、地球と比べて極めて厚い大気での物理現象の理解が進むと期待されます。

また本研究では理学的成果のみならず、他の探査機の機器較正への活用も行われました。気象衛星ひまわり8号・9号での観測期間の間、金星は日本の金星探査機「あかつき」に搭載された中間赤外カメラLIR*7と国際水星探査計画「BepiColombo」に搭載された赤外分光計MERTIS*8による観測がなされています。この3機器による金星の同時観測データを用いて機器間の定量的比較を行い、特にLIRによる観測輝度温度の較正に向けて新たな定量的な指標が得られました。
このような気象衛星の活用は、気象衛星ひまわり8号・9号のみならず他国の気象衛星を用いても実行可能であり、金星大気温度モニタリングの新たな観測手法が確立されたと言えます。特に金星探査機「あかつき」との通信が途絶えている今、次の金星探査の機会までは唯一の宇宙空間からの赤外波長帯での金星観測となる可能性があります。本研究で開発された手法は今後も金星大気の長期変動を明らかにする貴重な観測データを提供し、金星大気の研究の発展のみならず、他の惑星研究・探査にも幅広く寄与し続けていくと期待されます。
用語解説
- *1 熱潮汐波:太陽光が金星の雲層で吸収されることで大気が加熱され、雲層から上下に伝搬する重力波。金星大気のように安定成層している(冷たい下層の上を暖かい上層が覆っている)場合、暖められた空気は上昇しても周囲よりも高密度のため復元力が生じ、その結果同じ高度で空気が振動してできる波を重力波と呼ぶ。天体物理学でいうところの重力波とは違い、惑星大気中に生じる波動である。
- *2 ロスビー波:惑星の自転によるコリオリ力が緯度によって異なることで生じる惑星規模の波。地球と異なり金星では東向きに伝搬する。地球のような回転体上で物体が移動する際、進行方向に対して垂直な方向に生じる見かけの力(慣性力)をコリオリ力と呼ぶ。
- *3 惑星スケール:大気大循環などのように、惑星全体にわたって生じる気象現象や大気の動きの規模を指す。
- *4 気象衛星ひまわり8号・9号:日本及び東アジア、西太平洋領域を撮像している日本の静止気象衛星で、天気予報のみならず、台風や集中豪雨、気候変動の監視などに貢献している。ひまわり8号はひまわり7号の後継として2014年に打ち上げられ、2015年夏より運用が開始された。ひまわり9号は2016年に打ち上げられ、バックアップとして待機後、2022年12月にひまわり8号とバックアップの役割を交換する形で運用が開始された。
- *5 輝度温度:ある波長で観測される放射輝度を黒体輻射によって説明しようとしたとき、必要とされる黒体の温度。ある方向に放射される電磁波のエネルギーを、単位面積・単位立体角あたりで表したものを放射輝度と呼ぶ。
- *6 光学的厚さ:ある波長の電磁波が物質を透過する際に、物質の吸収による減衰を決める量。雲層における電磁波強度の減衰の波長依存性のため、異なる波長のバンドを用いることで雲層内の異なる高度の温度情報をみることができる。
- *7 LIR:金星探査機「あかつき」に搭載された赤外放射計Longwave Infrared Cameraの略。
- *8 MERTIS:水星探査機「BepiColombo」に搭載された赤外放射分光計Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometerの略。
論文情報
| 雑誌名 | Earth, Planets and Space |
|---|---|
| 論文タイトル | Temporal variation in the cloud-top temperature of Venus revealed by meteorological satellites |
| DOI | https://doi.org/10.1186/s40623-025-02223-8 |
| 発行日 | 30 June 2025 |
| 著者 | Gaku Nishiyama, Yudai Suzuki, Shinsuke Uno, Shohei Aoki, Tatsuro Iwanaka, Takeshi Imamura, Yuka Fujii, Thomas G. Müller, Makoto Taguchi, Toru Kouyama, Océane Barraud, Mario D'Amore, Jörn Helbert, Solmaz Adeli, Harald Hiesinger |
| ISAS or JAXA所属者 |
鈴木 雄大(宇宙科学研究所 太陽系科学研究系 日本学術振興会特別研究員(PD)) |
関連リンク
- 東京大学大学院理学系研究科プレスリリース「金星大気温度の長期変動の観測に成功―気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用―」2025年6月30日
- 東京大学大学院新領域創成科学研究科プレスリリース「金星大気温度の長期変動の観測に成功―気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用―」2025年7月1日
- 国立天文台プレスリリース「金星大気温度の長期変動の観測に成功―気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用―」2025年7月1日
- 立教大学プレスリリース「金星大気温度の長期変動の観測に成功―気象衛星ひまわり8・9号の宇宙望遠鏡的活用―」2025年7月1日
執筆者
ISAS共著者からひとこと(鈴木 雄大)
現在ドイツ航空宇宙センター(DLR)で研究されている西山さんは、月や小惑星の表層・内部を主軸として研究されてきた一方で、常に幅広い視野を持って精力的に研究されており、様々な惑星探査ミッションでご活躍されています。皆様の生活にもお馴染みの気象衛星ひまわりは地球を観測していますが、稀に視野に金星等の他天体が写り込んでいます。本研究ではこの写り込んだ金星に着目し、世界で初めて複数波長の赤外線による金星の長期観測データを取得しました。JAXAではこれまでに多くの探査機を打ち上げてきましたが、やはり数には限界があります。本研究は金星の複数高度における温度の長期変動を示したというだけでも価値のある研究ですが、既存の、しかも本来惑星観測を目的としていない衛星の惑星科学への応用可能性を示したという点でも非常に重要な成果です。金星探査機あかつきや水星探査機BepiColomboといった現在運用中の探査機の機器較正にも寄与した本研究は、今後の惑星の赤外観測データの質の向上にも貢献したと言えるでしょう。


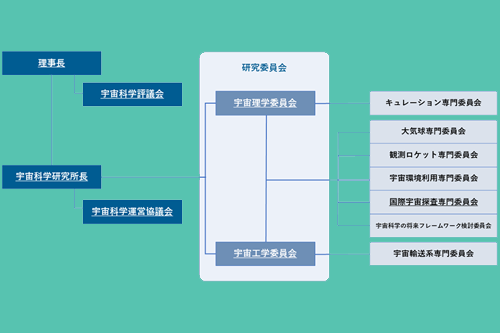

 西山 学・ドイツ航空宇宙センター(DLR)/
西山 学・ドイツ航空宇宙センター(DLR)/ 
