TOP > レポート&コラム > 宇宙科学の最前線 > 「あかり」衛星で探る星間塵の一生
![]()
| │1│2│3│ |
今回、我々は2006年10月にアマチュア天文家板垣公一さんが発見した超新星2006jcを、爆発の約半年後に赤外線天文衛星「あかり」で観測しました。国立天文台の「すばる」望遠鏡や広島大学の「かなた」望遠鏡を用いて超新星爆発以降継続的に行われた可視光の観測からは、超新星が爆発後2ヶ月を境に暗くなり、半年後には「すばる」望遠鏡でもやっと観測できる程度にまで暗くなる様子がとらえられました。一方、「あかり」の観測では、爆発の半年後に赤外線で明るく光を放つ超新星の姿がとらえられました。この観測結果は、超新星周囲にできた塵が明るく熱放射を行っていることを示し、超新星周囲における塵誕生の瞬間をとらえたものといえます。
「あかり」による近・中間赤外線測光データと近赤外線分光データ、東京大学のMAGNUM望遠鏡による同時期の近赤外線測光データを用いて、より詳細に塵の放つ赤外線放射の性質を調べたところ、近赤外域の熱放射を担う約500℃の炭素質の塵(高温成分)に加えて、中間赤外域の超過を担う約50℃の炭素質の塵(低温成分)の2成分が存在することが分かりました。塵の形成にかかわる理論計算との比較研究から、高温成分は超新星爆発に伴う放出ガスをもとに新たに誕生した塵であり、低温成分は超新星爆発以前に放出された物質によって形成され、超新星爆発を起こす前の親星を遠巻きに覆っていた既存の塵だろうという結論に至りました。同時に、これらの観測結果と最新の恒星進化モデルとの比較から、超新星2006jcの親星は誕生当初、太陽の40倍程度の質量を持った大質量星で、激しい質量放出を経て超新星爆発時点では太陽の7倍程度の質量になっていたことが分かりました。
このように、数百万年にも及ぶ星の進化の末のわずか半年間という一瞬の出来事を「あかり」が幸運にもとらえ、星間塵の誕生と大質量星の進化の描像にかかわる重要な情報を我々にもたらしてくれました。一方、こうした描像が大質量星の進化に普遍的なものであるのかどうかは、現時点ではまだ定かではありません。しかしながら、少なくとも本研究の結果は、太陽の数十倍の質量を持つ大質量星が、超新星爆発の際だけでなく、その前の一生の進化過程を通じて星間塵の形成に寄与し得る、という重要な示唆を与えてくれたといえます。
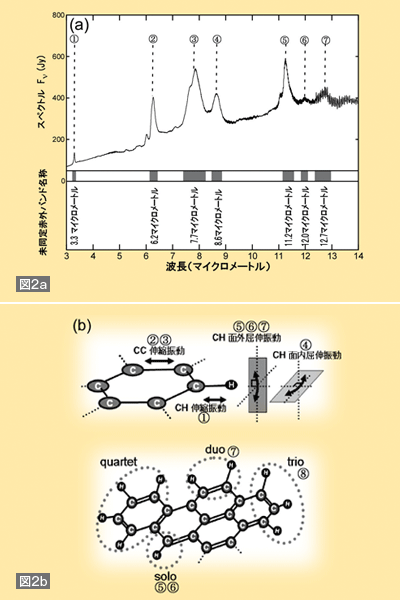
|
| │1│2│3│ |
