![]()
気球の開発
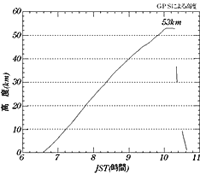
図1 : 高度53 kmに達したBU60-1号機の高度曲線
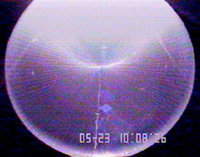
図2: 高度53 kmで満膨張になったBU60-1号機

図3: スーパープレッシャー気球の体育館での加圧膨張試験
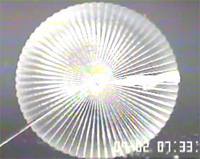
図4: スーパープレッシャー気球の気球環境での膨張試験

図5: 水蒸気を浮揚ガスとした金星気球モデル
気球実験の可能性を広げる、新しい気球の開発を行なっています。特に、飛翔高度を向上させる薄膜型高高度気球の開発、および、長時間の飛翔を可能にするスーパープレッシャー気球の開発に力を入れてきました。
薄膜型高高度気球の開発
薄膜型高高度気球は、気球に使うフィルムを薄くして気球自体を軽くした、高くまであがる気球です。搭載重量は数kgです。2003年には高度53 kmまで到達し、世界最高気球到達高度を30年ぶりに塗り変えました(図1、図2)。その後も、気球用フィルムを薄くする研究を進めており、2.8マイクロメートルの厚みのフィルムを開発し、これを使った気球で高度記録の更新を目指しています。
スーパープレッシャー気球の開発
スーパープレッシャー気球は、気球を長時間にわたって飛びつづけられる気球です。通常使われている気球は、ゼロプレッシャー気球と呼ばれるもので、気球の下部に排気口がついており、気球ガスの圧力と飛翔している大気の圧力が等しくなっています。この気球の場合、日が沈むと気球のガスの温度が下がってしぼんでしまうため、浮力を失い気球は降下してしまいます。これは、浮力が気球の体積に比例しているためです。このため、日没になると気球につんだバラストと呼ばれる砂を投下して軽くすることで、降下を防ぐのですが。気球が飛び続けるには、このバラストを毎晩、落とさなければならず、最初に積んだバラストの量で飛べる時間が制限されてしまいます。
この問題を解決するには、気球を密閉してあらかじめ圧力をかけておくことで日が沈んでもしぼまないようにした、スーパープレッシャー気球が有効です。しかし、気球に圧力をかけると、皮膜に大きな力がかかるため、なかなか実現できずにいます。
気球グループでは、フィルムの選定、接着方法、フィルムとロープの固定方法、気球の型紙の形状、気球頭部尾部構造、などの技術開発を進め、小型気球の屋内膨張試験(図3)、飛翔試験(図4)によってその技術を一歩ずつ確認してきました。2006年には、体積2,000m3の気球を飛翔させ、十分に圧力に耐えられることを確認しています。2007年には、ブラジルで、実際の科学実験に利用することができる、体積300,000m3の気球を飛翔させる試験を行ないます。
惑星気球
大気のある惑星には気球を浮かべることができます。風に乗って広範囲の地表面を詳しく探査することや浮遊している大気自体のその場観測もできます。温度環境が変化しても浮力が影響を受けにくいスーパープレッシャー型の気球なら非常に長い間観測を続けることができます。地球の成層圏と同程度の大気密度しかなく温度変化の激しい火星や、数十気圧にもなり高温で硫酸性の大気をもつ金星など、各惑星に適した気球の研究を行っています。火星には高い圧力差に耐えられる3次元的な膨らみ構造をもつカボチャ型スーパープレッシャー気球、金星の高温大気中では水を浮揚ガスとして用いるコンパクトで軽量な円筒型気球(図5)を検討しています。また、300℃以上になる金星の低高度では非膨張形式の金属薄膜製球形気球を考えています。
