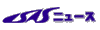| - Home page |
| - No.270 目次 |
| - 宇宙科学最前線 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - いも焼酎 |
| - 東奔西走 |
| - 内惑星探訪 |
| - 科学衛星秘話 |
| - 宇宙・夢・人 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |

さる7月26日(土)に相模原キャンパスで宇宙科学研究所一般公開が行われました。開場前から大勢の人が集まり,予定を繰り上げて9時40分ごろに入場を開始しました。当日は前夜の雨も上がり,薄曇りで絶好の一般公開日和となり,入場者は1万5000人を越える盛況となりました。
今年は,5月に打ち上げに成功した小惑星探査機「はやぶさ」の構造モデルを中心に,惑星系の展示で第1会場(A棟1階ロビー)を飾りました。また共和小学校校庭をお借りして水ロケットを復活しましたが,相変わらず子供たちの人気の的でした。新企画のスペースチェンバーを使った人工オーロラもなかなかの人気でした。その他どの会場も大変盛況で,見学者の切れることがありませんでした。今年はお隣の相模原市立博物館の協力を得て,ミニミニ宇宙学校をその会議場で開催しました。こちらは入場者の誘導が今後の課題となりました。
宇宙研の一般公開は今年が最後ですかとの質問を受けました。宇宙研は今年10月に新機構に移行しますが,宇宙科学の研究・開発の現場を市民の皆さんに見学・体験していただき,宇宙科学への理解を深めていただく行事は今後も続けますよ,とお答えしました。来年以降もこのような手作りの一般公開を続けることができるよう願っています。
(長瀬文昭)
|
|
|---|