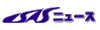| - Home page |
| - No.289 目次 |
| - 特集にあたって |
| - プロローグ |
| - 1 国分寺のペンシル |
| - 昔の人は偉かった! |
| - 2 千葉のペンシル |
| + 3 荻窪のペンシル |
| - 4 道川のペンシル |
| - ペンシルの飛翔は私たちが撮った! |
| - 5 ベビーへ |
| - 6 後を頼むぞ |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
3 荻窪のペンシル
●暗中模索
 |
|---|
| 3種のペンシル |
 ロケットが飛翔体のことだと気付いたのが,糸川先生が来てから2日目のことです。それまでは,何で私が女性の飾り物(ロケット)をやらされるのかと思っていました。(垣見)
ロケットが飛翔体のことだと気付いたのが,糸川先生が来てから2日目のことです。それまでは,何で私が女性の飾り物(ロケット)をやらされるのかと思っていました。(垣見)
 内部の圧力や推進力を測らなくてはなりません。荻窪の工場の中にテストスタンドを作るのですが,いつ爆発するか分かりませんから,穴を掘って人間が入れるくらいの地下にベトンで実験用の燃焼室を作りました。(戸田)
内部の圧力や推進力を測らなくてはなりません。荻窪の工場の中にテストスタンドを作るのですが,いつ爆発するか分かりませんから,穴を掘って人間が入れるくらいの地下にベトンで実験用の燃焼室を作りました。(戸田)
 ちょうどそのころ,武豊にペンシルの推進薬よりもっと大きい65mmと110mmのものがあることが分かりました。だから,ペンシルと並行してベビーロケットの開発も始めました。そのテストも荻窪工場のテストスタンドでやりました。初めのころは意外に推進力が強く,そのために振動が起きて隣の工場にある旋盤が揺れてしまいました。「削っているものが駄目になってしまうから,荻窪でそんなことをやってはいけない。出て行ってくれ」と言われました。(戸田)
ちょうどそのころ,武豊にペンシルの推進薬よりもっと大きい65mmと110mmのものがあることが分かりました。だから,ペンシルと並行してベビーロケットの開発も始めました。そのテストも荻窪工場のテストスタンドでやりました。初めのころは意外に推進力が強く,そのために振動が起きて隣の工場にある旋盤が揺れてしまいました。「削っているものが駄目になってしまうから,荻窪でそんなことをやってはいけない。出て行ってくれ」と言われました。(戸田)
●天才垣見の奮闘
 ペンシルの設計は,私がやりました。というのは,そんな金にならないことに会社が人材をくれないのです。だから,私1人だけでした。設計の基本である熱計算も全部自分でやりました。しかも,今のような電卓ではなく,手回しのタイガー計算機です。これは肉体労働で,例えば掛け算の2×5のときは2を5回,回さなければならないので,大変な作業なのです。(垣見)
ペンシルの設計は,私がやりました。というのは,そんな金にならないことに会社が人材をくれないのです。だから,私1人だけでした。設計の基本である熱計算も全部自分でやりました。しかも,今のような電卓ではなく,手回しのタイガー計算機です。これは肉体労働で,例えば掛け算の2×5のときは2を5回,回さなければならないので,大変な作業なのです。(垣見)
 戦争に負けて,中島飛行機には航空機用の材料がそのまま残っていました。材料倉庫に行くと,ジュラルミンや鉄材料などいろいろあり,特にジュラルミンがたくさんありました。その中に直径30mmぐらいのジュラルミンの丸棒がありました。その名称を見ると「チ−201」となっていました。「チ」というのは中島の戦争中の規格で,ジュラルミンのことを「チ」といっていたのです。「チ−201という材料があって,これはロケットの材料に使えそうだ」と糸川先生に話をしたら,「ジュラルミンなんてロケットの燃焼熱で溶けちゃうよ」と言われました。しかし熱伝達を計算すると,どうもそれほどの温度にはなりません。(垣見)
戦争に負けて,中島飛行機には航空機用の材料がそのまま残っていました。材料倉庫に行くと,ジュラルミンや鉄材料などいろいろあり,特にジュラルミンがたくさんありました。その中に直径30mmぐらいのジュラルミンの丸棒がありました。その名称を見ると「チ−201」となっていました。「チ」というのは中島の戦争中の規格で,ジュラルミンのことを「チ」といっていたのです。「チ−201という材料があって,これはロケットの材料に使えそうだ」と糸川先生に話をしたら,「ジュラルミンなんてロケットの燃焼熱で溶けちゃうよ」と言われました。しかし熱伝達を計算すると,どうもそれほどの温度にはなりません。(垣見)
燃料は先述のとおり,戸田が日本油脂の村田から譲り受けていた,朝鮮戦争のときに使われたバズーカ砲の燃料である。バズーカ砲は速く燃えないと困るので,そういうマカロニのような燃料をたくさん入れて砲弾にするわけである。糸川の即断で,それを燃料にしようという話になった。
●冷や汗の実験
 まず,燃料が燃えるスピードを実験で出さないといけません。もらったデータから考えてたぶんこのぐらいで燃えるから,そうするとどれぐらいのガスが発生するか,それによってどのくらいの圧力に上がるかというのを計算して,実験装置を作りました。(垣見)
まず,燃料が燃えるスピードを実験で出さないといけません。もらったデータから考えてたぶんこのぐらいで燃えるから,そうするとどれぐらいのガスが発生するか,それによってどのくらいの圧力に上がるかというのを計算して,実験装置を作りました。(垣見)
 その装置でまず1本燃やして,無事に燃えました。次は2本燃やしてみる,次に3本燃やしてみる,とやっていったわけです。4本無事に燃えたところで,ジャンプして8本入れて燃やしました。荻窪の構内にタコツボを掘ってそこに置いて,上に向けて燃やしていたのです。8本目になったときに,大きな音がして何かが上に上がっていきました。(垣見)
その装置でまず1本燃やして,無事に燃えました。次は2本燃やしてみる,次に3本燃やしてみる,とやっていったわけです。4本無事に燃えたところで,ジャンプして8本入れて燃やしました。荻窪の構内にタコツボを掘ってそこに置いて,上に向けて燃やしていたのです。8本目になったときに,大きな音がして何かが上に上がっていきました。(垣見)
 何が上がったか,すぐには分からなかったのですが,ひょっとタコツボの中を見ると,ロケットのノズルがないのです。あれと思ったら,「ダーン」と落ちてきました。グラウンドは硬いところですが,そこに1mぐらいめり込んでいました。どうもノズルが落ちたらしい,と掘り起こしてみたら本当にノズルでした。(垣見)
何が上がったか,すぐには分からなかったのですが,ひょっとタコツボの中を見ると,ロケットのノズルがないのです。あれと思ったら,「ダーン」と落ちてきました。グラウンドは硬いところですが,そこに1mぐらいめり込んでいました。どうもノズルが落ちたらしい,と掘り起こしてみたら本当にノズルでした。(垣見)
 いろいろ調べたら,燃焼速度のデータが間違っていました。そのためにガスの発生量がめちゃくちゃに多くて,内圧が上がってボルトにかかる力がうんと増えてしまい,ボルトが切れてしまったのです。計算によれば,本来8本ぐらいで強力なボルトが切れるわけがないという先入観がありましたので,判断を誤った次第です。(垣見)
いろいろ調べたら,燃焼速度のデータが間違っていました。そのためにガスの発生量がめちゃくちゃに多くて,内圧が上がってボルトにかかる力がうんと増えてしまい,ボルトが切れてしまったのです。計算によれば,本来8本ぐらいで強力なボルトが切れるわけがないという先入観がありましたので,判断を誤った次第です。(垣見)