No.204
1998.3
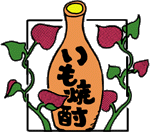 ISASニュース 1998.3 No.204
ISASニュース 1998.3 No.204
No.204 |
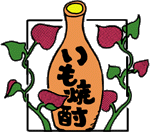 ISASニュース 1998.3 No.204
ISASニュース 1998.3 No.204
|
| - Home page |
| - No.204 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - 送る言葉 |
| - 宇宙科学将来計画検討会について |
| - 見えてきた宇宙X線背景放射の正体 |
| - 火星探査入門 |
| - 追悼 |
| - 東奔西走 |
| - 宇宙輸送のこれから |
| + いも焼酎 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
新聞記事のロケット1号
1960年12月9日内之浦町南方上向集落にあった旅館池田荘で,東大教授糸川英夫博士を取り囲むように同大文部事務官下村潤二朗氏,久木元峻町長,上林房正信議長,田中キミ町婦人会長ほか町のトップクラスが鳩首懇談をしていた。東大ロケット実験場を内之浦町南方長坪に誘致するというビッグニュース。肝心の長坪振興会長を有線放送で急遽呼び出す依頼があり,私も会場に同席させてもらった。糸川博士の帰京の時間を聞き出し,南日本新聞社社会部へ特報。社会部記者が鴨池空港で糸川博士をお待ちして取材。翌12月10日付の社会面に,博士の顔写真と長坪の地図入りでロケット候補地の記事が掲載された。これがやがて全世界にアピールされてゆくKSCの新聞記事ロケット1号となった。
200号ロケットと玉木先生
1973年9月23日付南日本新聞社会面に,200号機を超したロケットの見出しで玉木章夫先生の追悼記事を書いた。
「1955年8月,秋田県道川で産声をあげた日本のロケットペンシル300-1号機から通算すると内之浦200号機は291機目になる。ペンシルロケット時代からロケット開発のリーダーだった玉木章夫東大宇宙航空研究所長は,9月7日ガンのため逝去された。葬儀の翌日15日,同実験場から打ち上げられたカッパ10C型4号機は,内之浦200機目のロケット。風に強いロケット開発に全力を注ぎ込みながら病魔に倒れた玉木教授の頭脳が生かされたミュー3C型の予備テスト機で,みごと成功した…。」
玉木先生が所長時代だったか定かではないが,よくウォーキングをされていた。ある日の午後,先生が額に汗をにじませて拙宅に来訪された。妻が入れたKSCでも好評のコーヒーを目を細めて召し上がったあと長野観音を拝観してきました。とても立派な観音様で自然環境もすばらしいところでした。折角の保存を望むと,微笑みを浮かべて話されたお顔が今でも目を閉じれば瞼に浮びます。
長野観音は元文4年廻漕業の須田儀兵衛(ぎひょうえ)が勧請したもので,町役場から6キロ,大谷添林道下の大巌窟の中に鎮座する石造の十一面観音。洞窟の中にサラサラ流れていた湧水が,水脈が変わって流水が多くなり洞窟内の地盤沈下が目立ってきた。玉木先生のことを思い起こしながら町社会教育課と対策を講じている。
示現流?シャッター
1998年2月5日KSCから打ち上げられた,SS-520-1号機は,私の記録では内之浦368機目のロケット。これまでほとんどのロケットを撮影してきたが,私のロケット撮影法はモータドライブを使わず,ファインダーの中の任意の位置で一発でロケットを仕留める。それを示現流シャッターと自称している。それはカッパ10C型2号機の打上げから始まった。
1969年9月26日,姿勢制御装置をテストする同機は,こともあろうに2段目だけが飛び出すという前代未聞の打ち上げとなった。1・2段の間から姿勢制御用の燃料の過酸化水素が過熱して勢いよく噴き出した。異状を察知した私は,長坪グリルの鉄柱を盾に身構え,噴射と2段目飛び出しのロケットを仕留めて翌27日の社会面を華々しく飾った。
内之浦町の文化祭には,写友が宇宙やロケットをモチーフにした作品を展示する。「宇宙に一番近い町」が内之浦のキャッチフレーズ。カメラを通して宇宙に思いを馳せる仲間を一人でもふやしたいと思っている。
(フリーカメラマン まき・たくみ)
|
|
|---|
|
|---|