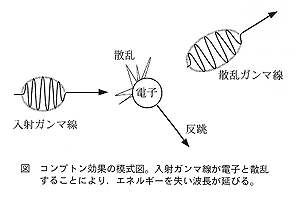第11回 「コンプトン散乱」
宇宙科学研究所 堂谷忠靖
光の性質というと,小学校の理科の実験でも取り上げられるように,レンズで集光したりプリズムで七色に分解したりと,我々にも馴染みの深いものである。しかし,同じ光の仲間でも,エックス線やガンマ線になると,可視光では見られない性質を示すようになってくる。
エックス線やガンマ線のように,波長が短くエネルギーが高い(正確には,電子の静止エネルギーに近い)電磁波で重要になってくる現象に,コンプトン効果がある。この現象は,1923年にアメリカの実験物理学者,コンプトンによって発見された。コンプトン効果は,電磁波を波ではなく粒子と考えると理解しやすい(図参照)。ガンマ線の“粒子”が静止した電子に勢い良くぶつかると,その反動で電子がはじき飛ばされ,逆にガンマ線がその分だけエネルギーを失ってしまう。つまり、ガンマ線のエネルギーと運動量の一部が電子に移動するわけである。
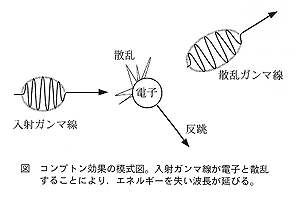
その結果,ガンマ線の波長は少し長くなってしまう。この,散乱によりガンマ線の波長が少し長くなるというのが,コンプトン効果である。このように書くとわかりにくいかも知れないが,相手を弾き飛ばすことで自分の運動量が落ちるというのと原理的に同じことは,ビリヤードやおはじき遊びでも行なわれているわけで,ごく当たり前のことと言えるかも知れない。この発見により,コンプトンはノーベル賞を受賞した。
今度は,電子が高速で動いている場合について考えてみよう。この場合は,勢い良く走っている電子に光子が弾き飛ばされ,光子のエネルギーがウンと高くなる代わりに,電子のエネルギーが低くなることになる。前の例とは,電子と光子の立場が逆になっているわけで,このような散乱を逆コンプトン散乱と呼んでいる。身近な例では,ボーリングでボール(電子)に弾き飛ばされるピン(光子)でも同じことが起きているわけだし,身近でない例では、スウィングバイで加速していく惑星探査衛星があろう。後者では,惑星が電子に,探査衛星が光子に対応するわけである。
ところで,宇宙を眺めると,とてつもなく強い磁場をもつ中性子星(表面で1012ガウス,ピップエレキバンの10億倍)のまわりや,巨大ブラックホール(太陽質量の100万倍以上)などのやたら重力ポテンシャルの深いところには,ほとんど光速で飛びまわる電子がふんだんに存在する。このような電子が,周辺に存在する可視光などの波長の長い光子を弾き飛ばすと,光子はウンとエネルギーをもらってエックス線やガンマ線に変化することになる。実際,これらの天体からは,強力なエックス線やガンマ線の放射が観測されている。
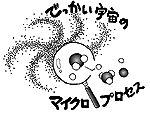 ISASニュース 1997.10 No.199
ISASニュース 1997.10 No.199
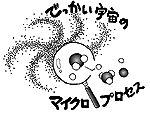 ISASニュース 1997.10 No.199
ISASニュース 1997.10 No.199