No.183
1996.6
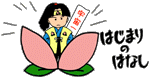 ISASニュース 1996.6 No.183
ISASニュース 1996.6 No.183
No.183 |
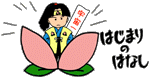 ISASニュース 1996.6 No.183
ISASニュース 1996.6 No.183
|
| - Home page |
| - No.183 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - M-V事情 |
| + はじまりのはなし |
| - 東奔西走 |
| - 小宇宙 |
| - いも焼酎 |
| - BackNumber |
月をさらに身近にした出来事と言えば,アポロ計画による人類の月面活動であろう。科学的にもアポロ宇宙飛行士が月面から持ち帰った岩石の研究により,月物質に関する化学的データは飛躍的に増大した。月の岩石は地球に比べて難揮発性元素が多く,逆に揮発性元素と親鉄性元素が欠損していることが分かった。
月と地球のちがいは,月がどのようにして誕生し,地球のまわりをまわるようになったのか,すなわち「月のはじまり」に大きく関係していると思われる。月の起源については,19世紀のダーウィンによる分裂説に始まり,これまでに様々なモデルが提唱されている。それらは地球と月の関係によって,以下に述べるような3つのモデルに分けられる。
| - Home page |
| - No.183 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - M-V事情 |
| + はじまりのはなし |
| - 東奔西走 |
| - 小宇宙 |
| - いも焼酎 |
| - BackNumber |
最近では,火星サイズの天体が原始地球に衝突し,飛び散った地球のマントルが地球のまわりで集まって月が作られたという仮説(ジャイアント・インパクト説)がアメリカを中心に流行した。巨大衝突は必然的に物質を加熱するので,月の揮発性元素が少ないことが説明でき,地球−月系が持つ大きな角運動量も説明できるため人気を得た。しかし,この仮説も月の起源説の決定打にはならなかった。
これらのモデルの拠り所になっているのはアポロ計画で得られたデータである。月の表側の限られた地域の表層の情報を月全体の平均的な情報にどう焼き直すかについては今も議論が続いているため,どのモデルが正しいかを検証できないのが現状である。来年度打ち上げられる宇宙科学研究所月内部探査機ルナーAにより「月のはじまり」の謎を解くためのグローバルな情報が得られることが期待されている。
月は衛星ではあるが比較惑星学的立場からいえば地球型惑星のひとつとして取り扱ってもよいほど大きい。また,月は太陽系内の衛星としては惑星(地球)に対してとても大きいので,「月のはじまり」は「地球のはじまり」に大きく影響していたであろう。月のはじまりの謎を解くことは惑星や太陽系のはじまりの謎を解く重要な鍵となる。
(はやかわ・まさひこ)
|
|
|---|
|
|---|