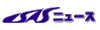| - Home page |
| - No.302 目次 |
| - 宇宙科学最前線 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - 科学衛星秘話 |
| - 宇宙の○人 |
| - 東奔西走 |
| - いも焼酎 |
| - 宇宙・夢・人 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
はやぶさ近況
イトカワの素顔をとらえるONC−T(AMICA)
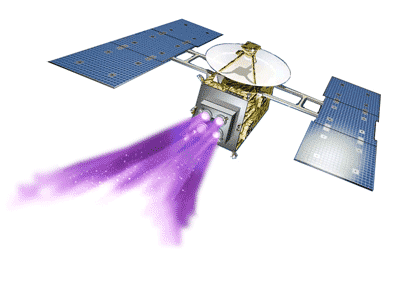 |
|---|
| 「はやぶさ」 |
「小惑星の理学観測といえばカメラ!」と筆者としては言いたいところではあるのですが、残念ながら「はやぶさ」には理学観測専用のカメラは積まれていません。実は、宇宙機の目として使われる航法用カメラを一部理学観測のために使わせていただいて、サイエンス目的の画像を取得しているのです。そのため、同じカメラでもONC−T(望遠光学航法カメラ)とAMICA(Asteroid Multiband Imaging Camera)という2通りの名前が付いています。前者が工学側の呼び名で、後者が理学側の呼び名です。ここでは、AMICAと呼ぶことにしましょう。
ご承知の通り、AMICAは数多くのイトカワの画像を取得し、その特異な形状や表層の姿を明らかにしました。しかし、カメラの真骨頂は、やはり色フィルタを用いたカラー情報の取得だと思います。
AMICAには、7バンドの色フィルタと偏光子が搭載されています。色フィルタは小惑星の望遠鏡による分光観測で実績のあるシステムとほぼ等価のものを搭載していて、小惑星表層のわずかな色の違いも判別することができます。幸いイトカワは、明るさだけでなく色のバリエーションも豊富だったため、この7バンド撮像による色の違いの判別は非常に有効で、かつ興味深いものでした。
イトカワの表面を見ると、傾向として明るい部分が青っぽく、暗い部分が赤っぽくなっていることが明らかになりました。小惑星表面の物質が宇宙放射線や微小隕石の衝突などにより劣化するという現象があるらしいとされているのですが、これは、その程度の違いを示している可能性があると考えています。
今後の議論のため色をきちんと定量的に決めるには、キャリブレーションが不可欠です。そのためAMICAは、イトカワへ向かう途上でいくつもの標準星を撮像して情報を集めてきました。現状ではまだ定性的な色の違いしか示すことはできませんが、キャリブレーション担当のメンバーたちが今も、標準星データを用いた定量的な色の表現をするために奮闘中です。その作業のめどが立って、初めてAMICAの性能がフルに発揮されることになると期待しています。
 |
|---|
| AMICAの3バンドの画像を合成した、イトカワの合成カラー画像 (色とコントラストは強調している) |
(齋藤 潤)
|
|---|