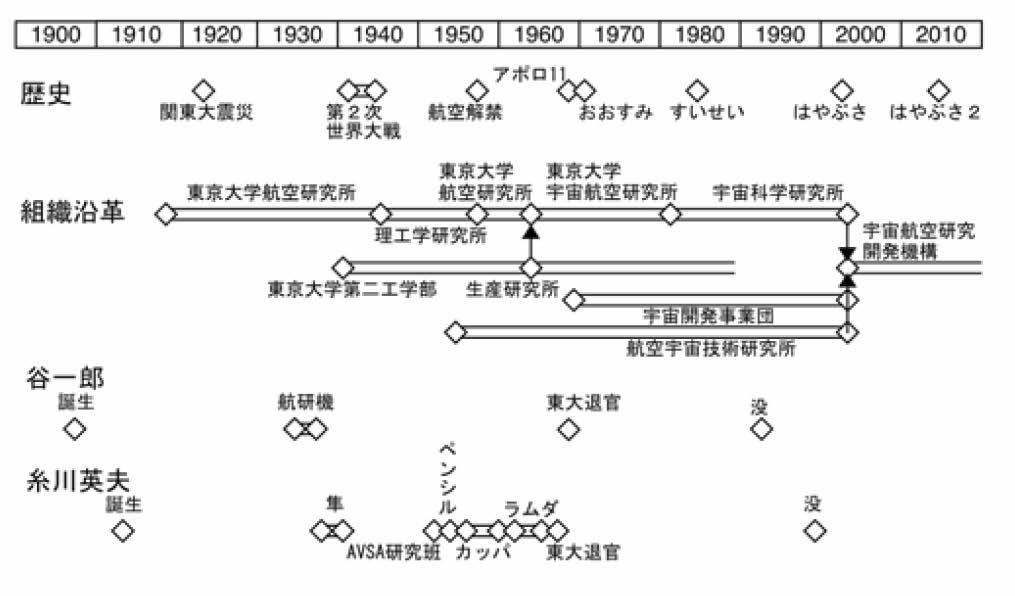TOP > レポート&コラム > ISASニュース > 特別企画
![]()
特別企画
エンジニアリングとは人間がものを創る行為である。
学問とは真理をめぐる人間関係である。
前編(完全版)
宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系
宇宙探査イノベーションハブ ハブ長
教授 國中 均
![]()
1.きっかけ
「研究をどのように進めたら良いのですか」というような唐突な質問をしばしば受ける。もしも仮に特殊なテクニックを伝授できたとしても、それは無意味なことだ。研究手法なんてものは時代とともに変遷するのであるから、私の知見経験をお伝えしても、未来においては全くの無力であろう。ほんの一例をお示ししたい。私が京都大学工学部に入学した当初、必須として「T定規」と「烏口」を買い求めさせられた。これらの道具を駆使して製図の講義が進められ、工学部出身者の嗜みとして設計製造図面を描ける技量を取得した。大学院の頃になると、ロットリングやステッドラーという大変優れた筆記用具が現れて、設計図面や論文図表の墨入れ作業にことごとく用いられて、あっという間に烏口は淘汰されてしまった。英語論文を書く場合には、それまではタイプライターで1文字ずつ手動で打っていたのであったが、英文ワープロで書いた文章を RS232C 経由でタイプライターから直接出力できるようになった。次にプリンタはドットマトリックス式となり、英文字だけでなく漢字や平仮名が打てるようになって、日本語ワープロが全盛となる。時をおかず、レーザーやインクジェットプリンタに換装され、文字だけでなく図表も描けるようになり、CADで描いた製造図面をそのままプリンタ出力できるようになった。そして今では単純な2次元でなく3DーCADとなり、印刷するどころか3Dプリンタで直接事物が作れる。この経緯はたった40年間の事柄なのだ。研究のための個別テクニックは、その時代の最先端技術を駆使し使いこなせば十分に事足りる。であるから、社会的遺伝子(Meme)としてお伝えするべきは、「研究の精神」でしかなかろう。これについては、本稿の最後に書き述べたい。
本稿を取りまとめる直接的きっかけは、当該研究部門の若手や学生が、あまりにも刹那的に周囲のノイズに動揺し、自分に託され本務を見誤りそうになる有り様を見たことに契機とする。宇宙科学研究所(以下、宇宙研)のお歴々が何を考え、どのように行動し、何を成し得てきたか、その経緯や経過を知る方が少なくなっていることも危惧する。私とて、文献や伝聞で知るのみなのだが、先達が発せられたお言葉や残された記述にはある共通する概念が秘められているのだと思う。私が理解するところのその精神をすこしでもお伝え出来たらなと思い、ここに原稿を取りまとめる。
さて、たいへん謎めいた題名を本稿に掲げたが、後ほど種明かしするとしよう。
2.大学院新入生のころ
大学院に進学する前の1982年夏のこと、当時博士課程に在学されていた牧野隆氏(現IA取締役)を訪ねて、当時駒場にあった宇宙研を見学させていただいた。「ロケット推進を研究してみたいのだけれど」と希望を述べたところ、「化学ロケットは既に実用のレベルで、もはや研究の対象でない。でも電気推進というのがあってね、まだぜんぜんなんだ」というお話を伺った。それがきっかけで、栗木恭一先生が主宰される電気推進の門戸を叩くこととなった。栗木先生は、レンガ建ての1号館1階の部屋におられた。その部屋の高いところに怖い顔をされた方の写真(図1)が飾ってあり、研究の相談に伺う度に頭上から睨まれている感覚で、すいぶん居心地が悪かった。事あるごとに栗木先生の先生のお話を伺うことがあった。「理不尽に怒る」とか「以前に指示した論文は読んだかねと、私の脳を外部メモリのように使う」とか「年度当初の第1回の講義の冒頭、開口1番が「しかし」から始まった」とか、数々の逸話である。かなり厳格な先生だったのだなと印象であった。それが流体力学の名著「流れ学」1)を編纂された谷一郎先生で、あの写真の主であることがしばらくして理解された。また栗木先生からは、「旧航研」という単語をよく聞かされた。宇宙研には「新設」グループと「旧航研」グループの二派に分かれていて、どうも仲が悪いらしい。そして、前者はあのロケット研究の開祖といわれる糸川英夫先生に源を発し、一方後者は谷先生が率いていたらしい。となると、糸川先生と谷先生は反目しあっていたのだなとてっきり思い込んでいた。人間関係のことであるから、学生の身分で機微なことは聞けないまま、そのようにすっかり信じていた。

図1 |
谷一郎先生。「谷一郎先生追悼文集一期一会」2)には、たいへん大勢の方が思い出を寄稿されている。谷先生はたとえ空襲の最中であっても、一部の隙もない背広姿、中央で節目の頭髪、厳格そのもののたたずまい、と皆揃ってお書きになっている。またたいへんなお蕎麦好きで、子供の頃から「やぶそば」に通われていたそうだ。JAXAの皆さん、新御茶ノ水本社にお立ち寄りの節には、谷先生を偲び、徒歩でほんの5分の距離の「神田やぶそば」に行かれてはいかがか。私は残念なことに谷先生にお会いしたことがない。Dandy & Noble ということであれば、私のイメージは栗木先生そのものなので、谷先生と重なって思われる。 |
新たに購入した海外学術雑誌の目次のリストが電話帳の厚さになって、毎月図書館から送られてきていた。栗木先生はそれ全てに目を通されて、注目すべき論文題名の脇にそれを担当する学生の名前を書き込んだ上で、回覧されるものだから、学生一同困った。名指しされてしまうと致し方なくその論文を読み、その参考文献を探し、孫引き、曾孫引きと古い論文を辿って乱読し、知識を増やしていった。新着論文ならともかく、こんな古い論文は見つかるまいと思っても、時計台地下のカビ臭い書庫から大概の文献を見つけ出すことができた。宇宙研の図書館の蔵書量は私の想像を遥かに超えていた。あるとき、偶然にも糸川先生の著述3)を見つけ、何気なしに手にとったところ、「私の師=谷一郎さんについて」という章を見つけて、びっくりした。私はすっかり誤解していたことに気がついた。それがきっかけで、研究所の沿革や谷先生と糸川先生の人となりや活動・言動に気に掛けて見聞きするようになった。
3.宇宙研の沿革と谷一郎・糸川英夫の活躍
図2 |
宇宙研の沿革と谷一郎・糸川英夫の活躍 [画像クリックで拡大] |
組織の沿革と対比させながら谷・糸川両先生のご活躍をおさらいしてみよう(図2参照)。航空機の基礎研究を目的に、1918年に東京帝国大学の附置研究所として、深川に航空研究所が創設された。1923年の関東大震災にて施設が全焼したため、それを契機に駒場へと移転した。(ジブリ映画「風立ちぬ」にて堀越二郎が通っていた学舎が深川の航空研究所であり、被災の様子が描かれている。)所謂プロジェクトとして企画された航研機が1937年に1万kmを超える無着陸周回飛行の世界記録を樹立する。海外からの情報収集には大変熱心で、洋雑誌が大量に購入され、妙録委員会が全ての論文に目を通し、月1回集り議論がなされていた。妙録委員会空力部門の主宰は谷先生であり、構成メンバーとして当時学生の糸川先生が活躍された。宇宙研の誇る蔵書量はこの活動に由来し、栗木先生の指導方式もここに繋がるのだと思う。谷先生は、粘性流・乱流の研究を進められ、抵抗の少ない層流(LB)翼を完成させ、戦闘機紫電改などに応用された。この技術は戦前戦中の最高軍事機密であり、米国では極秘の内に研究開発されていた。情報交換や技術交流が隔絶された環境で、谷先生は独自に研究を進められ、多くの学術論文として発表したものだから、米国側は肝を冷やしたらしい。谷先生は、卒業したら直ぐ様助手で採用するつもりであったのだが、戦争が差し迫る状況で何やらあったのか、糸川先生は中島飛行機(現IA)に就職し、一式戦闘機隼などの開発に携わる。それでも当時会社のあった荻窪から駒場へと足蹴く通い、最新の航空技術に研鑽を積んでいた。1941年開戦直前、教室主任として谷先生、助教授として糸川先生という陣容で軍事教育を司る東京大学第二工学部が組織された。しかし、戦況は悪化の一途をたどり、ついに敗戦。GHQの統制下、航空技術の研究開発が禁止され、航空研究所は約半数の教授陣を公職追放により失い、規模を縮小し理工学研究所となる4)。谷先生はここに戻られる。第二工学部は生産技術研究所となり、糸川先生はそのまま留まる。
戦後、この2人はそれぞれに米国を訪ねて、独自の価値判断とその後の進路を決断する。
....................................................................................
1952年の夏、シカゴの中心街ホテルで、アメリカ機械学会と航空学会の共催するシンポジュウムが開かれ、故フォン・ブラウン博士の「有人・月飛行」と題する特別講演が行われた時のことである。その会場で、私は思いがけず、谷一郎先生にお会いした。 〜中略〜。私は、興奮さめやらぬ気持ちで会場を出ると、先生とコーヒー卓を囲んだ。先生は、故フォン・ブラウン博士とは対極的に、いかにもスマート、ノーブルで物静かな風格であられたが内には強靱不屈の闘志を秘められていたに違いない。「たいへん情熱的ですな。フォン・ブラウンさんは、・・・・」そんなことを言われて、いろいろとお話をされた。2)
....................................................................................
一方、糸川先生はこのように述べている5)。
....................................................................................
空白であるジェットエンジンの開発と、ジェット旅客機の研究を急きょ、追いかけるべきか。それとも、まだホンのハシリに過ぎない宇宙研究にジャンプして、やがて来るであろう宇宙研究国際競争時代に出場資格を確保するべきか。はるか太平洋をへだてた日本の一つの運命を、アメリカにいたからこそ、深刻に考えていたのだと思う。
....................................................................................
谷先生は戦前戦中の業績が認められ、欧米から高い評価を受ける。「日本でやがて航空が解禁された時に、すぐに列国の水準に追いつかなくては」2)と、航空技術再興を目標とされていた。(今年2015年、国産ジェット旅客機MRJが大空に勇姿を見せたことは喜ばしい限りだ。)片や、糸川先生は業績半ばで熱意を燻らせていて、まだお若く、次なる新たな領域へ挑戦を志す。社会からの期待や要請、挑戦的姿勢と言った環境条件が2人では異なっていたのだろう。
旅程を切り上げて早々に日本へ帰られた糸川先生は、AVSA研究班を1953年に組織してロケット開発に着手する。旧中島飛行機の荻窪工場での燃焼実験を皮切りに、ペンシル・カッパ・ラムダロケットと研究開発が進み、1958年IGY国際地球観測年には、高度100kmに到達する。航空研究禁止が解かれ、理工学研究所から名前を戻した航空研究所と糸川グループを合体させ、宇宙航空研究所として1964年に再編成された。この時多くの議論が巻き起こる2)。基礎研究を目標としていた研究所が、航研機と言ったシステム開発に手を染め、多くの負の事柄を誘発した経験から、ロケット開発や衛星打上といった事業を大学に持ち込むべきでないという主張や、航空禁止の期間に日本の航空技術は立ち遅れてしまい、もはや研究の対象でなく、航空研究所としては存続し得ないといったことであった。この時の航空研究所所長というお立場で、人心を掌握し組織の整理統合に尽力されたのが、谷先生であった。この間に、谷先生と糸川先生が直接お話しされたというような記述を私は知らない。ここを契機に、人工衛星の実現に向けて組織化と活動が加速されてゆく。しかし、学問や技術とは異質の動議がかかり、1962年に糸川先生は一線を退いてしまい、谷先生も翌年に定年退官される。それでも後進たちは、失敗を積み重ねてようやっと、1970年2月に24kgの「おおすみ」を軌道周回させるに至る。こうして世界で4番目の衛星打ち上げ国に名を連ねることができた。糸川先生が戦後に目標とされた「宇宙研究国際競争時代に出場資格」5)を得たのだ。しかし、米国はその半年も前の1969年7月にアポロ11号で月有人探査を実現させている。日米ではそれだけの技術格差であった。
ロケット事業が拡大し東大附置研究所の枠組みでは賄うことができないほど、予算が膨張する。そこで東大を離れ文部省直轄の組織、宇宙研として再編される。この時も研究所を二分する大きな議論が巻き起こる6)。基礎研究に回帰するべしとするグループと、国立大学の枠組みを取り払い自由闊達に宇宙科学に邁進するべきと考える者達に別れ、結局1981年、前者は境界領域研究所として駒場に残留し、後者は宇宙科学研究所となり相模原へと移転する。航空研究所から宇宙航空研究所へ、さらに宇宙科学研究所へと2回の組織編成の際に、関係者の心に残った蟠りが栗木先生の言う「旧航研」の言葉に集約されているのだと思う。
ここまでの組織の離合集散は伝聞や記録から読み取って知ったことである。私がリアルタイムの目撃者となったのは、宇宙開発事業団・航空技術研究所・宇宙研を統合し、2003年宇宙航空研究開発機構(JAXA)の出現だ。最大の理由は国家財政の逼迫であり、この3機関の合計予算は1999年度の公式2,200億円をピークに下降傾向をたどる。連携をより密にして効率的効果的な宇宙開発事業を行うべしとする国の行政改革の一環である。当時「はやぶさ」を打ち上げた前後のことであり、宇宙現場維持に奔走していて、組織運営のことなど興味もないしまたその任でもなかったので、どこか第三者的感覚であった。
何度か内部会合があり、新たな組織に宇宙研方式を深く浸透させるべし、という勇ましい意見もあったが、結局のところ事業団1,000名vs宇宙研300名では、吸収といった体であった。統合前後に複数のロケットや衛星の事故に見舞われたが、JAXAの英知を結集し立て直し、昨今では宇宙技術が安定に運用されようになった。
いつも最先端を求め、創意工夫を発揮して「日本発のイノベーション」でもって空から宇宙さらに深宇宙へと射程を伸ばし、人類の活動領域拡大に貢献した経緯が見て取れよう。
( 後編(完全版)に続く)
参考文献
1) 谷、「流れ学」、岩波全書、1963年
2) 谷一郎先生追悼文集委員会、「一期一会 谷一郎先生追悼文集」、1991年
3) 糸川、「糸川英夫の人生に消しゴムはいらない」、中経出版、1995年
4) 河村、「大学生活思い出の記」、東京大学宇宙航空研究所報告 第14巻第2号、1978年
5) 糸川、「私の履歴書」日本経済新聞、昭和49年
6) 竹野、「大学における工学教育」、名城大学理工学部研究報告、No.47, 2007