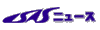| - Home page |
| - No.289 目次 |
| - 特集にあたって |
| - プロローグ |
| - 1 国分寺のペンシル |
| - 昔の人は偉かった! |
| - 2 千葉のペンシル |
| - 3 荻窪のペンシル |
| + 4 道川のペンシル |
| - ペンシルの飛翔は私たちが撮った! |
| - 5 ベビーへ |
| - 6 後を頼むぞ |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
4 道川のペンシル
●秋田ロケット実験場
次の最大の難関は,いよいよ本格的に上に向かって飛翔実験を行う場所の選定だった。落ちてきたロケットが危害を及ぼしてはいけない。外国のように広い砂漠のない日本としては,海岸から打ち上げて海に落とす以外にはない。そのためには,まず船舶や航空機の主要航路を避けなければならない。それに漁船が少ない場所がよい。学問的な研究なので,政治的な紛争からは一線を画したい。そこで,文部省が中心となって各省次官会議で協力の打ち合わせまで行い,関係各省が一切の面倒を見ることになった。
 1955年ごろには,海岸はすべて米国が占有していてね。空いているところは佐渡島と男鹿半島の2ヵ所しかなかったんですよ。当時,糸川くんは私とペアを組んでチームを動かしていてね。私たち2人は海上保安庁の船を出してもらって,まず佐渡島を見に行きました。ところが当日は海が荒れて,糸川くんは船にすっかり酔ってしまった。これでは,佐渡島に機材を運搬することはとても考えられない。実験場としては落第だってんで,次に男鹿半島に行ってみたんだが,とても狭くて実験場として不向きでした。そこで私たちは相談して,道川なら男鹿半島に近いし,海岸が広く使えること,それから町が近いので寝泊まりに宿屋が使えることなどの理由で,道川を選んで実験をやったのです。(高木 昇)
1955年ごろには,海岸はすべて米国が占有していてね。空いているところは佐渡島と男鹿半島の2ヵ所しかなかったんですよ。当時,糸川くんは私とペアを組んでチームを動かしていてね。私たち2人は海上保安庁の船を出してもらって,まず佐渡島を見に行きました。ところが当日は海が荒れて,糸川くんは船にすっかり酔ってしまった。これでは,佐渡島に機材を運搬することはとても考えられない。実験場としては落第だってんで,次に男鹿半島に行ってみたんだが,とても狭くて実験場として不向きでした。そこで私たちは相談して,道川なら男鹿半島に近いし,海岸が広く使えること,それから町が近いので寝泊まりに宿屋が使えることなどの理由で,道川を選んで実験をやったのです。(高木 昇)
高木と糸川は,いろいろなことを相談して決めた。チームは,機械・電気・航空という分野の専門家の集まりである。これからの発射実験では,それぞれの分担した専門のところが故障して失敗を重ねてゆくことだろう。失敗個所を分担した専門家は,当然故障原因は自分でよく分かる。だから反省はそれぞれの専門家がすべきであって,専門家以外の人が口出ししてはならない。グループはいろいろな専門家の集まりであり,決して専門以外のことで議論はしないこと。それを互いによく承知して戒め合ったのである。
それから,電気と電気以外の専門家が組になって実験主任を行うこと,例えば,高木昇と糸川英夫,玉木章夫と斉藤成文,森大吉郎と野村民也のように,実験主任の組み合わせが決まっていった。
こうした経緯で,ロケット発射の舞台は秋田県の道川海岸に移る。道川は1955年8月から1962年に至るまで,日本のロケット技術の温床であり続けた。
 |
|---|
| テントが実験本部 |
 |
|---|
| ペンシル300のランチャ |
●ペンシル300の打上げ
道川での歴史的な第1回実験は,ペンシル300の斜め発射であった。1955年8月6日。天候晴れ,風速5.7m。長さ2mのランチャ上に,全長30cm,尾翼ねじれ角2.5度のペンシル300がチョコンと載っている。発射上下角70度,実験主任は糸川英夫,総勢23名の実験班。13時45分,赤旗上げ。14時15分,花火上げ。「総指揮」と書いた腕章を腕に巻いた糸川は,主任として実験場所上段に着席した。電球を10個ほどつけ,ロケット運搬終了,ランチャ装置終了など実験準備の進行に従って裸電球を一つずつ消していき,最後に発射準備完了となったとき,端にあるひときわ大きな電球が点灯する仕組みを考えたのも,糸川である。彼は「日本初のコントロールセンターです」と言って澄ましていた。
 |
|---|
| 糸川の秒読み |
30秒前から糸川の秒読みが開始された。いつもより緊張した声。
「5,4,3,2,1,ゼロ!」。……14時18分,発射!
「あっ!」
誰もが息をのんだ。ペンシルはランチャから砂場へ転げ落ち,砂浜をねずみ花火よろしくはい回ったのである。
 そのとき,実験する方は23人しかいませんでしたが,報道陣は70〜80人来ていたと思います。報道陣に対する宣伝など,糸川先生は非常に上手でした。ランチャは池田教授の設計で,特殊な形をしていました。国分寺での水平発射はうまくいきました。ところが秋田での第1号機はロケットの支えを怠ったので,火を入れた途端に落ちて地面をはい回ってしまい,失敗でした。下にくぎを1本刺せば止まったので,それで飛ばしました。高度600mぐらいのところまで飛んで成功しました。(戸田)
そのとき,実験する方は23人しかいませんでしたが,報道陣は70〜80人来ていたと思います。報道陣に対する宣伝など,糸川先生は非常に上手でした。ランチャは池田教授の設計で,特殊な形をしていました。国分寺での水平発射はうまくいきました。ところが秋田での第1号機はロケットの支えを怠ったので,火を入れた途端に落ちて地面をはい回ってしまい,失敗でした。下にくぎを1本刺せば止まったので,それで飛ばしました。高度600mぐらいのところまで飛んで成功しました。(戸田)
ロケット燃料に点火するには,その直前に小型のイグナイター(点火器)にまず点火し,そこから出る炎で主燃料に火を付ける。国分寺のように水平発射ではないので,ロケットがすべり落ちないようお尻にビニールテープの支えを張ってあったのだが,イグナイターが発火したとき,その小さな噴射でビニールテープが外れ,ロケットは打ち上がらず,「打ち下がった」のである。
もちろん急いでランチャ下部に鉄線のストッパーを取り付け,15時32分に再度挑戦。尾翼ねじれ角0度のペンシルが史上初めて,重力と空気抵抗の障害のただ中を,美しく細い四塩化チタンの白煙を残して夏の暑い空へ飛び立った。到達高度600m,水平距離700m。記念すべきペンシルの飛翔時間は16.8秒であった。
重さわずか230gというミニロケットの海面落下に備えて,400トンの巡視船が沖合に出動した。8月の熱い砂に実験班員のキャラバン靴は潜り込み,
 あたかも古代遺跡を掘りにきた探検隊のようでした。電話も引かず自転車が足でした。大学の先生方がやる野外実験とはこういうもの,とその質素さが今は懐かしいですねえ。(下村潤二朗)
あたかも古代遺跡を掘りにきた探検隊のようでした。電話も引かず自転車が足でした。大学の先生方がやる野外実験とはこういうもの,とその質素さが今は懐かしいですねえ。(下村潤二朗)
この日,糸川が夏の日の静謐を詠んだ。
夏海の まばゆきをまへに
初火矢を揚げむとすれば 波は寄る音
 |
|---|
| 道川のロケット発射場全景 |