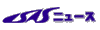| - Home page |
| - No.262 目次 |
| - 新年の御挨拶 |
| - ISAS事情 |
| - 特集にあたって |
| - 第1章 はじめに |
| - 第2章 「ひのとり」から「ようこう」へ |
| + 第3章 「ようこう」の観測装置 |
| - 第4章 「ようこう」の科学成果 |
| - 4.1 概観 |
| - 4.2 硬X線で見た新しい太陽フレアの姿 |
| - 4.3 フレアの磁気リコネクションモデル |
| - 4.4 フレアに伴うX線プラズモイド噴出現象 |
| - 4.5 S字マークは要注意 |
| - 4.6 X線ジェット |
| - 4.7 活動的なコロナ |
| - 4.8 コロナ加熱 |
| - 4.9 コロナの観測から分かった磁気周期活動 |
| - 第5章 国内の共同観測 |
| - 5.1 太陽を波長10Åと波長108Å(=1cm)で見る |
| - 5.2 フレア望遠鏡との協力 |
| - 5.3 飛騨天文台との協力観測 |
| - 第6章 「ようこう」からSOLAR-Bへ:新しい挑戦 |
| - 日本的発想と国際協力 |
| - 水星の日面通過 |
| - 太陽フレアと磁気圏サブストームの比較リコネクション学の発展 |
| - 全世界への「ようこう」データの配信 |
| - 「ようこう」と世界の科学者たち |
| - 日食観測は鬼門! |
| - 英語になったTOHBAN(当番) |
| - 「ようこう」関連の国際会議,成果出版物 |
| - 「ようこう」関係受賞一覧 |
| - BackNumber |
|
「軟X線望遠鏡」は,日米の国際協力で開発された,太陽全面を軟X線領域(5-60Å)で撮像する望遠鏡です。太陽コロナのダイナミックな変化や太陽フレアで生成される高温プラズマを高い空間分解能(2.45秒角)で観測します。軟X線望遠鏡は,斜入射X線反射鏡により直接太陽像を焦点面に結び,X線CCDを検出器として用いています。6種類のフィルタで太陽を撮像することにより,太陽プラズマの温度・エミッションメジャーなどの物理量を温度解析によって求めることができます。「ようこう」上に搭載されたマイクロプロセッサにより,フィルタの選択,露出時間,観測領域を自動制御しています。
|
 図3.1:軟X線望遠鏡(SXT)
|
|
「硬X線望遠鏡」は,太陽フレアが作り出す高エネルギー電子・超高温プラズマからの硬X線放射の撮像観測を行い,フレアにともなう磁気エネルギーの解放機構,とくに粒子加速機構及び硬X線放射機構の解明を目的としています。HXTは,64個のすだれコリメータから構成された,世界で初めての「フーリエ合成型」のX線望遠鏡です。64個の空間フーリエ成分を地上のコンピュータを用いて像合成を行います。第21太陽極大期(1979-1982年)に活躍したSMMや「ひのとり」にくらべ,時間分解能(0.5秒),空間分解能(5秒角)ですぐれています。また,4種類のエネルギーバンド(14-23-33-53-93keV)でフレアの硬X線像をとらえることができ,30keV以上の高いエネルギー領域での撮像観測を初めて実現しました。
|
 図3.2:硬X線望遠鏡(HXT)
|
|
「ブラッグ分光器」は鉄などの高階電離イオンが発する軟X線の4波長域の輝線スペクトルを高分解能で分光観測することができます。これにより,フレア中のプラズマの加熱や運動の様子を解明することができます。BCSは日英米国際協力で開発されました。
|
 図3.3:ブラッグ分光器(BCS)
|
|
「広帯域スペクトル計」は,軟X線(2-30keV)から,硬X線(20-400keV)・ガンマ線(0.2-100MeV)にいたる広いエネルギー域のスペクトル観測を目的としています。なお,ガンマ線領域のスペクトル計は,宇宙ガンマ線バーストのモニターとしても活躍しました。フレアのスペクトル観測を行うことで,フレア時に生成される高温プラズマの加熱メカニズムや,高エネルギー電子やイオンの非熱的な加速メカニズムを明らかにすることを目的としています。
|
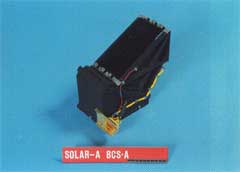 図3.4:広帯域スペクトル計(WBS)
|
(矢治 健太郎,坂尾 太郎)