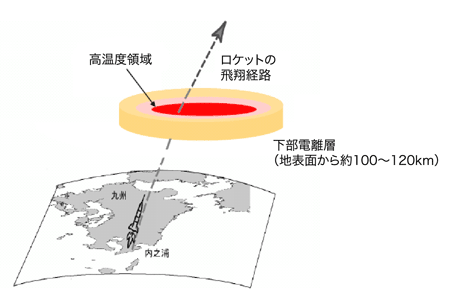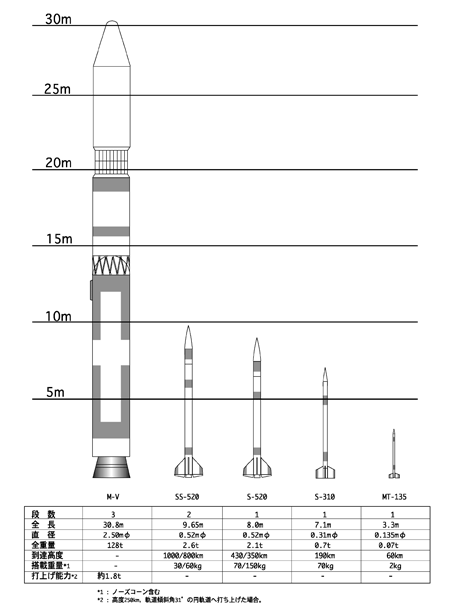TOP > トピックス > トピックス > 2006年 > 観測ロケットS-310-37号機噛み合わせ始まる
![]()
観測ロケットS-310-37号機噛み合わせ始まる
来年1月に打上げ予定の観測ロケットS-310-37号機の噛み合わせが 12月4日から始まっています。この観測ロケットは、高度約150km まで上昇して電離圏下部に発生する高電子温度層の生成メカニズムを 解明する事を目的としています。打上げを約1ヵ月後に控え、ロケット には観測機器(PI)と共通計器(CI)が組み上げられて、着々と準備が 整いつつあります。今後、振動試験、衝撃試験、スピンタイマー試験等 を経て、打上げへと進んでいきます。(実験主任 阿部琢美)


1.ロケットの概要
(1)ロケット名 : S-310-37
(2)ロケット全長 : 8 m
(3)ロケット全重量: 0.8 t
(4)搭載機器重量 : 59.4 kg
(5)到達高度 : 140 km
(6)水平距離 : 178 km
2.実験場所
宇宙航空研究開発機構 内之浦宇宙空間観測所
3.実験予定日
2007年1月16日(火)11時00分
(実験を延期する場合の期間は、1月17日〜2月28日)
4.実験観測の内容『下部電離圏の高温度層生成メカニズムの解明』
(1)実験の目的
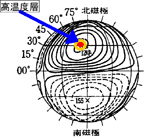
[電離圏電流系の分布]
地球表面上の昼面(正面が12時)での分布を表します。実線は反時計、点線は時計回りの電流を表しています。電流系の中心は緯度30度付近に存在します。
電離圏中の高度105〜110 kmの領域で冬季の午前11時前後という限られた条件において、電子の温度が背景に対して局所的に数100Kから時には1000Kに達する程の上昇を示すという特異な現象が、過去に行われた観測ロケット実験により報告されています。
その後の研究によって、この温度上昇は右図に示すような電離圏中に存在する電流系の中心付近(緯度30度付近)に発生する事がわかってきました。
本実験の目的は、観測ロケットを用いて、この電流系の中心付近で電子温度、電子密度、電子エネルギー分布、電場、磁場の総合観測を行うことによって、電子温度を上昇させるメカニズムを解明することにあります。
電離圏と呼ばれる空間は電波を反射する特性をもつため無線通信にとって重要な領域であるとともに、GPS受信機で使用する電波が電離圏を通過することからも、この領域は我々の生活にも関連していることがわかります。
今回のロケット実験の目的である「高温度層の生成メカニズムの解明」がなされ電離圏に関する我々の理解がさらに進むと、無線通信の信頼性やGPSを用いた位置測定精度が向上し、電離圏の利用分野の更なる発展につながるものと考えています。
(2)実験の概要
本ロケット実験の目的は上に述べた高温度層の生成メカニズムの解明にありますが、これを達成するために、
a) 冬季の午前11時頃
b) Sq電流系の中心が内之浦上空に位置する
c) 高温度層の存在が予想される領域をロケットが観測可能
という条件下で各種測定器を搭載したロケットを打ち上げ、高温度層内においてプラズマの総合的(プラズマ温度・密度、磁場、電場)な観測を実行します。
電離圏電流系の位置は地上に設置した磁力計のデータを見ることによって判断できます。日本各地に設置された磁力計のデータをリアルタイムでモニターし、電離圏電流系の中心が内之浦上空を通過している事を見極めて、ロケットの発射を行います。
観測ロケット実験の概念図 |
観測ロケットS-310-37号機に搭載する観測機器は以下のとおりです。
| 搭載機器名 | 観測項目 | 担当 |
|---|---|---|
| 超熱的プラズマエネルギー分析器 | 電子エネルギー分布 | JAXA宇宙科学研究本部 |
| ラングミューアプローブ | プラズマ(電子)温度・密度 | JAXA宇宙科学研究本部 |
| 電子密度擾乱測定器 | 微小スケール電子密度擾乱 | JAXA宇宙科学研究本部 |
| 電子温度測定器 | プラズマ(電子)温度 | JAXA宇宙科学研究本部 |
| 電場・中波帯測定器 | DC電場、中波帯電波 | 富山県立大学 |
| 磁力計 | 磁場 | 東海大学 |
| 太陽センサー | 太陽角 | 東海大学 |
| 地平線センサー | 地平線方向 | JAXA宇宙科学研究本部 |
また、ロケット打上げ条件判断のため、地上では以下の観測を行います。
| 場所 | 観測項目 | 担当 |
|---|---|---|
| 芦別(北海道)、女川(宮城県)、久住(大分県)、奄美(鹿児島県) | 磁場 | 九州大学宙空環境研究センター |
ロケット全体図 |
2006年12月12日