
PLAINセンターニュース第107号
Page 2
 |
|
PLAINセンターニュース第107号 |
| 00 | 0 | 祢宜田 智子
日本福祉大学 情報社会科学部 |
|
|||||||||||
|
8月2日〜16日の2週間、大矢君と私は PLAIN センターで勉強させて頂きました。今回の滞在の目的は、X線天文衛星(今回に関しては ASCA)のデータ解析方法の習得と、解析の順序をまとめた初心者用の X線解析マニュアルの作成です。ですがまだまだ分からないことばかりなので、教わったことをマニュアルとして文章化するという手順となりました。 X線データ解析に必要なソフト(表1)は NASA/GSFC の一部門の HEASARC(High Energy Astrophysics Science Archive Research Center)のサイトからダウンロードできます。まずは、これらのソフトをインストールして設定する手順をマニュアル化することから始めました。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| PLAINセンターニュース第107号Page2 | ||||||||||||||
| X線データ解析のおおまかな流れは図1のようになります。 | ||||||||||||||
| PLAINセンターニュース第107号Page2 | ||||||||||||||
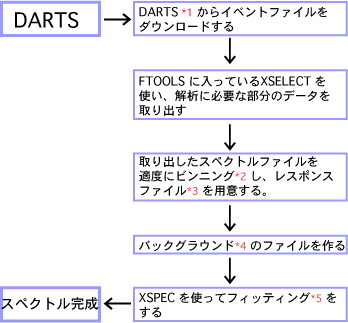 図1 おおまかな解析の流れ |
*1 DARTS |
|||||||||||||
|
*2 ビンニング |
||||||||||||||
|
*3 レスポンスファイル |
||||||||||||||
|
*4 バックグラウンド |
||||||||||||||
|
*5 フィッティング |
||||||||||||||
| PLAINセンターニュース第107号Page2 | ||||||||||||||
|
この他にも天文一般の基礎知識として学んだ話をマニュアルとしてまとめました(表2)。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| PLAINセンターニュース第107号Page2 | ||||||||||||||
これらは大学の研究でデータ解析をしようと思ったときに、最初の一歩を踏み出すための文書として、私のような文科系の学生にも分かりやすいように作りました。まだ公表できる形にはなっていませんが、このようなマニュアルが完成すれば、宇野研究室の後輩はもちろん、他の学生でも簡単に X線データ解析に取り組むことができます。 DARTS のサイトには既に「はじめての表街道2000」というマニュアルがあります。良いマニュアルで今回の解析をするときにもお世話になりました。しかし、これは研究者向けに作られているので、何も知識のない初心者が読むには大きすぎてどこから読み始めれば良いのか分からない、また文面も高度だという印象を受けました。そこで解析作業の全体をつかむことに重点を置き、解析の流れが分かるように努めました。あらかじめ解析の流れを把握してから、「はじめての表街道2000」を読めば、より深く理解できることと思います。 また作業の合間には秘書の方に6階の X線グループの研究室を案内して頂きました。偶然そこに居合わせた方たちから CCD の仕組みの説明を受けることができ、マニュアルに盛り込むこともできました。また別の日には4階で Astro-E2 搭載予定の HXD(Hard X-ray Detector)などの説明をして頂きました。硬X線 は X線のように反射させずに CdTe(カドテル:テルル化カドミウム半導体)などを使ってそのまま検出するそうで、100keV 程の X線まで観測できるそうです。ASCA では 10keV まで観測できていたのですが、その10倍も高エネルギーなX線を観測できるのです。これからどんな宇宙が見えてくるのか楽しみです。 最終日には2週間の滞在の成果を発表しました。まだまだ理解が浅く、満足のいく発表ではありませんでしたが、今まで知らなかったことや今後の研究の進め方 へのアドバイスを頂き、良い経験となりました。X線で見ていたものを可視光でも見てみるなど面白そうで、今後ぜひ試みたいと思いました。 宇宙研では行く先々で親切にご指導頂き、大変充実した日々が過ごせました。心より感謝申し上げます。発表の折にも皆様お忙しい中集まって頂いて、ありがとうございました。今後も宇宙研で得た経験を忘れずに卒業研究に励みたいと思います。皆様もくれぐれもお体には気を付けてお過ごし下さい。 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||