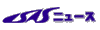| - Home page |
| - No.227 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - M-V-4/ASTRO-Eの打上げ失敗について |
| - 「おおすみ」30周年 |
| - 宇宙を探る |
| - 東奔西走 |
| - 学びて時にこれを習う |
| - いも焼酎 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |

この大気光の縞々模様の発生機構の解明にせまることが,今回のS-310-29号機ロケット実験の主目的で,これと同時に大気光の発光高度を地上から同定する方法を検証することを試みました。
発射のオペレーションは,1月10日の0時をもってタイムスケジュールに入り,2時には打上げの準備をほぼ終えました。天気の回復が遅れ,待つこと3時間余り,この日の発射時刻の限界をわずか2分残した5時50分,ロケットはランチャーを離れました。ロケットは順調に飛翔し,主観測物理量であった酸素原子密度をはじめとして,予定された全てのデータが取得されました。これまで,米国製マイクロロケットによって行われてきたアルミ箔による風の観測が初めて本ロケットで試みられて,大気物理量とこれと密接に関係している大気力学情報を一つのロケットで同時に得る目処がついたと考えます。
本ロケットは,新月であること,縞々模様の大気光が見られることに加えて,快晴であること,の3つの厳しい発射条件に加えて真夜中に打上げ作業を行うことになりましたが,大隅,山川,内之浦の3ヶ所の光学観測点,および風の観測を試みた山川,信楽との連絡も順調で,ロケット発射予定期間の初日に大きな成果を得られたことは所内の皆さんと外部関係機関の大きなご理解とご支援があったことによるものです。大気観測グループを代表して,ここにお礼を述べたいと思います。なおこの実験についてはいくつかの新聞に観測ロケット実験としては珍しく,詳しく報道されました。
(小山孝一郎)
|
|
|---|