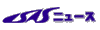| - Home page |
| - No.027 目次 |
| - 国際地球観測年(IGY)記念号にあたって |
| + 我国での宇宙観測のはじまり |
| - IGYの頃 |
| - ユーゴスラビアにロケット推進薬製造技術のうりこみ(1963年) |
| + IGYと初期のロケット研究 |
| - 我国の電離層ロケット観測の成果 |
| - 大気光および大気光学観測 |
| - 電磁圏観測 |
| - お知らせ |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
秋 葉 鐐 二 郎
1954年といえばまだ戦後という雰囲気が随所に残っていたように思う。その頃,生産技術研究所ではAVSA研究班( Avionics and Supersonic Aerodynamics )が組織されロケット研究への道が模索されていた。糸川先生の下でロケットをテーマに私が大学院に進んだ時代の背景である。
何しろ大学院の一学生であったのだから天下の大勢がどの様に推移したのかを詳しく知る由もないが「生産研究」によればIGYにAVSA研究班が協力することを決めたのは1955年の2月頃であるという。その頃すでに米国では高層観測の手段としてロケットが活用されてはいたものの,ミサイルとしてのロケットの色は濃く戦争体験を持つ世代としては何か引っかかりを覚えていたのであるがこのIGY参加を機会に突如目の前に明るい展望がひらける思いがしたものである。もっとも1957年の後半から1958年末迄の間に,高度100kmに達するロケットを作らねばならぬという条件でこれを引受けるのは当時の先生方にとって相当の決心の要ることであったようである。
ともあれ世間からみれば,計画は華々しくペンシルロケットの国分寺射場における試射から順調にすべり出したかの如く見えたに違いない。しかし実態は高度100kmに上昇するロケットとペンシルロケットとの技術格差を正しく認識するところから取り掛ったといってよい。
ペンシルロケットに使った火薬はダブルベースという種類で圧伸成型で作るため自由にいろいろな形にすることも出来ずまた大きさも最大直径10mmφが限度であった。したがって大型モータを作るためにはこの様な入手できる形の火薬をさながら傘立てに傘を並べるが如く(野村教授の表現による)に配列して燃焼室に仕込むという方法がとられた。そしてこの様にして実現できるであろうモータを組合せて要求性能が達成されるかどうかの見通しをつけるのがまた大仕事であった。
供試モータは馬車で運ばれた…!?(道川)
|
信じられない光景だが……。(道川)
|
何しろ計算機といえば手廻しの卓上計算機か計算尺しか一般には使えない時代である。糸川先生の御希望通り次の日に結果を出すのは並大抵のことではなかったし,出した結果が100kmはおろか,20kmにも達しないものばかり,流石の先生も途方に暮れた御様子で若輩の私に迄どうしたものかと漏らされることすらあった。そこで足りない知恵を絞った結果,燃焼後の垂直上昇軌道が位相面上で総合的に与えられることに着目し,当時渡辺勝先生が研究されていた微分解析機のお世話になりやや見通しのきく議論を可能とし,2つの性能向上の方策を具申したのも忘れられない思い出である。
1つは当時の様な短燃焼秒時のロケットでは単純に段数をふやし増速をしても空気抗力のため高々度に達することは出来ず,段間で多惰慣性飛行の間をとること,もう1つは密度の濃い大気層を避け気球から発射する方法がそれであった。
しかしそれでもモータ性能の悪さは如何ともし難く画期的進歩はコンポジット推薬の開発によりもたらされた。これによれば任意の形の推薬を鋳型法で作れるため内面燃焼型モータによる機体の軽量化が可能となるのである。小生も研究のテーマに関連してこの開発に取組んだが初期は爆発の連続で器材を購入して請求書が届く前に破片になってしまうことも稀でなく研究室出入のユシヤ製作所の主人を嘆かしめたのも語り草である。
とも角も1年余の開発期を経てこの新推薬は実用の域に達し第1段にこれを用いたK-5型の成功で一応の目安がついたのはIGYの最只中で何とか辷り込めるかどうかは続く二段式のK-6型の成否にかかっていた。私自身はその最初の成功に立合った記憶はないが1958年の6月,2号機の飛しょうでどうにかIGY観測のため機体として及第点が与えられたのであった。
その頃,「すべての機体故障は構造の責任である」といわれ苦労をされたのが現在の森所長である。
一方搭載機器の方もまた相当に心細いもので,いつも通信途絶や追尾不能の時は機体か機器のいずれの故障によるのか判らずに終ることも再三であった。そのためIGYの観測も最も単純な発音弾による風,気流の測定が主役であった。
IGYの工一スK-6型ロケット(道川)
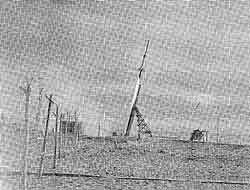
現在,K-6型の到達した高度へは一段式の小型気象ロケットが週一回のぺースで打上げられそれもやがて通算500機を越えようとしている。
(あきば・りょうじろう 宇宙科学研究所)