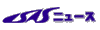| - Home page |
| - No.027 目次 |
| - 国際地球観測年(IGY)記念号にあたって |
| + 我国での宇宙観測のはじまり |
| + IGYの頃 |
| - ユーゴスラビアにロケット推進薬製造技術のうりこみ(1963年) |
| - IGYと初期のロケット研究 |
| - 我国の電離層ロケット観測の成果 |
| - 大気光および大気光学観測 |
| - 電磁圏観測 |
| - お知らせ |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
前 田 憲 一
秋田県道川海岸でカッパー6型機(K-6)によってはじめて観測データが得られたのは,1958年の暮れであった。IGY(1957〜1958年)をめざして急いだ東大生研のロケット開発がやっと間にあった訳である。初期の観測のことは,私と平尾邦雄さんと連名のPlanet. Space Sci., Vol.9, pp.335-369,1962の記事に載っているが,初期の観測対象はロケット到達高度が低いことも考えて,気温・風,宇宙線,太陽放射の三つであった。宇宙線は11月に2回成功,気温・風は12月にはじめてデータがとれ,その後のデータと共に国際シンポジウムその他の報告に載っている。(これは私と当時大阪市大の竹尾氏の担当であった。)太陽放射の方は9月にはじまったが,フィルムの熱損傷,捲きとり故障,回収不能などで結局4回ともデータが取れずに終った。K-6の到達高度は約50kmで,平尾さんのイオン密度測定は,高度200kmの能力を持つK-8の出現を待って行なわれ,最初の成功は1960年9月で,本格的電離層観測のスタートとなった。
日本のロケット観測計画のはじまりは1954年にさかのぼる。IGYのフランス語はAGIでその為の特別委員会CSAGI(一般にクサギと言った)がICSUの中に設けられたのが1953年,日本では翌年IGY委員会ができた。この年1954年の8月から9月にかけてURSI(オランダのハーグ)とIUGG(イタリアのローマ)が開かれる予定で,これらの会合ではCSAGIは一つの目玉であった。ハーグのURSIでははじめてロケットによる電離層観測結果の報告がちょっぴり顔を出して我々を興奮させた。この時アメリカのBerknerから永田武さんに,日本でもロケットをやらぬかという話があり,永田さんと私は相談して,日本でもロケットをやりたいという結論になり,2人連名の手紙を萩原雄祐,茅誠司両先生に出した。京大の長谷川方吉先生にも別に手紙を出した。ローマのIUGGへ来てからも2人で実現の為の方途を語り合った。私のメモには長谷川先生からは返事の手紙がローマに来たとなっている。帰国後関係方面に陳情する形となり,2人の動きは翌1955年2月のIGY研連委(学術会議)と測地学審議会(文部省)の合同委員会で正式に実を結びGOのサインがでることとなった。3月から矢つぎ早やにロケット小委員会が招集された。東大生研の糸川英夫,高木昇両氏との正式の接触はこの第1回委員会で3月5日であった。
学術会議内にロケット観測特委ができたのが1956年4月,この年の9月に私ははじめて秋田県の道川を訪れた。ペンシルロケットの発射を見たのである。発射は成功したが,光学追跡の為の発煙が不十分でこの方は部分的成功ということであった。
文部省から東大を通じて生研に与えられる政府予算は1955年度はゼロ,翌年度も僅少,1957年度にはじめて予算らしい予算がついたようで,前年(1956年)の11月頃予算資料の作成に参加,1957年1月大蔵省の査定が7千万円,直ちに復活要求の作業にとりかかるという次第であった。
K-6型ロケットに搭載した発音弾

第2極年の第2年(1933年)に私は現在の電波研平磯支所で電離層の実験をはじめていたが,第2極年以後電離層研究は世界的に急激に発展し,日本では1941年に文部省に電波物理研究所ができた。これが今日の郵政省電波研究所につながっている。
IGYを契機としては宇宙空間研究が爆発的に発展し,1964年に東大宇宙航空研究所ができ,これが今日の文部省宇宙科学研究所となった。ロケットの発端と時を同じくしてはじまった南極観測事業も,IGYの目玉の一つであって,1957年1月には第1次観測隊のオングル島上陸という所まで進んだ。これは今日の国立極地研究所(文部省)の創設(1973年)につながっている。
極年もIGYもそれらの年だけの観測が大切なのではなく,それにいたる迄の世界の科学者の計画・準備,それ以後の協同観測,データの交換,研究成果の討議などに意義がある。国内的に見ても研究所の創設,大型機器の購入,協同利用,研究者人口の増加などの引き金になるところに大きな意義がある。さてこの次はどのような飛躍が期待されるであろうか。
(まえだ・けんいち 京都大学名誉教授)