No.284
2004.11

|
|
|---|
No.284 |

ISASニュース 2004.11 No.284 |
|
|
|---|
|
惑星が生まれるところを見たい!
赤外・サブミリ波天文学研究系
|
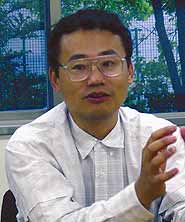
|
かたざ・ひろかず。
1961年,兵庫県尼崎市生まれ。 1990年京都大学大学院理学研究科修了。京都大学大学院理学研究科研修員,科学技術庁科学技術特別研究員(郵政省通信総合研究所勤務)を経て, 1992年,東京大学理学部天文学教育研究センター助手。 2000年4月,宇宙科学研究所助教授。専門は赤外線天文学。すばる望遠鏡の中間赤外線撮像分光装置COMICSを開発。現在は,赤外線天文衛星ASTRO-F,SPICAの開発に携わる。 |
|---|
 |
今月号の「宇宙の○人」で紹介している「がか座β星における微惑星のリングの発見」の論文はイギリスの科学雑誌『Nature』(2004年10月7日号)に掲載され,新聞各紙でも取り上げられました。研究グループの一人として,観測したときから大発見の感触はあったのでしょうか。 |
|---|---|
 : : |
実は,まったくありませんでした(笑)。すばる望遠鏡に取り付けた中間赤外線撮像分光装置COMICSで,がか座β星を観測したのは2003年12月です。観測は2日間でしたが,どちらもいまひとつの天気でした。がか座β星は南天にあり,すばる望遠鏡があるハワイでは高くまで昇ってきません。高度の低い天体は大気の影響を受けやすく,天気が悪いと観測データの精度は極端に落ちます。観測所への報告書には,「天気が悪く,観測データは多分使い物にならないでしょう」と書いたほどです。 がか座β星は,星の周りに塵とガスから成る円盤を持つ,とても有名な天体です。このような円盤の中で,塵が集まって微惑星となり,微惑星が衝突・合体を繰り返しながら惑星が誕生すると考えられています。中間赤外線を使うと,円盤をつくっている塵を観測することができます。COMICSを開発しているときから,がか座β星を狙っていました。しかし,なかなか観測する機会に恵まれず,ようやく念願がかなったときは天気が悪い。ちょっと悲しかったですね。
ところが,岡本美子研究員が観測データの解析を進めていくうちに面白そうな結果が出始めた。円盤が放つ中間赤外線をCOMICSで分光観測すると,塵の大きさと種類が分かります。その結果,微惑星がリング状に分布していることが明らかになってきたのです。「これはNature級の発見だ」と分かるまでに2ヶ月かかりました。 |
 |
今回の発見を可能にしたポイントは? |
 : : |
まずは,すばる望遠鏡の性能。そしてCOMICSの性能です。分光データを取りながら天体の像もモニターするという観測しやすさへの配慮の行き届いた中間赤外線の観測装置として,世界で最も早く立ち上がったCOMICSを用いることで,今までにない詳しい観測が可能になったのです。 |
 |
 さんは,なぜ赤外線天文学を選んだのですか? さんは,なぜ赤外線天文学を選んだのですか?
|
 : : |
赤外線が,人類にとって新しい波長の電磁波だからです。新しいことを開拓していくのが好きなんです。新しい波長で宇宙を見ると,必ず新しいものが見えてくる。それが面白い。 |
 |
2000年に宇宙研に移り,現在は赤外線天文衛星ASTRO-F,SPICAの開発をされているそうですね。 |
 : : |
がか座β星の円盤は,1983年に打ち上げられた赤外線天文衛星IRASの観測によって発見されました。IRASは初めて赤外線で全天を観測した衛星です。IRASよりももっと高い感度・分解能で全天を観測し,赤外線天体のカタログを刷新しようというのが,ASTRO-Fです。たくさんの円盤を観測することで,円盤がどのように進化していくかが明らかになるでしょう。 ASTRO-Fの次に計画されているSPICAは,3.5mの大口径です。すばる望遠鏡では観測できないような暗い天体も見えてくるでしょう。星の周りの円盤は塵とガスから成りますが,今観測できているのは塵だけです。大口径,そして宇宙で観測するSPICAは,ガスが放つ赤外線も詳しく観測できますから,円盤の全体像に迫ることができるようになります。 |
 |
子どものころの夢は? |
 : : |
小学生のころは,大工さんになりたかったんです。物をつくることが大好きだったので。 |
 |
では,これからの夢は? |
 : : |
がか座β星は,惑星の形成過程からいうとかなり進化していて,もう惑星ができているはずです。もっと早い段階,惑星が生まれるところを見たいですね。そのためには,地上でも宇宙でも,さらに大きな望遠鏡が必要です。 日本でも,地上に口径30mの望遠鏡をつくるという計画があります。SPICA級の衛星を複数打ち上げて干渉計にしよう,もっと大口径の望遠鏡を打ち上げようという構想もあります。でも,お金をかけて力づくで大きくしただけでは面白くない。新しいアイデアや方法を持ち込んで,今までできなかったことができるようにならないと,進歩ではありません。しかも,それを自分でやりたい。自分でいろいろ工夫して観測装置をつくり,今までほかの人が見ることができなかった新しいものを見たいですね。 |
|
|---|