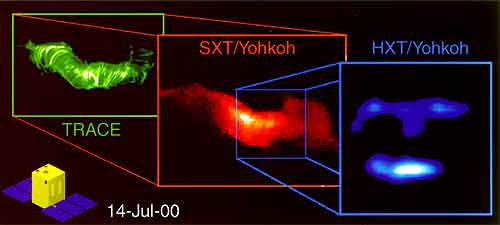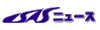| - Home page |
| - No.244 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - 宇宙を探る |
| - 東奔西走 |
| - 宇宙探査のテクノロジー |
| - いも焼酎 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
 再使用ロケット実験機第2回離着陸実験
再使用ロケット実験機第2回離着陸実験 

近ごろ都に流行るもの,へそ出しルックに行政改革,信頼性向上の伝染病・・・。
「お父さん,たったの9mで宇宙まで行けるの?」
こいつら新聞を見やがったらしい。
「あほー,千里の道も一歩からじゃ」
再使用ロケット離着陸実験は6月9日から能代実験場で始まりました。2年前の第1回実験ではエンジンむき出しの機体をふらふらと浮かしたのですが,それでもなんとか2回連日で飛ばして再使用とか繰り返しとかをやってみました。今回は大幅に機体に手を入れて,もう少しスマートな離着陸と,液水ロケットの繰り返し飛行をさらに効率よくかつ安全に行うことを目指しました。耐久性設計をしたエンジンをはじめ,RTK-GPSを用いた航法誘導など多くの部分が新しくなっています。機体はもっと高度を上げるのに備えて空気力を管理するためエアロシェルで覆いました。このため燃料の水素漏れには十分な対策や監視の仕立てを用意して運用しました。消火器まで載っています。将来高頻度で宇宙との往復を行う輸送システムや有人仕様の安全性の考察など,次の時代に求められる輸送システムに必要な技術要素の勉強の結果から,特に繰り返し飛行に関わる大事な課題を自ら経験して完全再使用のシステム構築のための基礎データを蓄積することがこの仕事の目的です。

実験は梅雨の北の端が上がったり下がったりする中,エンジン燃焼確認試験に引き続き,3回の離着陸飛行を行いました。高度は10mから20mへ,誘導ループにGPSを入れてと順次進め,6月25日の最後の実験では22mの高度まであげてしゃきっと着陸。着地点のずれは5cm。GPSを用いた誘導もうまく機能し,2日遅れながら予定した全ての実験を無事に終えることができました。前回と違ってゆったりやろうと目論んでいたのですが,天候のせいもあって結果は最後の3日半の間に3回の飛行といういつも通りのドタバタになってしまい,また図らずもQuick Turnaroundを実践することになりました。
「おーい山川ちょっと見てみ」
気球を上げて風の様子見。
「20mってあそこまで。怖いな。やめとこか」
弱気の実験主任はいつでも止める理由を探しています。これにうち勝つには大丈夫という裏付けと実験班の熱意が必要です。ヤケクソではできません。どの飛行も結果は良好で,機体やエンジンをこのくらい手なづけておけば出来上がりはこのくらい,という感覚はだいたい分かってきました。でも調子に乗ってはいけません。高度は22m,いや機体の先っぽは25mだ,と高さを競うのはほとんど意味がありませんが実験班の達成感と歓声の大きさはやはり高度に比例します。この調子では100mも上がって降りてきたらとんでもないことになりそうです。光学記録も含め保安監視のビデオまで良い映像を撮ろうと追跡に懸命です。結果はただの物笑いご愛嬌追尾カメラも出ましたが,いくつかのシーンでは少しは「未来のにおい」がするものも撮れました。においだけでは勿論ダメですがこれも大事でしょう。

この実験は完全再使用という将来の宇宙輸送の革新のための基礎実験です。「少しでも未来に近づいた」のか「ただ危ないことをやっているだけ」なのかの判断はこれを読まれた方に任せます。我々はこのような小規模の実験でも経験することは多いと知ってさらに前に進みたいと思います。千里の道のゴールにあるのは「誰でも行ける宇宙旅行」とか,「太陽発電衛星の建設」とか今の宇宙の利用とは全くスケールの違うものです。勿論この実験の他にもやるべきことはいっぱいあります。千里の道のりを加速して世の中を前に進めることが我々の目指すところです。宇宙研のロケットの元気の源です。より一層のご批判とご支援をお願いします。
(稲谷芳文)
>>>第1回打上げシーンを動画で(656K)
>>>第2回打上げシーンを動画で(604K)
(参考)動画を見るにはquicktimeが必要です。
quicktimeダウンロードサイトはこちら
|
|
|---|