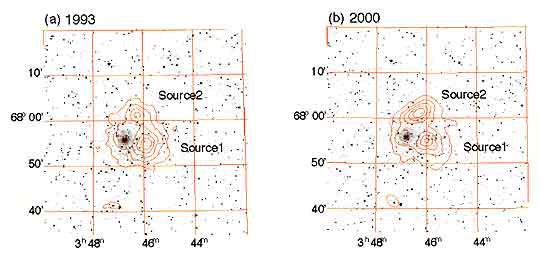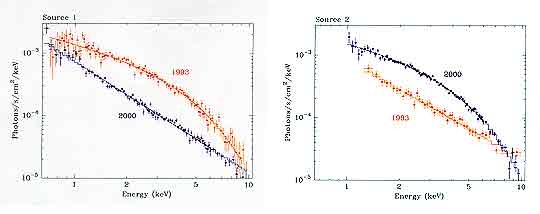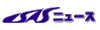| - Home page |
| - No.232 目次 |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - M-V事情 |
| - 東奔西走 |
| - 惑星探査のテクノロジー |
| - いも焼酎 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
| 用語解説 |
| バラスト |
2000年度第1次大気球実験は,2000年5月22日から6月9日まで三陸大気球観測所において実施されました。放球した気球はBT5型1機,B30型1機,B50型1機およびB150型1機の計4機でした。
B150-5号機は,エマルションチャンバーによる高エネルギー一次電子を観測することを目的に5月31日に放球されましたが,放球直後に気球頭部に取り付けてある排気弁が不具合をおこし,三陸大気球観測所北東約3kmの山中に着地しました。観測器は6月5日にヘリコプターにより完全な形で回収されました。
B30-68号機は,気球を一定高度に長時間浮遊させるためのオートレベルコントローラの飛翔性能試験を目的に6月3日に放球されました。本実験で,気球が水平浮遊状態に入ったことをコントローラが認識し,バラスト投下高度を正しく設定でき,疑似日没状態で正しくバラストを投下できることが確認できました。
B50-46号機は,15〜25kmの高度で大気ガンマ線スペクトルを観測することで,ニュートリノ振動について確実な議論ができるようにすることを目的として6月5日に放球されました。15,18,21,25kmの各高度で30分から1時間の水平浮遊状態を実現することができ,数GeVから数10GeVに渡るエネルギー領域での大気ガンマ線のスペクトルが5〜10%の精度で観測することができました。
BT5-19号機は,日本で開発した超薄膜新ポリエチレンフィルム(厚さ3.4ミクロン)で製作した容積5,000m3気球の飛翔性能試験を目的に6月7日に放球されました。本気球は,予定高度43kmまで正常に上昇し,所期の目的を果たすことができました。本実験の成功により,フィルムの性能および接着技術が実証されたことになり,超薄膜フィルムを用いた気球の大型化の目処を立てることができました。
(山上隆正)

|
|
|---|