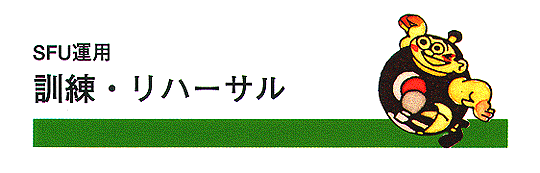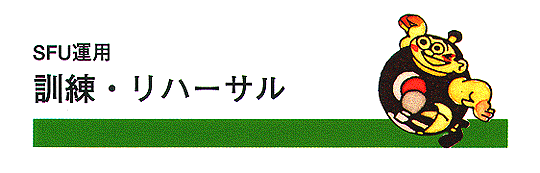ある日のこと,宇宙研の廊下でばったり出会った二宮教授に申し渡された。
「少しSFUの仕事を手伝うように!」
「はあ〜」
何でもトレーニングとやらを担当するようにとのこと。SFUのことを全く知らない自分がトレーニング担当? 第一,宇宙研でのこれまでのロケット打上げや衛星関係の仕事で,ことさらトレーニングという言葉がでてくるような大げさな訓練を行った覚えがない。
その後しばらくして,NASAヒューストンにあるジョンソンスペースセンタにSFUのエキスパートの方々と同行することになった。会議の席上,二宮先生がトレーニング担当として私を紹介した。直ぐにNASA側の訓練担当責任者が後ろの方から愛嬌よく手を挙げて挨拶を送ってくれた迄は良かったが,別の訓練担当者から「おまえの方は訓練チームとして行動するのか,それともおまえ一人でやるのか?」との質問が出された。その時は,頼りなさそうな私を見て出た当然の質問であると解釈した。しかし,その後NASA側の訓練チームは100人以上の制御,通信,電源,操作,操縦,―――等各分野の専門家で構成され,充実した訓練設備を使って,連日訓練に専念していることを知り,先の質問の意味が判ってきた。これはえらいことを引き受けてしまったと後悔しても遅かった。SFU関連の分厚い書類と戦って,少しでも他の人たちに,追いつく努力をするしかなかった。
SFUチームの訓練は日本側だけで行う国内訓練から始まった。 最初のうちは,衛星と地上局がコンタクト出来る10分程度の時間内に,必要なコマンドを送りきれず途方に暮れた。しかし,作業手順書の見直しと繰り返し訓練の結果,なんとか時間内に,完了できるようになった。
次のステップでは外国局が参加した。予定されている時間に,相手局の準備が出来ていなかったり,通信回線が必要な時間に確立しなかったりして,始めのうちは惨憺たる状況であった。そのうち,旨くいく時もあるというレベルに達した。ここで学んだ大きな収穫は,このようなオペレーションでは外国局を100%当てにするのは現実的ではないということである。この体験は,実際のSFUの運用に入ってから大いに役立った。外国局を使った運用が旨くいかない場合でも,誰一人慌てることなく,「まあ,こんなもんだろう」の一言で落ちついて対応策を練ることが出来た。
訓練のハイライトはスペースシャトルによるSFUの回収である。回収はスペースシャトルの管制を行うNASAジョンソンスペースセンタが全体の指揮をとり,何本もの司令電話回線を同時に使って,厳しい制約時間内で,英語で行われるために非常に複雑なものとなった。全てが順調に行くとした場合の標準運用訓練から始まり,熟練度が上がるにつれて,様々な異常事態が想定された。最後の頃にはこれ以上壊しようがないほどの異常事態が訓練問題に挿入された。またスペースシャトルの全搭乗員,ジョンソンスペースセンター管制室,スペースシャトルやSFUと電波で結ぶための国内,国外局,そして相模原SFU管制室等が全て参加する大規模な総合訓練も実施された。 訓練終了後は「もうだめ!」と言わんばかりの疲れきった面々もしばしば見受けられた。
図35. 大忙しの訓練チーム

訓練チームは「いじめ」を楽しんでいたわけではない。訓練を受ける人達ほどSFUに精通してないグループが訓練問題を作成するためには大変な努力を要した。NASA,NASDA,ISAS,訓練担当メーカからなる訓練チームのメンバーが何度も何度も電話会議,電子メイル,ファックス,そして時には直接顔をつき合わせて問題の作成を行った。実際の訓練ではトラブルへの判断は訓練側の予想と異なることもあり,臨機応変に対応する必要があるため,舞台裏もてんてこまいの状態となった。
実際の運用では訓練問題に非常に近い事態が起こり,まさに「山が当たってしまった」と言うのが実感である。
(橋本正之)