No.190
1997.1
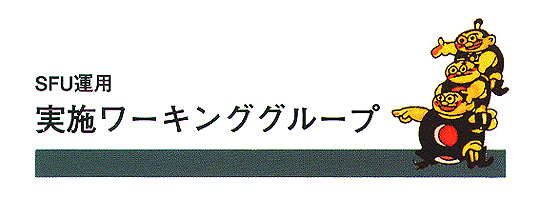
No.190 |
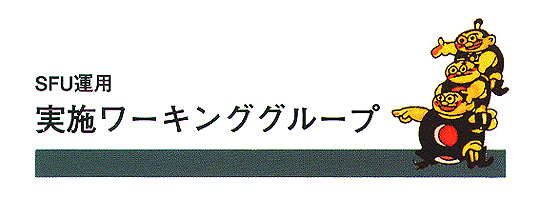
|
| - Home page |
| - No.190 目次 |
| - 新年のご挨拶 |
| - SFU特集にあたって |
| - SFUプロジェクトを終えて |
| - SFUシステム |
| - SFU実験 |
| - SFU運用 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
| - SFU略語 |
| - CDR |
| - CSR |
| - DSN |
| - EM |
| - JSC |
| - MCC |
| - PFM |
| - POWG |
| - SEPAC |
| - SFU |
| - SOC |
| - STM |
| - USEF |
| - NASA安全パネル |
| - STS-72 |
三省庁共同でプロジェクトを進めるに当たり,「SFUの開発等のために実施する作業に係るインタフェース調整上の技術的な問題等について検討・調整を行う」ことを目的とした,「SFU実施ワーキンググループ」が,昭和62年5月末,栗木教授を主査として関連実施機関,即ち宇宙科学研究所・宇宙開発事業団・通産省宇宙産業課(無人宇宙実験システム研究開発機構)で結成された(新エネルギー・産業技術総合開発機構は後にメンバーとし登録された)。
昭和62年は基本設計フェーズであり,NASAのスペースシャトルで回収されるSFUの設計はどのようにあるべきか等のコンセプト作りの話題が中心であった。また,共同購入による費用削減を計ると共にコアシステム機器/ミッション機器の信頼性確保のため,部品/材料専門委員会が開催されたのもこの時期であった。シャトル搭載のための安全審査フェーズ0も昭和62年冬に開催された。NASAとの間の調整は「SFUシステムの国内・国外調整」等で詳述されると思われるので,ここでは割愛するが,シャトルによるSFU回収概算費用算出,回収契約文書の検討に手を付け始めたのもこの時期であった。実験・観測機器の検討はこれまで担当各機関で独自に進められていたが,これらを取りまとめる実験総括ワーキンググループ(EIWG)が設置されたのは昭和63年夏のことであった。
平成元年はSFU構造・熱モデル(STM)及びエンジニアリングモデル(EM)の製作と安全審査フェーズĄの対応を中心に展開した。連日連夜サブシステム間のインターフェース調整,NASA安全性要求を満足するための設計変更検討等で明け暮れた。そして平成2年1月から10月まで筑波宇宙センターを借用し行われたシステムSTM試験,10月から翌年3月まで三菱電機鎌倉製作所でシステムEM試験が実施された。
これら一連の作業を通じ重量が大幅に超過することが判明したため,プロトフライトモデル(PFM)製作に当りサブシステム毎に削減重量を割当てることにした。しかしコアシステム機器のみでは吸収できず,当初搭載ミッション機器重量とし予定していた1トンを900ʉに変更せざるを得なくなった。
SFUコンテナの製作を行ったのもこの時期である。コンテナの直径は5mにもなり,輸送に当り道路を管轄する建設省と交通安全を管轄する警察庁の特別許可が必要であることが判明し,幾度となく許可取得のための陳情に出かけた。
平成3年度は最終設計審査会(CDR)とそれに続く安全審査フェーズ˘を中心に展開したが,同時に実施三機関のSFU打上げ/回収に係る基本協定の協議と,NASAとの Interim Agreement (中間契約)の協議が並行して進行し,それぞれ平成4年1月31日,2月14日に締結された。NASAとの調整はこの後も延々と続き,本契約は平成6年2月7日になってしまった。この間の経緯は「打上げ業務契約書締結物語」を参照戴きたい。
平成4年初夏に至りH-˘ロケット打上げ1年延期が確定的になった。平成6年1〜2月期打上げを目指し,軌道上運用準備,PFM組立総合試験準備を大騒ぎして進めていた我々にとり,1年延期の報は一瞬安堵の感を与えたものの,延期に伴う保管・NASAとの調整等,省庁をも含む問題となり更に忙しい夏になってしまった。平成4年9月1日から平成5年11月にかけて筑波宇宙センターを借用し実施されたPFMのシステム試験は,推進系の加圧に当り高圧ガス取締法上の取扱問題の調整はあったが,NASAとの間で懸案となったモーダルサーベイ試験も無事終了することができた。
安全審査フェーズŁは,NASAと本契約が締結できた直後の平成6年3月から開催された。最終安全審査でもあり,審査ボードメンバーと火花を飛ばす激論を繰り広げる一瞬もあったが,最後は審査委員長からSFUの安全性はよく考えられていると褒められ一同安堵の胸を撫で下ろしたものである。
(松岡 忍,(財)無人宇宙実験システム研究開発機構)
図36. JSC構外にあるリージェントパーク会議場
|
|
|
|
|---|
|
|---|