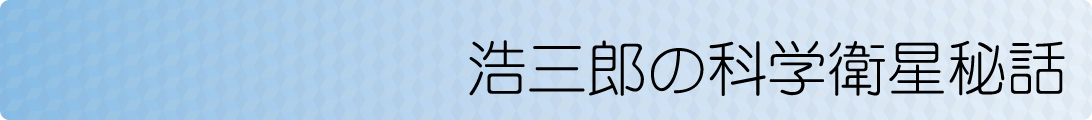TOP > レポート&コラム > ISASコラム > 浩三郎の科学衛星秘話 > 第2回 日本初の人工衛星「おおすみ」誕生(後編)
![]()
第2回 |
 |
| (ISASニュース 2002年9月 No.258掲載) |
 |
受信レベルとしては、136MHzのビーコン信号は正常で、ロックオンしたときのレベルが-133dBm、最高で-113dBmでした。296.7MHzパイロット信号および295.6MHzテレメータ信号は低めでした。
その後、第2周目の受信を18時30分06秒から18時41分23秒の間に行いましたが、受信レベルは低く、翌2月12日第6周の受信はきわめて微弱な信号を捉えたのみで、第7周の受信も試みたが受信できませんでした。米国航空宇宙局の追跡でも、南アのヨハネスブルグ局が、2月12日4時30分(日本時間)に弱い信号電波を受信したのが最後でした。この結果、「おおすみ」の信号は発射後14〜15時間で途絶したものと思われます。
搭載した電池は30時間以上の寿命と推定されていましたが、予想以上の高温になったため電池の容量が急速に失われ、予定より早く信号の途絶を招いたと考えられます。電池が搭載されている計器部の温度上昇は、第4段燃焼の際にモーター部に蓄積した熱が伝わったもので、設計の際にモータケースを黒色にし放熱を良くしたり、機器の取り付けの熱絶縁、機器をアルミニウム蒸着のマイラー膜で包む放射防御等対策はされていましたが、予想以上の蓄積熱量があり放熱しにくいところがあったものと考えられます。後日、送信機の温度が上がると周波数が高くなる特性があるので、搭載したものと同等のもので温度試験を行った結果、予想以上に高温まで電波を出し続けていたことが確認されました。
「おおすみ」の軌道は遠地点5,151km、近地点337kmと、当初の予想に比べ近地点が低く遠地点がいちじるしく高いものでした。これは飛しょう経路が低かったのと、第4段の速度成分が大きかったことによるものでした。
衛星の軌道推定は18mφパラボラアンテナが296.70MHzのパイロット信号を自動追尾した時の角度データと136MHzビーコン信号のドップラー受信機から得られるドップラーデータを用いて行われました。即ち、ドップラー・シフトから距離変化率を求め、これを積分して角度データと組み合わせることによって軌道推定を行う方法が取られました。推定は良く合っており、追跡のための有力なデータを提供することができました。
「おおすみ」は32年以上経った今でも地球を回っています。昨年内之浦の栄楽技官が、NASAの軌道情報をもとに「おおすみ」の撮影に成功したことはすでに報じられています。打ち上げ時の軌道と比較すると遠地点高度がかなり低くなってはいますが、仮に遠地点が1日に80〜100m下がるとしても、まだまだ地球を回り続けると考えられます。
当時ロケットの性能計算をしていた計算機について少しふれてみましょう。飛翔経路の計算は空気抵抗のような非線形項を含んでおり、数値計算が必須で、手まわし計算機しか実用にならず、数多くの計算をこなす努力は並大抵ではない時代でした。性能計算にコンピュータが本格的に使われるようになったのは、内之浦に移った1962年頃でした。
ロケットの飛翔性能計算式として、L-4S計画の始動に伴い、1964年頃から3次元6自由度の運動方程式が衛星投入までの軌道計算で使われており、当時大学院生だった松尾先生、的川先生、上杉先生が昼夜計算しておられたのを思いだします。
1964年に宇宙研にディジタル計算機HIPAC103とHITAC5020Fが導入されて計算能力が向上しましたが、それでも今では数秒の計算が1時間近くかかっていたと思う。しかし衛星投入が風まかせと評された第1段ロケットの風の影響を吟味する上では威力を発揮していました。
当時もミッション達成上、第4段計器部の重量に厳しい制限が加えられました。マグネシウムを主材料とする軽合金を用い、金属ケースは最小限度にとどめ、わずかに高周波部と電池の気密保持にのみ使用されていました。テレメータ送信機の既製の筐体にドリルで多数の孔をあけて(1号機と2号機のみ)減量を図るなどポッテイング、コネクタ、ネジ1本に至るまで重量の管理を行う苦労もありました。衛星重量の軽量化はここから始まったと思います。
こうして実験班が心血を注いだL-4Sによる衛星が誕生しました。成功を実験班と共に喜び町をあげて歓迎してくれた内之浦の方々の協力が大きな力になりました。今でもその時の感謝の気持ちは忘れられません。
(井上 浩三郎)
|