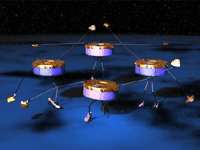PLAINセンターニュース第93号
page 4
ドイツ便り〜Cluster-II衛星のデータ環境について
衛星の概要
さて、科学目的の説明が長くなったので話が前後してしまいましたが、衛星の概要を紹介しておきます。Cluster-IIの4機の衛星は2000年の7月16日と8月9日の2回にわたって2対の衛星がカザフスタンのバイコヌール基地からソユーズロケットを使って打ち上げられました。4つの衛星には公募を経てそれぞれに愛称がつけられていてSC1=ルンバ、SC2=サルサ、SC3=サンバ、SC4=タンゴと呼ばれます。「4つのClusterカルテットが宇宙空間でダンスを繰り広げる、」というイメージ(図4)で命名されたそうで、いかにもヨーロッパ風の洒落た名前です。軌道の遠地点は地球半径の19.6倍、近地点は地球半径の4倍の極軌道衛星で軌道周期は57時間。スピン衛星でスピン周期は15rpm、スピン軸は黄道面に垂直となっています。衛星の大きさは直径2.9 m、高さ1.3 m、重さが2,000 kg(科学機器71 kg)で、長さ50 mの4本のアンテナと2本の長さ5 mのマストが伸びています。1つの衛星上には11の科学観測機が搭載されており(表)、4つの衛星の構成はすべて等しいものになっています。2000年夏の打ち上げから年末にかけての約5ヶ月間に初期運用として各観測機のチェック等が行われましたが、4つの衛星で計44の測定器のうち、1つの衛星のイオン分析器と別の衛星のポテンシャルコントローラー、計2つが残念ながら正常に動作しないことがわかりました。とはいえ、44のうち42もの機器が正常動作しているということは大変素晴らしいことです。これらの衛星群の管制は主にドイツのダルムシュタットにあるESAの宇宙管制センター(ESOC: European Space Operations Center)で行われ、スペインのヴィラフランカにある15 mアンテナからコマンドが送信されます。一方、衛星からのテレメトリーは同じくヴィラフランカにある15 mアンテナから取得され、ESOCを経て各データセンターへ生データが配布されることになっています。テレメトリーは一部、米国の深宇宙ネットワークのサポートを受けて受信されます。ヴィラフランカでの可視時間は約10時間ですが、4つの衛星のデータを受信するために1機あたりの正味は2時間半に限られてしまいます。この為、各観測機器はいくつかの観測モードを備えており、重要なイベント時(磁気圏境界面通過、等)にのみ詳細なデータを取得する(バーストモード)ように工夫されています。それでも、総データ量は1日あたり平均約1 Gbyteにもなり、約2年間のミッション・ライフで800 Gbytes弱のデータを取得することになります。44もの観測機器のいくつもの観測モードを整理してコマンド計画を作成するのが大変な仕事であることは想像に難くありませんが、この仕事はイギリスにあるJSOC(Joint Science Operations Center)で行われます。各機器のPIからのリクエストに応じてJSOCで衛星へ伝送するプログラムを作成し、それをESOCから衛星へ伝送するということになっているようです。さて、今回はそろそろ与えられた紙面が尽きてしまったので、本題である「ESOCで取得されたデータがどのように配布されデータベース化されているか」については次回に話を続けたいと思います。
| Topics |
| ・何故4つの衛星なのか? |
|
・衛星の概要 |
| ・近況報告 |
| 観測機器名 | 観測項目 |
|---|---|
| ASPOC | Active Spacecrafgt Potential Control (ポテンシャルコントロール) |
| CIS | Cluster Ion Spectrometry (イオン) |
| EDI | Electron Drift Instrument (電場) |
| FGM | Fluxgate Magnetometer (磁場) |
| PEACE | Plasma Electron and Current Experiment (電子) |
| RAPID | Research with Adaptive Particle Imaging Detectors(高エネルギー粒子) |
| DWP | Digital Wave Processing Experiment (波動) |
| EFW | Electric Field and Waves (電場) |
| STAFF | Spatio-Temporal Analysis of Field Fluctuations (波動) |
| WBD | Wide Band Data (波動) |
| WHISPER | Waves of High Frequency and Sounder for Probing of the Electron Density by Relaxation (波動) |
|
|
|
何故4つの衛星なのか? |
近況報告 |