新 SIRIUS システム (利用形態) -- 最終回
今回で最終回になりますが、新SIRIUSシステムの利用形態についてお話します。詳細については、新 SIRIUS システムの使用手引書を参照して頂くこととし、ここではその概要についてお話します。
新 SIRIUS システムは、科学衛星によって取得された衛星観測データの処理・解析を目的としたシステムです。世界各局で受信された科学衛星データはデータ伝送回線等により、宇宙科学研究本部に送られてきます。このデータは基本処理と呼ばれる処理を施した後、整理された形で新 SIRIUS システムに格納され利用者に提供されます。
新 SIRIUS システム上の衛星観測データは、衛星毎に受信局毎の受信単位等の単位で管理されています(前回 12 月号参照)。利用者はこのデータを、時刻(衛星観測時刻)やパス番号(受信年月日等を冠したデータ識別番号)によって指定し SDTP(Space Data Transfer Protocol : 宇宙研定義による標準データ転送方式)やファイル転送によりワークステーションへデータを受け渡すことが出来ます。また、Web版画面検索により登録データの確認や軌道データの表示等をすることができます。これらについて以下で説明します。
1. 利用者への衛星データの受け渡し形態
-- 1.1 プログラムインターフェース
-- 1.2 ファイルインターフェース
2. 登録データの検索
-- 2.1 ファイルインターフェースによる検索一覧情報の獲得
-- 2.2 Web版画面検索
3. おわりに
1. 利用者への衛星データの受け渡し形態
利用者ワークステーションとの衛星データの受け渡し形態としては、プログラムインタフェースとファイルインタフェースの二つがあります。
1.1 プログラムインタフェース
プログラムインタフェースは、SDTP 関数を使用したソケット通信により利用者ワークステーションへ SIRIUS 登録データを直接受け渡すインタフェースで、データは、PCA PDU(Physical Channel Access Protocol Data Unit)、VCDU (Virtual Channel Data Unit)、パケット等を指定することによりその形態でデータが受け渡されます。図1にプログラムインタフェースの概念図を示します。
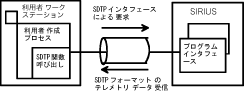
図1. プログラムインターフェース概念図
1.2.ファイルインタフェース
ファイルインタフェースは、利用者ワークステーションより、リモートシェルコマンド(rsh)を起動しておこなうものです。利用者側から要求するデータの条件(衛星名、データ種別、データ期間)を設定したパラメータファイルを予め CPU サーバに転送しておき、rsh コマンドにより CPU サーバ上のファイルインタフェースを起動し、その後 CPU サーバ上に作成された衛星データファイルを ftp 等により取得する手順で実行します。図2にファイルインタフェースの概念図を示します。
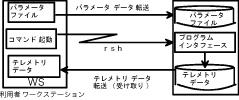
図2. ファイルインターフェース概念図
2. 登録データの検索
新 SIRIUS 上の登録データ検索(表示)の方法には、一覧情報のファイル転送による方法と Web 版画面検索による方法とがあります。
2.1 ファイルインタフェースによる検索一覧情報の獲得
衛星データのファイルインタフェースによる方式と同様、SIRIUSに格納されているデータの検索一覧情報をファイルの形態で利用者に提供するものです。
2.2 Web版画面検索
新 SIRIUS 上に登録されているデータを Internet Explorer 又は Netscape のブラウザを使用して検索表示するもので、
ができます。付加機能として、
- 衛星データの 10 進及び 16 進ダンプ機能
- 指定データワードの図形表示機能
があります。以下の図は初期タイトル画面、衛星名選択画面、パス情報表示画面、衛星データダンプ画面の例です。
|

図3. 初期タイトル画面
|
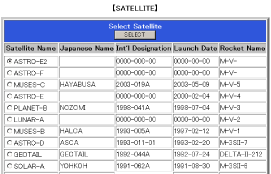
図4. 衛星名選択画面
|
|
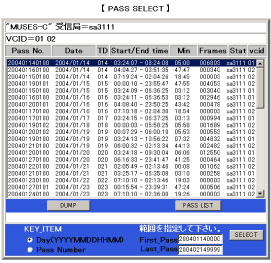
図5. パス情報表示画面
|
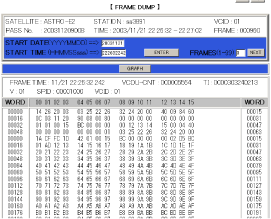
図6. 衛星データダンプ画面
|
3. おわりに
新 SIRIUS システムは構想から8年余の歳月をかけて開発したシステムです。このシステムは平成10年に小規模システムが稼動開始しておりますが、いまだ開発途上のコンポーネントもあります。今後も、種々の機能を追加すると共にシステムの高速化を図って行くつもりです。このシステムが宇宙科学研究に寄与することを願っておわりとします。
|

