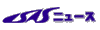| - Home page |
| - No.294 目次 |
| - 宇宙科学最前線 |
| - お知らせ |
| + ISAS事情 |
| - 科学衛星秘話 |
| - 宇宙の○人 |
| - 東奔西走 |
| - いも焼酎 |
| - 宇宙・夢・人 |
| - 編集後記 |
| - BackNumber |
2005年度第2次気球実験
 |
|---|
| BU60-2号機のガス注入の様子 |
2005年度第2次気球実験は,8月15日から9月3日まで,三陸大気球観測所で4機の気球実験が予定されていました。16日には震度5の地震に見舞われましたが,幸い大きな被害を受けずに実験を継続することができました。今年度はジェット気流が北海道の北にまで上がり,気球を太平洋上に出すことができないため,なかなか放球するチャンスがありませんでした。
8月22日にやっと第1号であるB100-13号機の放球準備作業に入りましたが,作業中に不具合が発生し,気球のみ放球するというアクシデントが起きました。この実験の目的は,高エネルギー電子および大気ガンマ線の観測でした。観測器は無傷で完全な形のまま地上に残されたため,来年度以降,再挑戦することとしました。
その後,再び上層風の条件が悪くなり待機状態が続き,その上台風11号の到来などでスケジュールが大幅に遅れましたが,8月28日7時40分にBU60-2号機を放球することができました。実験の目的は大気重力波および成層圏オゾンの観測であり,地上から中間圏下部に当たる高度51.5kmまでのオゾンおよび風向,風速,温度データを,高度分解能5mで取得することに成功しました。この気球は到達最高高度の世界記録を達成した同型気球の2号機であり,50kmを超える高度での観測は,今回が日本で初めてとなりました。
8月29日18時8分にB30-71号機の放球を行い,気球は高度33.8kmで水平浮遊状態に入りました。実験の目的は,夜光および雷放電に伴うVLF電波の観測でした。観測装置はすべて正常に動作し,所期の目的を果たすことができました。今後,詳細な解析を行い,高々度発光現象および発光メカニズムの解明を進める予定です。
B200-6号機は,無重力実験装置の2重殻構造の実験部およびシステムの動作実証試験を目的として実施する予定でしたが,上層風の条件が本実験には適さないため,来年度以降に延期としました。
(山上 隆正)
|
|
|---|