No.286
2005.1
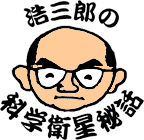 ISASニュース 2005.1 No.286
ISASニュース 2005.1 No.286
No.286 |
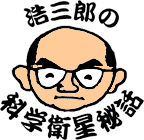 ISASニュース 2005.1 No.286
ISASニュース 2005.1 No.286
|
|
|
|---|
|
磁気圏観測衛星「あけぼの」その2井 上 浩 三 郎 「あけぼの」 「あけぼの」の最初の大きな試練は,打上げの1年半前にやってきました。フライトモデルの製造中に,輸入品のC-MOS IC(シーモス集積回路)の中に不良品があることが発見されたのです。これはICのリード部分のハンダメッキがはがれ,基板へのハンダ付けができなくなってしまう不具合です。関係者による検討の結果,追加輸入の手続きを取るのと並行して,同じICを使用している機器については,日本で改修することになりました。 IC製造メーカーの改修方法の指示のもとに,NEC(日本電気)社内において信頼性を考慮しつつ慎重に改修作業を実施していきました。当時衛星システムを諸先輩とともに担当されたNECの萩野さんは「ぎりぎりのスケジュールではありましたが,関係者の努力によりフライトモデル製造に間に合い,無事打ち上げられました。軌道上でも問題なく,改修がうまくいったことが確認されてほっとしました」と語っておられます。
南極昭和基地に建設した大型受信アンテナ「あけぼの」の観測領域が極域上空であるため,地上衛星受信局はKSC(鹿児島宇宙空間観測所,現在の内之浦宇宙空間観測所)のほかに海外に置く必要があり,データ取得率を100%近くにするため,カナダのプリンスアルバート,スウェーデンのエスレンジ,そして南極昭和基地を使用しました。当時第30次南極地域観測隊隊長兼越冬隊長として越冬され,昭和基地の大型アンテナの建設にご尽力された国立極地研究所の江尻全機先生は,その完成までの苦労をこう語られています。 「日本は中低緯度に位置するため,大量のデータを受信する地上局を極地方に持つ必要があり,諸外国の受信局への依託と併せ,日本の南極昭和基地に大型受信アンテナを建設することが検討されました。それで日本の南極観測を担っている国立極地研究所が設計・建設・維持運営すべてを担当することになったのです。自然条件の厳しい,また建設作業も夏期間の1ヶ月と限られている南極で,しかも米国でさえ実現できていない,直径11mのパラボラアンテナと受信局を作ることは,“南極を知らない無謀な計画”との批判もありましたが,第29次隊でアンテナ土台と局舎の建家,第30次隊でアンテナ本体と直径17mのドーム(円形天井),局舎内の制御・受信・記録系,基地から4km離れた島にコリメーション用アンテナなど,すべて完成し,すぐにEXOS-Dの軌道投入直後の受信に成功,太陽電池パドル展開の確認もできました。その後,膨大なデータがこのアンテナで取得されました。後日,南極でのアンテナ建設のノウハウを聞きに,POLAR衛星の打上げ支援の要請も兼ね,NASAから技術者が国立極地研究所を訪ねてきました」。
科学的成果「あけぼの」は1989年2月に打ち上げられて以来,多くの観測データを取得しており,放射線損傷のために劣化したオーロラ撮像装置のCCDを除いては今もなお有意義な観測を続けて,数多くの成果を挙げています。ここでは詳細な成果を報告できませんが,大きな科学的成果を2つ紹介しますと,その一つが「極域電離圏から大量の酸素イオンが定常的に流出する現象の発見」であり,もう一つは「オーロラが真夜中あたりで爆発的に輝きを増し大きく発展していく,いわゆる磁気圏嵐と呼ばれる現象を,オーロラ撮像装置がとらえた」ことです。
いまだ現役
「あけぼの」は打上げ以来,約16年が過ぎ,日本における衛星運用の最長記録を更新しています。 |
|
|---|