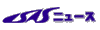| - Home page |
| - No.225 目次 |
| - 所長の任期を終えるに当たって |
| - 研究紹介 |
| - お知らせ |
| - ISAS事情 |
| - 宇宙を探る |
| - 東奔西走 |
| - 学びて時にこれを習う |
| - いも焼酎 |
| - BackNumber |

11月15日の午後,皇太子殿下同妃殿下が宇宙科学研究所を御訪問になった。かねてから最先端での宇宙科学研究活動を両殿下にご覧いただきたいと望んでいたので,まことに喜ばしいことであった。
まずご覧いただいたのは本館1階ロビーの展示である。宇宙科学研究所の歴史と成果の概要に続いてロケットと科学衛星計画をご紹介し,ローバー実験をご覧いただいた。両殿下は私達の説明に熱心に耳を傾けてくださり,次から次へと質問をしてくださったので,説明にも熱が入り予定の時間を超過するほどであった。ペンシルロケットからM-Vに至る発展に感心なさったり,松尾教授がポケットからロケットの燃料をとりだしてお見せすると「柔らかいのですね」と驚かれるなど,自然にとけこんで下さったのでお話ししやすく,的川教授はジョークでの実力も発揮できたようであった。
続いてM-3S IIの実物大モデルをご覧いただきながら飛翔体環境試験棟にご案内し,ASTRO-E計画をご説明したあと振動試験室で実機をご覧いただいた。大きな望遠鏡を搭載し,熱制御のためカプトン膜で覆われて金色に輝く実物の衛星に迫力を感じられたようで,ここでも沢山の御質問をいただいた。続いて特殊実験棟で「ようこう」による太陽コロナの観測データを御紹介した。X線で見るコロナの劇的な変動に感嘆なさり,宇宙の謎への御興味を深められたようにお見受けした。またASTRO-Eでも「ようこう」でも,共同研究について外国人研究者たちに直接ご質問をなさり,国際協力が日常的に行われていることを実感していただくことができたと思う。
こうして2時間あまりのご滞在時間はまたたく間に過ぎ,「ASTRO-Eの成功を楽しみにしています」のお言葉を残されて御機嫌よくお帰りになられた。
(西田篤弘)
|
|
|---|