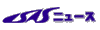これまで米,ロ,仏において,地上試験や飛行試験が行われて来ましたが未だゴールは示されていません。ここで特に記述しておきたいことは,地上風洞試験では高温空気を吹き出す特殊なエンジン燃焼風洞が用いられますが,可能な模擬飛行マッハ数は約8が上限で,それを越えるマッハ数には衝撃波を利用して空気のエンタルピを高める高温衝撃風洞が用いられることになります。しかしその性質上試験時間は数ミリ秒と極めて短いものであり,従ってマッハ8以上での実証には飛行試験が是非とも必要になります。
その天候が変わり始めたのは小山気象班チーフが天気と強気をみやげにKSCに到着してからである。6月29日には雨を嫌う頭胴部を整備搭に運び,全段結合を行う計画であったが,どの天気予報を見ても雨の予報。日曜日の28日は晴れの予報なので28日に作業を行い,月曜日の29日を休みにすることも検討していた。しかし小山気象班チーフはきっぱりと「28日も29日も問題なし」と予言。実験班として信じるべきは勿論我が気象班の予言。結果は29日には雨は降らず晴れ間も現れ,予言的中。気象班の信頼は一気に上がる。気象班は続けて「4日の打ち上げまで天候は絶好調」と追い打ちをかける。この時点では天気予報は曇り時々雨又は曇りの日々を予報していた。30日,ロケットを整備搭から出し,発射姿勢での動作チェックも快晴とは行かないまでも無事終了。翌7月1日からは晴れ続きで雷も皆無。この時期としては考えもしなかった幸運。作業は快調に進み,気象班に対する信頼は益々高まることとなった。ところで,6月28日の夜,「予測を誤った」と某班チーフからかかってきた電話は,私の幻聴だった事にしておこう。
7月2日には写真のように好天の中,電波テストを無事終了。4日の打ち上げに向けて準備完了である。翌3日15時からタイムスケジュールに入り,打ち上げの為の徹夜の作業が始まった。毎度のことであるが,何と手慣れた実験班であることか。各班間の連携を保ちつつ,確実かつ迅速に,どんどん作業は進められて行く。実験主任など居ても居なくても良さそうである。万一の商用電力停電に備えて自家発電機も起動されるが,必要最少限の電力を賄う能力しかない。冷房は一斉に切られ,照明も必要最少限に絞られる。ロケット搭載機器と衛星は内部電源に切り替えられ,着脱コネクタが外される。発射準備完了である。-60秒からのカウントダウン。発射。頑張れM-V。瞬間,半地下の管制室も揺れた。
(おのだ・じゅんじろう)