No.184
1996.7
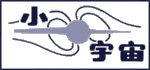 ISASニュース 1996.7 No.184
ISASニュース 1996.7 No.184
No.184 |
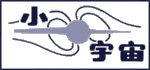 ISASニュース 1996.7 No.184
ISASニュース 1996.7 No.184
|
|
|
|---|
|
高野 忠光衛星間通信は,人工衛星(広くは宇宙飛翔体)間を,レーザ光で結ぶものです。これに対し電波による衛星間通信は,アメリカのデータ中継衛星TDRSで既に実用されています。レーザ光は電波に較べ,はるかに高周波数なので広帯域伝送が可能となり,ビーム光を細くできるので受信電力を増加し装置を小形化できます。また,地上の光無線通信に較べ,大気による吸収・散乱が無いという条件の良さも有ります。初期にはレーザ光源として,気体レーザや固体レーザが,検討されました。しかしこれらは電波システムに較べ,大きな利点を見い出せませんでした。それが再び注目されたのは,最近のことです。その技術的要因は地上での光ファイバ通信およびその部品(半導体レーザ,光ダイオード,光増幅器,等)の進歩に,また需要としては衛星を用いた大量データ収集システムや,前回の「衛星通信」で説明したLEO衛星間の通信があります。 光衛星間通信システムは上り系と下り系を1対として,構成されます。図1は典型的システムについて,片系のみを示します。送信側では,半導体レーザダイオードに順方向電流を流して発光させます。同時に,送るべき電気信号でダイオード電流を変化させることにより,出力光を変化させます(直接変調)。いわば発振器と変調器が一体化されているわけです。この光を,光アンテナ(一種の望遠鏡)を通しビーム状にして,相手に向けて送りだします。受信側では,光アンテナでなるべく広い範囲の光を集めた後,光ダイオードで電気信号に変換します。これは太陽電池と同じで,光が当たると電流が起こる原理です。また感度をあげるために,逆バイアスを強くしてなだれ現象を起こさせるダイオード(APD)が多く利用されます。 光衛星間通信は,衛星という動いている物どうしで上述の光送受信を行うところに,光ファイバ通信と異なる特徴があります。すなわち受信側では受信光の特徴を抽出して,到来方向を判断し,その方向に光アンテナを向けます。この時,同じ衛星の送信系も一緒に動かします。方向調整は,大まかと細かの2段階で行うのがふつうです。例えば全体を載せた2軸ジンバルを相手の軌道情報により動かした後,受信アンテナの結像位置を4象限検出器により検出し,その情報により反射鏡の角度を微調整するという方法が採られます。 また送信ビームについては,非常に細くかつ衛星がお互い動いているために,相手に到達するまでの時間遅れを考慮に入れて,先回りで方向づけする必要があります。例えば静止衛星から軌道高度1,000Ɠの衛星に送る場合,最大0.004゜先回りします。また自分の衛星の姿勢が変われば,その分を調整の補正角度に入れる必要があります。これらの理由から光衛星間通信には,飛翔体の姿勢と軌道の情報が不可欠なため,宇宙技術と通信技術の融合が必要となります。 また光アンテナの方向調整の段階で,最初からビームを細く(すなわち平面波に)しておくと,相手にうまく届かない可能性があります。従って初めは太いビーム(すなわち球面波)で送っておき,お互いに受信を確認した後,ビームを順序細くしていく方式が考えられています。 実際に宇宙空間に光ビームを飛ばしたのは,1992年NASA/JPLの木星探査機ガリレオと地球局との間が最初でしょう(ただし無変調)。変調光を用いた最初の例は,日本のETS-Šと地球局との間です。更に衛星間のデータ伝送用に,ESAでSILEX計画が進められています。これはリモートセンシング用周回衛星SPOTと静止衛星ARTEMISの間で行われるもので,1997年に50Mbpsの衛星間回線が完成する予定です。また光衛星間通信は,深宇宙探査機とデータ中継衛星の間の通信や,重力波検出用衛星システムにも応用が考えられています。
(たかの・ただし) |
|
|---|